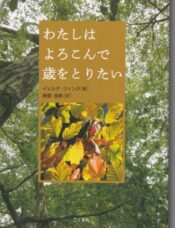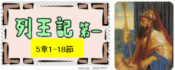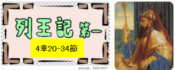マタイの福音書26章47~56節

イエス様の最後の晩餐の場面があり、その次にゲッセマネまで移動した場面がありました。私たちは順番に学んできました。
そして今日は、いよいよイエス様が捕えられてしまう、その個所となります。いつもは各章から順番に学んでいくのですが、今日は少し違った学び方をしてみようと思います。
52節、「その時イエスは彼に言われた、剣をおさめなさい。剣を取る者は皆、剣で滅びます」というこの言葉。この言葉から学んでみようと思っております。
イエス様がお話しになられたこの言葉。なぜこの言葉が出てきたのか、というところから見ていきたいと思います。
イエス様はとに戻られると、ヨハネとヤコブのところにも戻ってこられるのですが、毎回、弟子たちは眠っていたという話があります。イエス様は「その場」で祈っておられました。三回、祈られました。三回目の祈りの後にまた戻ってこられると、やはり弟子たちは眠っていました。「まだ休んでいるのですか?」とイエス様が話しておられるその時に、イエス様を捕えに来る人たちがやってきたのです。
そのような場面でしたね。イエス様に手をかけて捕えたという場面に入っていきます。
そのとき、剣で切りかかり、相手の耳を切り落としてしまったという行動に出ている者がいます。なんと、耳を切り落としてしまったのです。最終的にはイエス様がその耳を癒してくださいました。
その時に「納めなさい」という言葉が語られたのです。まさに、イエス様が話されたこの言葉には、ただ行動を止めなさいという意味ではなく、剣を手段として用いること自体を禁じる、そんな深い意味があると思います。
この「納めなさい」という言葉。非常に考えさせられる、イエス様の重要な言葉ではないでしょうか。
現代のような時代にあって、このイエス様の言葉には、とても重い意味が込められているのではないかと感じさせられます。
なぜ人は剣を取ってしまうのか。それがまず考えたいことです。
それはペテロの義務感だったのかもしれませんし、イエス様に従う者としての道を示したいという思いだったのかもしれません。でも、全体として示されているのは、もっと深い理由ではないかと思うのです。
緊急事態に私たちは弱さをさらけ出すことになります。この記事は、マタイだけでなく、マルコ、ルカ、ヨハネにも記されています。ですから、とても大事な記事だと思います。
紹介しているだけではなく、これは私たち自身の姿だと思います。
「私だけは決してあなたを見捨てません」と言っていた弟子も、いざとなれば、「あの人を知らない」と言ってしまう。私たちも、みんなそうだったと聖書には書いてあります。
特に、ひとりの女性が「あなたはあの人と一緒にいましたね」と言ったとき、「あの人は知らない」と言ってしまった。それは私たちの姿です。
非常に臆病で、そして本心を隠してしまう。それが私たちの姿なのだと思います。
でも、その姿が聖書にははっきりと描かれています。
戦争が始まってしまうと、自分の弱さを出すことが許されなくなってしまうことがあります。たとえば太平洋戦争の時、日本の兵士たちは「自分は日本人じゃない」と言うことなど、口が裂けても言えなかった、そういう状況だったと思います。
最後まで求められる厳しい状況の中、自分の弱さを出すことができず、武器を持って戦ってしまった。そのようなことがあったのではないでしょうか。
今、世界中で戦争が起きています。同じような問題が、今も繰り返されているのではないかと思います。
私たちも、もっと自分に素直になれて、自分の臆病さや弱さを認めることができたなら、もっと人と信頼し合えるのではないかと思います。
でも、それを認めたくないために、思わず剣を取ってしまう。そこに問題があるのだと思います。
「剣を取る者は皆、剣で滅びる。」これは現実の人間の姿を映し出している言葉だと思います。歴史の中で、剣を取って戦ってしまったがゆえに滅んでしまった民族や国の歴史が、数多くあるのではないでしょうか。
剣をもって傷つけられた人は、過剰な反応を引き起こす。そして必ず報復を招いていくということ。それが歴史の中で何度も語られ、そして今も変わらない現実ではないかと思います。
たとえば、教会の歴史を振り返ると、戦争と教会の関係には親和性が高かったとも言えます。
ドイツの教会の多くがヒトラーを支持していた時代。ほとんどの教会が戦争に協力していたという指摘もあります。
今のウクライナ戦争でも、ロシア政府は教会と一体となって、プーチンを支持しているとも言われています。
だからこそ、「剣をおさめなさい」というイエス様の言葉は、私たちの心に深く響かせておくべきものなのだと思います。
この言葉は、世界に向けて、本当に大切な御言葉として伝えていく必要があると感じています。
今回、「剣をおさめなさい」という言葉の意味は、単に復讐をするな、というだけではないと思います。
これは聖書全体を通して教えられていることであり、たとえば申命記32章35節では、「復讐と報復は私のもの」と神様が語られています。
ローマ人への手紙12章19節でも「自ら復讐してはいけません。神の怒りにゆだねなさい」とあります。
人間が復讐することではないというメッセージが、この「納めなさい」という言葉の背後にあるのではないでしょうか。
もう一つ、ここで教えられていること。それは、私たちが目に見える現実だけではなく、人々の心を戦いへと駆り立てる根本的な原因があるということです。
霊的な戦いというものが、私たちに求められていることなのだと教えられます。
イエス様は十字架に向かう中で、祈りによって神様に信頼し、勝利されていかれます。
闇の力と光の力が対照的に描かれている場面です。不満や怒り、憎しみに突き動かされる者たちと、神のご計画に信頼し歩んでいくイエス様。
イエス様はイスカリオテのユダに、「友よ、あなたがしようとしていることをしなさい」とイエス様は言われました。ご自分に何が起こるかをすべてご存知で、その上で歩まれていったのです。
「剣を取る者は皆、剣で滅びます。」もしイエス様が天の父にお願いすれば、十二軍団以上の御使いたちが今すぐにも来てくださる。しかし、それをされなかった。
なぜなら、「こうならなければならないと書かれている聖書が、どうして成就するのでしょうか」と語られているように、神のご計画を信じておられたからです。
「私は毎日宮で教えていたのに、あなたがたは私を捕えなかった。」という矛盾を指摘しつつも、あえてその道を受け入れられたイエス様。
自分の願いではなく、神の御心がなるようにと祈り、歩まれたその姿にこそ、私たちが目指すべき信仰者の勝利の姿があると思います。
どんな不安な時代であっても、怒りやすくなりやすい現代にあっても、私たちもこのイエス様の言葉を心に響かせて歩んでいきたい。
そう願います。