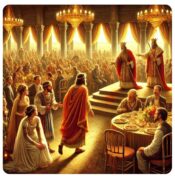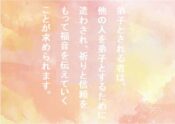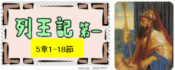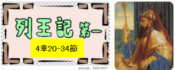マタイの福音書22章15節~33節

彼らは自分の弟子たちを、ヘロデ党の者たちと一緒にイエスのもとに遣わして、こう言った。「先生。私たちは、あなたが真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、だれにも遠慮しない方だと知っております。あなたは人の顔色を見ないからです。
ですから、どう思われるか、お聞かせください。カエサルに税金を納めることは律法にかなっているでしょうか、いないでしょうか。」
イエスは彼らの悪意を見抜いて言われた。「なぜわたしを試すのですか、偽善者たち。
税として納めるお金を見せなさい。」そこで彼らはデナリ銀貨をイエスのもとに持って来た。
イエスは彼らに言われた。「これはだれの肖像と銘ですか。」
彼らは「カエサルのです」と言った。そのときイエスは言われた。「それなら、カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。」
彼らはこれを聞いて驚嘆し、イエスを残して立ち去った。
その日、復活はないと言っているサドカイ人たちが、イエスのところに来て質問した。
「先生。モーセは、『もしある人が、子がないままで死んだなら、その弟は兄の妻と結婚して、兄のために子孫を起こさなければならない』と言いました。
ところで、私たちの間に七人の兄弟がいました。長男は結婚しましたが死にました。子がいなかったので、その妻を弟に残しました。
次男も三男も、そして七人までも同じようになりました。
そして最後に、その妻も死にました。
では復活の際、彼女は七人のうちのだれの妻になるのでしょうか。彼らはみな、彼女を妻にしたのですが。」
イエスは彼らに答えられた。「あなたがたは聖書も神の力も知らないので、思い違いをしています。
復活の時には人はめとることも嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようです。
死人の復活については、神があなたがたにこう語られたのを読んだことがないのですか。
『わたしはアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。』神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神です。」
群衆はこれを聞いて、イエスの教えに驚嘆した。
( マタイの福音書 22:15-33 JDB )
これまでの章では、「主人がぶどう園に息子を送ったら、農夫たちが『あの跡取りが来た』と言って殺してしまう」という例え話や、あるいは「結婚式の披露宴に招待した客を呼んでも、誰も来ない」という話など、いくつかの例え話がありました。
これらはすべて、ユダヤ人たちを表しています。長老たちのことを指しているのです。本来、神の選びの民であったはずのイスラエルの民が、せっかく救い主が来ているのに、全く反応しない。そのように、神の心にかなっていない彼らの姿を、イエス様は例え話を通して示されてきたのです。
最初、彼らは話を聞いてもよく理解できなかったようですが、次第に「これは私たちのことをイエス様が語っているのだ」と気づくようになります。そして、その気づきに対してどう反応したかというと、マタイによる福音書 21章45~46節には、次のように書かれています。
「祭司長たちとパリサイ人たちは、イエスのこれらのたとえを聞いたとき、自分たちについて話しておられることに気づいた。それで、イエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れた。群衆はイエスを預言者と認めていたからである。」
彼らにとって、この例え話は面白くないものでした。そこで、イエスを捕らえたいという思いを抱くのですが、この時点ではそれを実行することができませんでした。なぜなら、群衆を恐れていたからです。
群衆はイエス様を預言者と認めていたため、もし公然とイエス様を捕らえようとすれば、群衆から攻撃される危険がありました。したがって、彼らは直接イエス様を捕らえることができなかったのです。
そこで、彼らはより狡猾になり、巧妙な策略を巡らせるようになります。そして、その策略が、今日の場面へとつながっていくのです。
今日の場面は、15節から始まります。
「その頃、パリサイ人たちは出てきて、どのようにしてイエスを言葉の罠にかけようかと相談した。」
彼らは、あからさまにイエス様を捕らえることができません。けれども、なんとかしてイエス様を陥れたいのです。そのためにはどうしたらよいかと考え、言葉の罠にはめようとする策略を立てました。そして、そのために相談をした、と書かれています。
その相談の結果が、16節に示されています。
「彼らは、自分の弟子たちを、ヘロデ党の者たちと一緒にイエスのもとに遣わした。」
「自分の弟子たちを、ヘロデ党と呼ばれる人たちと一緒にイエス様のもとに遣わした」ということが、彼らの作戦だったのです。
当時、イスラエルはローマ帝国の支配下にありました。ローマの属国であったため、ユダヤ人もローマに税金を納める義務があったのです。しかし、ユダヤ人たちはローマに税金を納めることを快く思っていませんでした。基本的に反ローマの姿勢を取っていたのです。
一方、ヘロデ党の者たちはどうでしょうか。ヘロデ王朝は、ローマ帝国の後ろ盾によって成り立っている王朝でした。そのため、ヘロデ党の人たちはローマの支配を認め、税金を納めるべきだと考えていました。
つまり、パリサイ人たちは、政治信条が全く異なり、本来なら水と油のような関係にある両者を、一緒にしてイエス様のもとへ送り込んだのです。この点に、彼らの策略の巧妙さが表れています。
そして、彼らはイエス様のもとにやってきて、こう言いました。
「先生、私たちは、あなたが真実な方であり、真理に基づいて神の道を教え、誰にも遠慮しない方だと知っております。あなたは、人の顔色を見ないからです。」(16節)
彼らは、非常に丁寧な言葉遣いで、敬意を払うような態度を見せています。一見すると、イエス様を尊敬しているかのようです。しかし、これは単なる策略でした。
彼らの目的は、イエス様に確実に発言させ、その言葉を利用して罠にはめることだったのです。
つまり、イエス様に話してもらわなければならないのです。もしイエス様がここで黙ってしまったり、無視されたりしたら困ります。作戦が成功しないからです。確実にイエス様に話をしてもらうために、彼らはこのような言い方をしているのです。
「真理に基づいて神の道を教え、誰にも遠慮しない方だと知っております。」
これは、「ちゃんと今まで通り話してください」という意味なのです。話をさせた上で、言葉の罠にかける。それが、彼らの用意した作戦でした。
そして彼らは、こう質問しました。
「ですから、どう思われるかお聞かせください。カエサルに税金を納めることは、律法にかなっているでしょうか、それともかなっていないでしょうか。」
この質問も、実によく考えられたものでした。
ここで「カエサル」という言葉が出てきますが、これはローマ帝国を指しています。つまり、「ローマ帝国に税金を納めることは、律法にかなっているか、かなっていないか」という問いかけなのです。
もし「かなっている」と答えれば、ローマに税金を納めるべきだということになります。そうすると、ユダヤ人たちはがっかりし、イエス様を支持していた人々も皆、離れてしまうかもしれません。まさに、それを狙った質問なのです。
しかし、もし「かなっていない」と答えれば、その場にいたヘロデ党の者たちに訴える口実を与えることになります。
つまり、どちらを答えても必ず引っかかるように、周到な準備をしてイエス様のもとへやってきたのです。まさに、罠にかけようとする、非常に狡猾な戦略でした。
このような人々の姿を見たときに、私たちは人間の心がいかにねじ曲がっているかを思い知らされます。
エレミヤ書17章9節には、次のような言葉があります。
「人の心は何よりもねじ曲がっており、それは癒しがたい。」
以前の訳では、
「人の心は何よりも陰険で、治らない。」
とも訳されていました。
人間の心は、本当に陰険で、ねじ曲がっており、それは容易に治るものではありません。それほど、人の心というのは難しいものなのです。
聖書にはそのことが書かれています。
そして、立法学者やパリサイ人たちは、表面的には非常に丁寧な態度を取り、イエス様に尊敬を示しているかのように見えます。しかし、その心の中では、実に恐ろしいことを考えているのです。
これは2000年前の出来事ですが、私たちの時代にも当てはまるのではないでしょうか。
彼らは策略をもってイエス様のもとにやってきました。しかし、イエス様は彼らの心をすべて見抜いておられました。
18節「イエスは彼らの悪意を見抜いて言われた。『なぜ私を試すのですか、偽善者たち。』」
まさに、彼らは偽善者だったのです。
ここで私たちも、自分自身を顧みる必要があります。私たちの心のどこかにも、彼らと同じような部分があるのではないでしょうか。
表面的には信仰深く振る舞いながらも、心の中ではねじ曲がった思いや陰険な考えを抱えていることはないでしょうか。しかし、イエス様はすべてを見抜いておられます。そのことを覚えながら、私たちの心を神様によって清めていただき、整えていただくことが、とても大切なのです。
そして、イエス様は見抜いた上で、こう答えられました。
19節「税として納めるお金を見せなさい。」
そこで彼らはデナリ銀貨を持ってきました。
20節「イエスは彼らに言われた。『これは誰の肖像と銘ですか。』」
21節「彼らは言った。『カエサルのです。』」
そのとき、イエス様は言われました。
「それなら、カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。」
これは、非常に見事な答えでした。
彼らの質問の核心は、「税金を納めるべきかどうか」ということでした。そこでイエス様は、「では、その税として納めるお金を見せなさい」と言われたのです。
彼らが持っていたデナリ銀貨には、ローマ帝国の偉大な支配者であり、政治家であったカエサルの肖像が刻まれていました。
そのことを確認した上で、イエス様は「カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい」と答えられたのです。
この答えによって、彼らはどちらの方向にもイエス様を陥れることができませんでした。イエス様は、彼らの策略を完全に見抜き、それを覆されたのです。
彼らはこれを聞いて驚嘆したと、22節に出てきます。とても見事で、素晴らしい対応だったと言えるのではないかと思います。
私たちも、このような対応ができたらいいなと思うことが、時々あります。意地悪なことを言われたり、心ない言葉をぶつけられたりすることがありますよね。そのとき、カッとなって言わなくていいことを言ってしまうこともあるでしょう。そうした状況で、イエス様のように冷静に対応し、適切な返答ができたら素晴らしいと思います。しかし、それはなかなか難しいことでもあります。
イエス様の返答は、非常に見事でした。その理由は、主に二つあります。
まず一つ目は、この返答によって危険を回避したという点です。彼らはイエス様を罠にかけ、陥れようとしていました。まさに、貶めるための作戦だったのです。しかし、イエス様は見事にこの応答によって、その罠を退けられました。
彼らは「納めるべきか、納めるべきでないか」「律法にかなっているか、かなっていないか」という、イエスかノーかでしか答えられないような問いかけをしました。それに対して、イエス様は単純に「イエス」または「ノー」と答えず、「カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい」とおっしゃいました。これは、「どちらも大切である」という意味を持つ返答でした。まさに、見事な答えだったと言えます。
もう一つの理由は、この答えによって、私たちが地上でどのように生きるべきかという原則を提示した点です。イエス様の言葉は、単なる機転の利いた返答ではなく、私たちが地上で果たすべき務めについての重要な教えを含んでいました。
私たちは、神にお返しをしなければなりません。神様の恵みをたくさんいただいています。日々の食べ物、生活、健康、家族──これらはすべて、神様から無償で与えられている恵みです。
そして、私たちは神様の愛によって守られています。それに対して、私たちは心と体を神様にお返しし、時間を神様に捧げ、献金を捧げ、財産をもって神様に仕えることが求められています。
しかし、それと同時に、私たちは地上の務めも果たさなければなりません。信仰者だからといって、この世の責任を放棄してよいわけではないのです。
私たちは税金を納めるべきですし、選挙にもきちんと行くべきです。また、上に立つ指導者を尊敬することも大切です。
私たちが安心して生活できるのは、国という秩序があり、制度が整えられ、法律が制定されているからです。公共サービスも、私たちが税金を納めることによって成り立っています。もちろん、税金の使われ方についてはさまざまな議論がありますし、改善すべき点もあるでしょう。しかし、私たちは国から多くの恩恵を受けていることも事実です。そのため、私たちは地上の務めを果たし、この世に対して責任を持つことが求められています。
この世には、この世の務めがあり、それを果たさなければなりません。地上において、私たちには与えられた大切な役割があるのです。イエス様の言葉は、その両方の大切さを教えています。
ただし、もう一つ付け加えるとすれば、時として「この世に仕えること」と「神に仕えること」が衝突する場合があるということです。どちらかを選ばなければならない状況に直面することもあるでしょう。
そのようなとき、聖書は「神の国と神の義を第一にする」ことを教えています。私たちは、何よりも神様に仕えることを優先しなければなりません。
このことをよく示しているのが、ダニエルとその三人の友人たちの姿です。彼らは、ネブカドネツァル王という異教の王に仕えました。彼らは心から忠実に仕え、王に対して敬意を持って接しました。しかし、彼らは神への信仰を決して曲げませんでした。
このように、私たちは地上の務めを果たしつつも、神の国を第一にすることを忘れてはならないのです。
正面から仕えたのではなく、異教徒である敵の支配者に仕えたわけですが、それでもネブカドネツァル王に彼らは本当によく仕えました。その結果、王から強い信頼を得たということが確認できると思います。
しかし、それでも例えば、王の食卓に並べられた料理を食べなかったという話がありますよね。それは偶像礼拝に関わる食物だった可能性があり、彼らはそれによって自分の身を汚したくなかったのです。神様の前で身を怪我したくないという思いから、「私たちを水と野菜で養ってください」と願い、それが認められました。
また、大きな像を作り、「これを拝め」と命令されたときには、ダニエルの三人の仲間たちはそれに従いませんでした。確かに、王様に従うことはとても大事なことです。彼らも心から仕えていました。しかし、王よりもさらに偉大な方がいます。その方への忠誠を裏切るようなことが求められるならば、それはこの世の権威であっても従うことはできないという、はっきりとした姿勢を示しました。これが、ダニエル書の中に見られる重要な例だと思います。
ですから、神には神の務めがありますが、やはり神を第一にすることが原則であると聖書は教えているのです。
また、聖書には「彼は驚嘆して帰っていってしまった」と書かれています。ここで一つの問題が回避されたことがわかります。しかし、次に登場するのはサドカイ人たちです。23節からの展開では、彼らがイエスのもとにやってきます。
23節には、「その日、復活はないと言っているサドカイ人たちがイエスのところに来て質問した」とあります。彼らは、「ある女性が七人の兄弟すべてと結婚したが、皆子を残さずに亡くなり、最後に彼女自身も亡くなった。復活の時、彼女は誰の妻になるのか」と質問しました。
24節では、「モーセは…」と、彼らがモーセの律法を根拠として引用していることがわかります。これは申命記25章5節6節の言葉です。彼らは、モーセの律法の一部を引き合いに出して質問してきました。
律法には、「もしある人が子を残さずに死んだならば、その弟は兄の妻と結婚し、兄のために子孫を起こさなければならない」と書かれています。これは「レビラート婚」とも呼ばれる制度です。ユダヤ人は家系や家族を非常に大切にしており、神の祝福を子孫にまで残していくために、この制度を重んじていました。
彼らは、この制度を根拠として、「もし七人の兄弟すべてがその女性と結婚し、子を残さずに亡くなった場合、復活の時に彼女は誰の妻になるのか」と問いかけたのです。しかし、彼らの真の意図は、「復活なんてありえないのではないか?」という主張をすることでした。そのために、わざと申命記の言葉を引き合いに出して質問したのです。
イエス様は、彼らの問いに対し、29節でこう答えられました。「あなたがたは聖書も神の力も知らないので、思い違いをしています」と。
彼らは聖書の言葉を根拠に問いかけをしましたが、イエス様からすると、「そもそも聖書の本当の意味を理解していないし、神の力を信じていない」ということになります。そして、イエス様は30節と31節で、次のように答えられました。
「復活の時には、人はめとることも嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようです。死人の復活については、神があなたがたにこう語られたのを読んだことがないのですか?『わたしはアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である』。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神です」。
イエス様の答えには、二つの重要な点があります。
一つは30節の「復活の時には、人はめとることも嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようです」という言葉です。これは、復活後の世界では地上の結婚制度が適用されないということを示しています。したがって、彼らの質問自体が誤った前提に基づいていたことになります。
地上にある結婚という制度も、そのようなものから解放され、天の御国では皆が御使いのようになる、ということですね。イエス様はそのようにお答えになり、ここに一つの重要な指摘があります。
サドカイ人たちは、この世の地上の在り方がそのまま死後も続くのではないかと考えていました。彼らは、この世の価値観から離れられず、それが永遠に続くと考えていたのです。しかし、天の御国が来たら、全く違う世界になり、全く違う関係に生かされるのです。イエス様は、このことを明確に教えられました。
もう一つのポイントは、死人の復活についてです。イエス様は「神があなたがたにこう語られたのを読んだことがないのですか」と問いかけ、復活というテーマに関連して再び彼らに指摘をされました。最初に「思い違いをしています」と述べられましたが、今度は「読んだことがないのですか」と問いかけることで、彼らが聖書を正しく理解していないことを明確に示しています。
サドカイ人たちは、聖書の言葉を引用し、それに基づいて主張していました。彼らは、自分たちは聖書を正しく理解していると自負していたのかもしれません。しかし、実際には聖書が本当に伝えようとしていることを理解できておらず、思い違いをしていたのです。そのため、神様が示そうとしている真理を正しく受け取ることができず、矛盾を抱えていたと言えます。
その後、イエス様は32節で出エジプト記3章6節の言葉を引用されました。「私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である」というこの言葉は、サドカイ人たちが非常に大切にしていたモーセの教えの中に含まれています。イエス様はその言葉を用いて、「あなたがたはこの言葉の意味を理解していないのではないですか」と問いかけました。そして、この言葉こそが実は復活を教えている証拠なのだと主張されたのです。
「私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である」と語られた神は、死んだ者の神ではなく、生きている者の神です。ここで重要なのは、「神である」という表現が現在形で記されていることです。「アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であった」と過去形ではなく、「今も彼らの神である」と記されている点が決定的なのです。
この言葉が現在形で書かれているということは、アブラハムもイサクもヤコブも死んでしまったが、それでも彼らは生きているということを意味します。まさに今、神は彼らの神であり続けておられる。つまり、彼らは復活するのです。イエス様は、この言葉が復活の真理を示していると明確に示されました。
サドカイ人たちは、復活がないという前提で聖書を読んでいたため、どの聖書の箇所を読んでもその前提に基づいた解釈しかできませんでした。しかし、よく読むと、聖書は明確に復活を教えており、それを神様ご自身が語っているのです。イエス様は、このことを彼らに指摘されたのです。
「神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神です」。
確かに、アブラハムもイサクもヤコブも、遠い過去の人々であり、すでに死んでしまった先祖です。しかし、彼らは生きており、やがて復活するのです。必ず、彼らと再会する時がやってきます。ここに、復活の希望が示されているのです。
このやり取りを聞いた群衆は、イエス様の教えに驚嘆しました。パリサイ人もサドカイ人も、何とかしてイエス様を陥れようと策略を巡らし、罠を仕掛けようとしました。しかし、最終的にはただ驚嘆するしかなかったのです。これは、イエス様の素晴らしい応答であったと言えるでしょう。
私たちにも、すでに天に召された多くの方々がいます。彼らはこの世では亡くなりましたが、信仰によってイエス様にあって今も生きており、生かされているのです。私たちは、このことを信仰をもって受け止めることができるのではないでしょうか。
先に天に移された方々が増えてきました。私たちの教会にも、多くの方が天に召されました。しかし、そうした方々も必ず復活します。もうすぐイースターを迎えますが、それは復活の希望を皆で覚える時でもあります。この希望が与えられていることを感謝しながら、共にイースターをお祝いしていきたいと思います。
ここで、いくつかの問いかけをしたいと思います。
まず、私たちは偽善者になっていないでしょうか。イエス様に癒していただき、許していただき、清めていただくことが大切です。
もう一つは、私たちが目に見えるものが全てだと考え、自分の解釈だけで聖書を理解してしまっていないか、ということです。すでに持っている前提のもとで聖書を読み込み、勝手に解釈してしまっていないでしょうか。その結果、思い違いをし、聖書をよく読んでいるつもりでも、実はよくわかっていないことがあるかもしれません。
イエス様が教えようとしておられることに、私たちは謙虚に耳を傾けているでしょうか。それとも、頑なな信仰者になってしまっていないでしょうか。サドカイ人の姿から、そのことを学びたいと思います。
本当に教えられやすい心、砕かれた心で、主が教えようとしてくださることを素直に理解し、従っていけるように。そんな柔らかな心で、主に従うことができるように。これもまた、祈りが必要なことだと思います。
そして、私たちは復活の希望に生かされているでしょうか。死で終わりではありません。イエス様は、「神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神である」と言われました。
神様は今も私たちと共におられます。私たちはいずれ死を迎えますが、必ず復活し、御国へと迎えられるのです。その希望に生かされているでしょうか。このことを、自らへの問いかけとして、恵みに生かされていることに感謝しながら歩んでいきたいと思います。
今日はここまでにしたいと思います。お祈りをして終わりましょう。
愛する神様
今日は、イエス様がパリサイ人やサドカイ人、ヘロデ党の人々と対話され、見事に応答し、真理を示された姿を学ぶことができました。
私たちも、さまざまな人間関係の中で、いろいろな思いを抱えます。時には意地悪な気持ちになったり、人を裁いてしまったりすることもあります。どうか、私たちの心を主が支配してください。そして、柔らかな心へと作り変え、また、あなたにあって強い心へと作り変えてください。
あなたによって勝利をいただき、復活の希望という恵みに生かされていくことができるように、私たちを励ましてください。
御言葉による導きを心から感謝します。
イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン