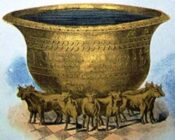マタイの福音書23章1~12節

この記事を書いている人 - WRITER -
若井和生牧師:飯能キリスト聖園教会牧師 この記事は、サイト管理者(solomonyk)の責任において、毎聖日ごとの礼拝メッセージを書き起こし、師の許可を得て掲載しております。
そのとき、イエスは群衆と弟子たちに語られた。
「律法学者たちやパリサイ人たちはモーセの座に着いています。
ですから、彼らがあなたがたに言うことはすべて実行し、守りなさい。しかし、彼らの行いをまねてはいけません。彼らは言うだけで実行しないからです。
また彼らは、重くて負いきれない荷を束ねて人々の肩に載せるが、それを動かすのに自分は指一本貸そうともしません。
彼らがしている行いはすべて人に見せるためです。彼らは聖句を入れる小箱を大きくしたり、衣の房を長くしたりするのです。
宴会では上座を、会堂では上席を好み、
広場であいさつされること、人々から先生と呼ばれることが好きです。
しかし、あなたがたは先生と呼ばれてはいけません。あなたがたの教師はただ一人で、あなたがたはみな兄弟だからです。
あなたがたは地上で、だれかを自分たちの父と呼んではいけません。あなたがたの父はただ一人、天におられる父だけです。
また、師と呼ばれてはいけません。あなたがたの師はただ一人、キリストだけです。
あなたがたのうちで一番偉い者は皆に仕える者になりなさい。
だれでも、自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされます。
( マタイの福音書 23:1-12 JDB )
23章1節ですが、その時イエス様は群衆と弟子たちに語られたということで、パリサイ人たちや律法学者たちが去った後だと思います。そこには群衆と弟子たちが残っていたわけですが、その彼らに話を始めるというのが、今日の23章の内容ということになります。「律法学者たちやパリサイ人たちはモーセの座に着いています。
ですから、彼らがあなたがたに言うことはすべて実行し、守りなさい。しかし、彼らの行いをまねてはいけません。彼らは言うだけで実行しないからです。
また彼らは、重くて負いきれない荷を束ねて人々の肩に載せるが、それを動かすのに自分は指一本貸そうともしません。
彼らがしている行いはすべて人に見せるためです。彼らは聖句を入れる小箱を大きくしたり、衣の房を長くしたりするのです。
宴会では上座を、会堂では上席を好み、
広場であいさつされること、人々から先生と呼ばれることが好きです。
しかし、あなたがたは先生と呼ばれてはいけません。あなたがたの教師はただ一人で、あなたがたはみな兄弟だからです。
あなたがたは地上で、だれかを自分たちの父と呼んではいけません。あなたがたの父はただ一人、天におられる父だけです。
また、師と呼ばれてはいけません。あなたがたの師はただ一人、キリストだけです。
あなたがたのうちで一番偉い者は皆に仕える者になりなさい。
だれでも、自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされます。
( マタイの福音書 23:1-12 JDB )
その内容をずっと読んでいくと分かるのですが、このパリサイ人や律法学者たちが抱えていた問題を、イエス様がここで指摘しておられるのが23章の主なポイントです。
そして、それが群衆と弟子たちに語られたということなんですね。ですから、パリサイ人たちが抱えていた課題を群衆や弟子たちに語ったということは、どういうことかというと、「あなたたちもパリサイ人のようになってしまう可能性がある」ということなのだと思います。そこに、きっと私たち自身も含まれているのではないかと思います。
ここでイエス様がご指摘なさっている、律法学者たちに見られる様々な課題や陥りやすい問題というのは、実は私たちも等しく抱えている課題であり、問題であり、私たちも気をつけなければならない点だということを、しっかり覚えておきたいと思います。
さて、立法学者たち、パリサイ人たちが抱えていた問題が23章の冒頭から語られているわけですが、今日の箇所、12節までの中でそれが明らかになっていきます。
まず1番目は2節です。立法学者たちやパリサイ人たちは「モーセの座についている」とあります。ここから始まっています。
「モーセの座」と呼ばれる場所があって、彼らはそこに就いているということなんですね。「モーセの座」って何だろうと私たちは考えるわけですが、これは立法が与えられ、それをイスラエルの民に教える権威を与えられた者の象徴のような座だったのだと思います。
申命記などを学んでくると分かるように、モーセは神の言葉を民に伝え、しっかりと御言葉を教えていました。そういう意味で、御言葉・律法を教える権威の座に彼らがついていた、ということが分かります。
一見、特に問題があるようには感じられないかもしれません。立法学者というのは、立法の専門家であり、誰よりも立法について詳しい人たちです。ですから、彼らがモーセの座について立法を教えるというのは、普通であれば当然と考えるところだと思います。
しかし、読み進めていくと分かるのですが、そこに彼らの「高ぶり」があったということですね。それがこの箇所から読み取れるのではないかと思います。
彼らは神様に召されてその座についたというよりも、むしろ自分から積極的にその座につき、人々に教えようとしていたのだと思います。そこには、やはり彼らの「高ぶり」が隠されていた、ということになるのではないでしょうか。
今日の結論は12節に記されています。
「誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされます。」
これが23章のメッセージの結論にあたるわけです。
この言葉を見ると、彼らにはやはり「自分を高くする」、つまり「高ぶりの罪」があったということですね。そういった高ぶりの姿勢から、様々な問題が生じていたということを、まず心に留めておきたいと思います。
2番目の問題は3節に出てきます。
「ですから、彼らがあなたがたに言うことはすべて実行し、守りなさい。しかし、彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うだけで、実行しないからです。」
ここには、彼らの「言動の不一致」、つまり「言うことと行いが伴っていない」という姿が示されています。言っていることは立派です。正しいことを語っているのですが、それを自分自身が実行していないという点に問題があったのです。
おそらく、人に教えることには積極的だったのかもしれません。しかし、自分自身を律するということはしていなかったのではないかと思います。
これも、私たちにとっても他人事ではない問題です。私たちも、聖書を学び、教えられたことを理解し、語ることが増えていく中で、言っていることと行いが一致しているかと問われると、必ずしもそうとは言えないかもしれません。
ですから、「言葉と行いは一致していなければならない」ということは、聖書のあちこちで教えられている重要な原則であり、パリサイ人たちの問題は、まさにそこにあったということです。
私たちも、言葉だけでなく、行いにおいても一致させていく者でありたいと願います。
3番目の問題は4節に見られます。
「また、彼らは重くて負いきれない荷を束ねて人々の肩に乗せるが、それを動かすのに自分は指一本貸そうともしません。」
この言葉には、「重くて負いきれない荷」と「指一本」という、非常に対照的な表現が使われています。この対比によって、彼らがいかに冷淡であったか、冷たい態度をとっていたかが強調されていると思います。
彼らは担いきれないような重荷を人々の背中にドンと束にして乗せ、苦しめておきながら、自分は一切それを手伝おうとしないのです。それは、非常に冷たい態度であり、愛のない姿です。
彼らは立法に基づいて数多くのルールを作り出し、それを守るようにと人々に教えました。「守ることで神に受け入れられる」「守ることで義とされる」と教えられた人々は、何とかしてそれを守ろうと必死になります。しかし、それによって、どんどん重荷が増えてしまい、本当に苦しむことになっていくのです。
ChatGPT:
以下に、いただいた文章を読みやすく訂正し、適切に句読点を加えたものをお送りします。語順や助詞なども、意味が自然になるように一部調整しています。
________________________________________
ところが、苦しんでいるのを見ても、彼らは何も手を貸そうとしなかった、という面があったのではないかと考えられます。そうならないように、私たちも気をつけたいと思います。
時々、「クリスチャンになる」ということを、いろいろな決まりやルールを守ることだと思っている人がいます。時々ですね、そう思って、「守らなければ祝福されないのではないか」とか、「守らなければ神様に愛されないのではないか、認めてもらえないのではないか」と思って、必死になって奉仕をしたり、献金をしたりと、そういう心境になってしまうことがあると思います。
でも、それは本来の姿ではないと思うんですね。神様は、すでに圧倒的な愛をもって私たちを愛してくださり、許してくださっています。その愛に応えるかたちで、私たちは奉仕もするし、献金もする。そういう順番なのです。
…と、ここで生活がとても苦しくなってしまうこともありますが——(すみません、ちょっとこちらの録画がうまくいっていないので…すみません。今日は色々とトラブルがありますね。あ、iPadが切れました、大丈夫ですね、はい、すみませんでした)——はい、それで私たちですね。
私たちも、そうなってしまわないように、重荷を人に背負わせておいて自分は何もしない、というような冷たい態度を取ってしまわないように、気をつけたいと思います。
さて、4番目の問題に進みます。5節です。
「彼らがしている行いは、すべて人に見せるためです。彼らは、聖句を入れる小箱を大きくしたり、衣の房を長くしたりするのです。」
4番目の彼らの問題点は、行いそのものは立派に見えても、すべて「人に見せるため」の行いだった、という点です。具体的な例もここで挙げられています。彼らは、聖句を入れる小箱を大きくしたり、衣の房を長くしたりする、と書かれています。
お手元の聖書に、聖句を入れる小箱に注釈や印がついているかと思います。その下を見ると、少し小さい字で解説がありますね。たとえば「出エジプト記13章1〜10節、11〜16節、新明記6章4〜9節、11章13〜21節」を記した4つの箇所が、区切られた小箱に入れられていたという解説です。
これは、新明記11章18節に出てくる教えに基づくものです。そこには、こんな言葉があります。
「あなたがたは、わたしのこの言葉を心と魂に刻み、それをしるしとして手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。」
つまり、忘れないように、御言葉を心に刻み、体に記しておきなさいという意味であり、神の言葉を大切にする習慣だったのです。ユダヤ人たちは、それを実践していて、紙に御言葉を書いて箱に入れ、それを額につけていました。
けれども、ここで指摘されているのは、その箱を「大きくした」ということです。本来は神の言葉に従って歩むための励ましだったはずのものが、人に見せるためのものになってしまっていたのです。
また、衣の房を長くするということについても、民数記15章38〜39節にこうあります。
「イスラエルの子らに言いなさい。彼らが代々にわたり、衣服の裾の四隅に房を作り、その隅の房に青いひもをつけるようにしなさい。」
そして、
「その房は、あなたがたがそれを見て主のすべての命令を思い起こし、それを行うためであり、淫らなことをする、自分の心と目の欲に従ってさまようことのないようにするためである。」
つまり、この房は、神の命令を思い出し、悪から離れるための助けとなるものでした。しかし、ここでも問題は「房を長くする」ことで、それを人に見せびらかすために用いていた、ということなのです。
神様に向かって信仰を励まそうとする本来の目的が、人に見せるための手段へとすり替えられていたのです。すべての行いが「人に見せるため」になってしまっていたという、具体的な例として、イエス様はこれを指摘されたのです。
彼らは、立派に生きているように見せかけながら、実は神を意識せず、人の目だけを意識して生きていた。そういう心のあり方を、イエス様は見事に見抜いて、指摘されたということです。
私たちも、本当に注意が必要です。知らない間に、信仰生活が「神の前での生活」ではなく、「人に見せるための生活」になってしまっていることがあるからです。
だからこそ、私たちはいつも「神を恐れて歩む」ことができるように、心を整えていなければなりません。神に対する恐れを忘れてしまうと、「みんなに見てもらいたい」「評価してほしい」「褒めてもらいたい」といった気持ちが出てきます。
私たちの信仰が、本当に「神の前での信仰」になっているかどうか、それをよく吟味する者でありたいと思います。
そして最後、5番目の問題として指摘されているのが、6節と7節です。
「宴会では上座を、会堂では定席を好み、広場で挨拶されること、人々から先生と呼ばれることが好きです。」
ここで指摘されているのは、「上座」「定席」を好むこと、挨拶されること、そして「先生」と呼ばれることが好きだという、彼らの心の状態です。
要するに、自分を特別扱いしてもらえることに快感を覚え、自尊心を満たそうとする、そういった心の傾向が指摘されているわけです。
それに対して、イエス様は三つのことを指摘して、教えてくださっています。そうならないようにと、三つのことを教えてくださっているのが、8節、9節、10節ですね。
「しかし、あなたがたは先生と呼ばれてはいけません。あなたがたの教師はただ一人であり、あなたがたは皆兄弟だからです。あなたがたは、地上で誰かを自分のための“父”と呼んではいけません。あなたがたの父は、ただ一人、天におられる父だけです。“指導者”と呼ばれてはいけません。あなたがたの指導者は、ただ一人、キリストだけです。」
ということで、「あなたがたは先生と呼ばれてはいけない」「誰かを自分たちの父と呼んではいけない」「あなたがたの父なる神様は唯一である」「指導者はイエス様ただお一人」ということですね。私たちの先生はイエス様、父なる神様も唯一。忘れないように。
だから、「呼ばれてもいけないし、呼んでもいけない」って、両方あるんだなっていうことが分かりますよね。呼ばれることも非常に誘惑ですけれども、呼ぶことも気をつけなくちゃいけないということです。そういうことが、ここで教えられているんだなというふうに思います。
ここに書いてあることに基づいて、私たちもよく「先生」って呼ぶわけですよね。牧師に対して「先生」と呼びますし、睦月先生とか小林一雄先生とか、みんな「先生」と呼ぶ。だから、「これに書いてあるから、もうこれからは“先生”と呼ぶのやめましょう」「小林一雄くんと呼びましょう」とか、「睦月くんと呼びましょう」っていうのも、それもまた逆の意味でちょっとおかしな問題になるかな、と思います。
こういうことは、そういう表現を否定しているわけではなくて、人間を、与えられている立場のゆえに特別視してしまうことへの危険、ということが注意されているんだと思います。
私たちはすぐ、立場とか肩書きとか、そういうものに弱いんですね。すごくね。それで、立場によって人間が成長するということもあるかもしれません。今まで平社員だった人が課長になる、係長になる、部長になるっていうことで、それによって自覚が深まり、責任感が育ち、成長するという面も確かにあると思います。
ところが、人間っていうのは弱いので、そういう立場が与えられると、だんだん自分が何か偉くなったような勘違いをしてしまう。そして、すごく優秀な人になったかのような誤解をしてしまう。そして、本当は自分は惨めで、乏しく、貧しい人間であるということをすぐ忘れてしまう。そうして、その立場にすがりついて、そこから離れられなくなってしまう。そういう弱さ、傾向を、みんな抱えているんじゃないかな、と思うんですね。
ですから、何か立場があるとすぐに特別視したくなる。あるいは、特別視されたくなる。そう呼んでもらいたい、呼びたい、という両方の作用があると思います。そうしてどんどん、人間が偉くなっていくというか、偉そうになってしまう。そういうことが、よく起こることです。私たち、とかくすごく振り回されるんだと思うんですね。
「〇〇大学を出た」とか、「どこの企業に勤めていた」とか、そういうことを、つい言いたくなる。そして、みんなもそういう人を見ると、「なんかすごい人だな」と見なしてしまう。そういう傾向っていうのは、みんなあると思います。どこの時代でも、どこの国でも、状況はみんな同じだと思います。
そうならないように。パリサイ人たちは、まさにそういう問題を抱えていて、「先生、先生」と呼ばれることをすごく喜んでいた。私たちも、みんな同じ課題を抱えていると思います。
ぜひ、そうならないように。本当に注意しなければいけない。私たちの主はイエス様であり、父なる神様は唯一の神様。本当の先生はイエス様だけなんだということを、よく覚えておきたいと思います。
でも、やっぱり尊敬は必要だと思いますよね。目上の人に対する尊敬って、とても大事なことだと思います。でも、「尊敬しながら特別視しない」という、その両立。なかなか難しいことですが、神様を恐れることから始まるのだと思います。
そして最後に、イエス様が大事なことを教えてくださっていて、今日の箇所は終わっています。
そうならないために、大事なこと。まず11節に、
「あなたがたのうちで一番偉い者は、皆に仕える者になりなさい。」
ということですね。そうならないために。私たちは、すぐにそうなってしまいやすい。でも、そうならないために大事なことは、やっぱり「イエス様を覚え続ける」ということかなと思います。
イエス様なんですよね。イエス様の姿です。
「あなたがたのうちで一番偉い者は、皆に仕える者になりなさい。」
これは、イエス様の生き様なんですね。イエス様は、一番偉かったんです。神の子、王様。その方が、すべてを捨てて、私たちに仕えるために、へりくだって仕える者になってくださった。それが私たちの主なんです。
イエス様を見ていたら、そうならない。私たちは、このイエス様をいつも見ていたら、そうならないんですよね。だから、「いつもイエス様を覚え続ける」ということが、一つ大事なことだと思います。
もう一つは、「神を恐れる」ということ。
12節には、
「誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされます。」
とあります。
「自分を高くする者は低くされる」と教えられている。誰が低くするんですか? それは神様ですよね。
「自分を高くする者は、神様によって低くされてしまう。」
「自分を低くする者は、神様によって高くされる。」
そうです。誰が高くしてくださるのか。絶対的な支配者である、主権者である神様が高くしてくださる。その神様がおられるということを覚え続けて、神様の前に恐れを持って生きるということ。
そのことを大事にしていく時に、私たちはこうした傾向から守られていく、ということですね。そういうことが分かるんじゃないかなと思います。
神様を忘れると……今の世の中って、本当にそうなってると思うんです。どんどん高ぶる。みんな、「お金がある」「地位がある」「権力がある」と、どんどん高ぶっていく。そして誰もそれを抑えられないような世の中になってしまっている。
弱い人、何も持っていない人は「負け組」と呼ばれて、どんどん見捨てられ、本当にひどい生活を強いられている。もう、そういう社会です。今もそういう現実です。
神様を見失ってしまうと、もう必ずそういう世界になってしまうんですよね。
でも、私たちは幸いなことに、イエス様と出会って、救いをいただき、神様を恐れる者に変えられたわけですよね。
この世とは全く違う生き方を与えられている。そして、高ぶれば必ず、私たちは低くされます。
でも本当に、イエス様のように身を低くしていく時に、神様は必ず祝福してくださって、高めてくださいます。
それが神様の約束であることを、ぜひ覚えていてください。
ぜひ、私たちもこれからイエス様に習って、神様の前にその心を持ち、主に従っていきましょう。
たとえば、人間関係においても、人との関わりの中においても、神を恐れながら、一緒に仕え、隣人に仕えていく者でありたいと思います。
はい、では今日はここまでにして、お祈りをしたいと思います。
神様、私たちはすぐに高ぶりやすく、そして本当に人からの評価を求めて、高く評価されて自尊心を満たしたいという、深い欲望を持っている者であります。
けれども、聖書によってそれを示してください。そうならないように、神様、御言葉によって導いてください。
励ましてくださることを覚えて、ありがとうございます。
どうぞ、私たちの弱い、そのような罪に汚れた私たちを清めてくださり、砕いてください。
整えてくださって、本当に身を低くしてあなたに仕え、互いに愛し合うことができるように、助け導いてくださいますようにお願いいたします。
この後、心を注ぎ出して一緒に祈ることができるように、導いてください。
この学びを感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
この記事を書いている人 - WRITER -
若井和生牧師:飯能キリスト聖園教会牧師 この記事は、サイト管理者(solomonyk)の責任において、毎聖日ごとの礼拝メッセージを書き起こし、師の許可を得て掲載しております。