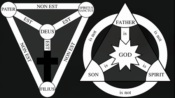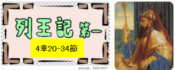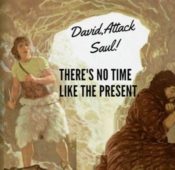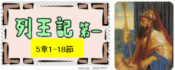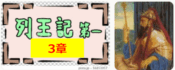第一列王記3章
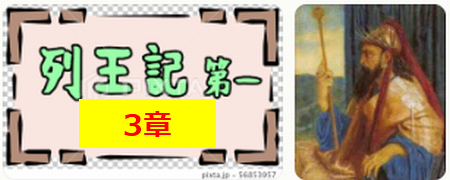
※聖書本文は最下にあります。
要約
ソロモンの生涯前半の信仰と知恵、そしてそこに潜んでいた堕落の萌芽について。
ソロモンの礼拝と「高き所」
ソロモンは多くの生贄と全焼の捧げ物をささげ、誠の神を礼拝しており、ここでの礼拝は異教の神々への礼拝ではないと説明されています。
しかし「高い所」という語が用いられていることは、のちの異教礼拝と堕落を予感させる表現として捉えられています。
初期の信仰と後の堕落
王になったばかりのソロモンは、概ね信仰的であり、父ダビデの信仰を継承して王の務めを果たしていたと評価されます。
ところが晩年になると、異教の神々への礼拝をイスラエルにもたらし、その後の王たちの時代まで続く偶像礼拝の歴史の始まりとなったと指摘されています。
政略結婚と信仰の曖昧さ
エジプトのファラオの娘との結婚など、国際情勢の中で政略結婚を選んだ背景には、安全保障や国の安定を求める思いがあったと考えられます。
しかし、そこには神に完全に依り頼みきれず、人間的な力やこの世の知恵に頼るソロモンの曖昧さが表れていると解釈されています。
聖書が描く信仰者像
聖書はソロモンを、素晴らしい面と残念な面を併せ持つ一人の信仰者として描き、どんな偉大な信仰者にも弱さや失敗があることを示していると語られます。
信仰を最後まで全うすることの難しさが強調され、イスラエル王国の歴史にもその弱さが刻まれているとされています。
夢の中での神の問いかけ
神は夢の中でソロモンに現れ、「あなたに何を与えようか。願いなさい」と問いかけます。
私達に対しても「自分なら何を願うか」を考えさせる問いかけとして用いられています。
ソロモンの願いと「聞き分ける心」
ソロモンは、長寿や富、敵の命ではなく、「善悪を判断し、神の民を裁くための聞き分ける心(知恵・判断力)」を求めました。
自分を「小さな子供」と告白し、多くの民を治める責任の大きさに対する自分の小ささを自覚しつつ、課題と責任のギャップの中で知恵を求める祈りをささげたと説明されます。
私たちへの適用(祈りと依り頼み)
私たちも課題や責任の大きさに比べて自分の小ささや弱さに打ちのめされ、「もうだめだ」となりやすいが、そこでこそ神に願うことができるのだと勧められます。
遠慮して願わずに自分の殻に閉じこもるのではなく、「願いなさい」と語られる神に信頼して祈るべきだと語られます。
神の御心にかなった祈り
ソロモンの願いは主の御心にかなった祈りであり、神はそのことを喜ばれたと説明されます。
神はソロモンに比類ない知恵と判断の心を与えるだけでなく、彼が願わなかった富と誉れも与えると約束し、御心にかなう祈りには願い以上のものが与えられると強調されます。
ダビデの道に歩むなら
さらに、ダビデのように神の掟と命令を守って歩むなら日々を長くするという約束が示され、神がソロモンを励まし、愛をもって配慮しておられることが語られます。
こうしてソロモンは、神からの知恵によって王としての務めを果たせるよう整えられていったとまとめられます。
二人の遊女の事件と知恵の実例
続く箇所では、二人の遊女が一人の生きている子をめぐって争う有名な裁きのエピソードが紹介されます。
ソロモンが「子を二つに切り分けよ」と命じるふりをすることで、真の母親の愛をあぶり出し、誰が本当の母かを見抜いた知恵の具体例として説明されます
筆耕
今日の箇所は、王位が確立したばかりの時に、ソロモンについて、二つのエピソードがまず紹介されているということが分かります。一つは、ソロモンがエジプトの王ファラオの娘と結婚し、エジプトと縁戚(政略結婚)の関係を結んだというエピソードが最初に紹介されています。
一節には、「ソロモンはエジプトの王ファラオと縁戚関係を結んだ。彼はファラオの娘を看取り、ダビデの町に連れてきて、自分の家と主の家、およびエルサレムの周りの城壁を築き終えるまで、そこにとどまらせた」ということが記されています。
エジプトの王ファラオとの縁戚関係、すなわち政略結婚だったと言っていいと思います。そのエジプトと結びつくことによって、何らかの益を得ようとした、もしくはそのことによって国の安定を得ようとしたことが意図されていたのかもしれません。いずれにしても、まずそうしたことをそのまま行ったということが、最初に出てくるわけです。
この出来事は、後に十一章一節から三節に記されている出来事に続いていく、ひとつのきっかけになったと考えられます。十一章の一節から三節には何が書いてあるかというと、その後のことなのですが、十一章の一から三まで読んでみますが、『「ファラオの娘の他に多くの異国人の女、すなわちモアブ人の女、アンモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヒッタイト人の女を愛した。この女たちは主がかつてイスラエル人に、『あなた方は彼らの中に入ってはならない。彼らをあなた方の中に入れてもいけない。さもないと彼らは必ずあなた方の心を転じて彼らの神々に従わせる』と言われたその国々のものであった。しかし、ソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。彼には七百人の王妃としての妻と、三百人の側女がいた。その妻たちが彼の心を転じた」という出来事に繋がっていきます。
いろんな異国、異教徒たちですが、異国の女性たちを妻にしてしまって、その数は七百人、側女が三百人という、とんでもない妻と側女がいたということになります。そして、そのことのゆえに、妻たちが彼の心を転じた、ということに繋がっていったということが、全体を読んでいくと見えてくるように思います。
ここの「あなた方は彼らの中に入ってはならない。彼らをあなた方の中に入れてもいけない」という言葉は、申命記の七章二節から五節までの引用ですが、モーセが約束の地に入る前に、こういう命令が下されていて、「その地に入って、現地の人々と結び合ってはいけない。そのようにあなたの娘を彼らの息子に嫁がせたり、彼らの娘をあなたの息子の妻としたりしてはいけない。そうすると、その異教徒たちが真の神への信仰を引き離してしまう」と戒められていたのですが、その戒めを明らかに破ったということになると思います。そういう出来事が、ひとつのきっかけになっていったのです。
ですから、この一節の出来事は、ソロモンの堕落のきっかけとなる出来事が、すでにここに記されていると考えることができます。
次に、生贄を捧げたということについてですが、三節、「ソロモンは主を愛し、父ダビデの掟に歩んでいた。ただし、彼は高きところで生贄を捧げた」。このようなことを、ソロモンは二節三節でしていたと紹介されています。
この「高き所」という言葉ですが、これはこの後、列王記に何度も出てくる言葉です。そして、「高き所」という言葉が出てくると、そこは一貫して異教の神々に対する礼拝が捧げられる場所として紹介されています。
ただし、二節を見ると、当時はまだ主の名のために家が建てられていなかったので、とあり、主の宮がまだ建てられていなかったこともあったようです。さらに四節を見ると、「そこが最も重要な高い所だったからである。ソロモンはその祭壇の上で全焼の捧げ物を捧げた」と記述されています。
ここで生贄を捧げて、全焼の捧げ物を捧げて、ここで真の神様を礼拝していますよね。たくさんの生贄を用意しています。ですから、これは異教の神に対する礼拝ではなくて、誠の神様に対する礼拝だったと言っていいかなと思うんですが、でも「高い所」という言葉がここに出てくることによって、その後のソロモンの堕落を予感させるような、そんな言葉ではないかなというふうに思います。
まだ王になったばかりです。そのままにされて、ソロモンの最初の頃は概ね信仰的であったと言っていいと思います。ダビデの信仰をちゃんと継承して、本当に信仰を持って王位について、その務めを果たしていたと思います。
でも、この後を読んでいくとだんだん分かるんですけど、晩年のソロモンはどんどん神様から離れていきます。そして、ソロモンを通して、実は異教の神々に対する礼拝がイスラエルに持ち込まれていくんですよね。
その後、リハビアムなどいろんな人が出てくるんですけれども、ずっと異教徒の神々への礼拝が止まらない、そういう歴史になっていくんですね。こうしたことが見えてくると思います。
ソロモンは、ダビデが築き上げた、本当にダビデの信仰によって築かれたイスラエル王国を引き継いで、ソロモンの時にさらに繁栄が極まります。この後で出てきますが、ダビデの時よりもっと繁栄するんですよね、ソロモンの時に。でも、それが繁栄の絶頂だったんですけども、その時にすでに堕落が始まっていることを、聖書はちゃんと記しているということなんですね。
なぜソロモンがエジプトのファラオと関係を結ぼうと思ったかというのは、当時の国際情勢など色々あるのだろうと思いますが、どこかやはり神様に完全に従いきれていない、人間の力によって頼んでしまっているソロモンの曖昧な部分がここから始まっていたことが見えてくるのではないかなと思います。
概ね神様を信じているソロモンの信仰の話が出てきますが、でも聖書は面白いですね。本当に素晴らしいなと思う面と、残念だなと思う面と、両方出てきます。どんな信仰者でも、みんなそうですが、完璧に描かれないんですよね。どんなに素晴らしい信仰者でも、残念だなと思うことが必ず出てくるんですね。
そういう面がソロモンにもあったし、イスラエル王国の歴史の中にもそうしたことが現れるということですね。そのことを私たちは確認できることかなと思います。本当に信仰を最後まで全うするというのは大変なことなんだろうなと思います。
私たちも神様を信頼して歩んでいますが、でもどこかでやはり人間の力に頼り、この世の常識や自分の判断などにより頼みながら生きていることが多いのではないかなと思います。こういう記事を通して、私たちが本当に神様を信頼できるよう、最後まで一緒にお仕えできるように祈りが必要だということを覚えたいと思います。
その上で、今度は5節から進みたいと思います。ここでは、神様が夢の中でソロモンに現れた話ですね。5節、「夢のうちにソロモンに現れた神は仰せられた。『あなたに何を与えようか』」ということですね。それで、神様は夢の中で現れて、「あなたに何を与えようか。願いなさい」と問いかけます。神様はソロモンに関わってくださったという、興味深い記事です。
もし皆さんが神様から「願いなさい」と言われたら、何を願うでしょうか。いろんなものを願うかなと思います。ソロモンは何を願ったのでしょうか。願った内容は9節に出てきます。
「善悪を判断してあなたの民を裁くために、聞き分ける心を下僕に与えてください。さもなければ、誰にこの大勢のあなたの民を裁くことができるでしょうか」と答えています。つまり、神様からの問いかけに対して、ソロモンの答えは「聞き分ける心」、判断力、知恵、そのようなものを求めて祈ったということです。
それは何のためか。民を裁くためです。「この大勢のあなたの民を裁くことができるでしょうか」ということで、王になった今、本当にいろんな判断をしていかなければいけない、そのためのよき知恵と判断力、聞き分ける心が与えられるように求めたのです。
7節でソロモンはこのように祈ります。「わが神、主よ、今あなたは私の父ダビデに代えてこのしもべを王とされました。しかし、私は小さな子供で、出入りする術を知りません。」つまり、「私は小さな子供です」と言っています。
その上で、8節「あなたのしもべは、あなたが選んだあなたの民の中にいます。あまりにも多くて、数えることも調べることもできないほど大勢の民です。」とあります。
今、ソロモンは王になり、ダビデによって築かれた繁栄を極める王国を継いでいます。本当に神様が祝福して王国になり、その豊かな王国を継いで王になったのですが、経験も何もありません。そして、この大勢の民をどうやって裁くか、その現実的な課題の大きさ、責任の重さに比べると、自分は本当に小さな子供である、そのギャップの中で知恵を求めた、聞き分ける心を求めたのです。
私たちにもこういう祈りが必要なのだろうなと思います。自分が小さく、子供のように見えてしまうことが多く、今向き合う課題や責任の大きさ、やらなければならないことの大変さなどと向き合うと、自分の惨めさや小ささ、弱さを思い知り、そこで落ち込んで「もうダメだ」となりやすいかもしれません。しかし、そこで願うことができるのです。
主は「あなたに何を与えようか」と願いなさいと言ってくださるのです。しかし、意外と遠慮して願わず、自分の部屋に閉じこもって「自分には何もできない」「自分は弱い」となってしまう傾向があるかもしれませんが、願うことができます。そして願えば、必ず与えてくださる方がおられるということです。それを覚え、主に信頼し、祈ることが求められていると感じます。
ソロモンの願いは、神様の御心にかなったものでした。10節で「主の御心にかなった祈り、願いだった」とあります。そのことを神様は喜ばれ、11節「あなたがこのことを願い、自分のために長寿や富、敵の命さえ願わず、正しい訴えを聞き分ける判断力を求めたので、私はあなたが言ったとおりにする。私はあなたに知恵と判断の心を与える。あなたより前にあなたのような者はなく、あなたの後にもあなたのような者は起こらない」と答えてくださいました。
戦いや勝利、あるいは具体的な利益や祝福を求めることもできたのでしょうが、彼が求めたのは「正しい訴えを聞き分ける判断力」でした。それは神様の御心にかなった願いで、神様はそれを与えると約束してくださいました。
さらに13節、「あなたが願わなかったもの、富と誉れもあなたに与える。あなたが生きている限り、王たちの中であなたに並ぶ者は一人もいない」とあり、結果的には、願わなかったものも与えられたということです。神様の気前の良さ、祈りは必ず叶えられるということを感じます。
御心にかなった祈りは必ず応えられ、しかも願った以上のものが与えられる、神様の祝福とはそういうものだということを教えられるのではないでしょうか。また、「父ダビデが言うように、あなたも私の掟と命令を守り、私の道に歩むなら、あなたの日々を長くしよう」と約束してくださり、ダビデのように主に仕え、信仰の道を歩むなら必ず祝福されるという約束をもって励ましてくださる、そういう神様のご配慮がここに示されています。
そのようにして、神様からの知恵が与えられていきます。その後の記事、16節から最後のところまでは、知恵が与えられたことが分かる具体的なエピソードが紹介されています。教会学校などでよく話になる、子供たちもよく知っている話ですが、二人の遊女が王のところにやってきた、という話です。
二人の遊女が王のところにやって来て、一人の女性が訴える。二人の遊女が同じ家に住んでいて、それぞれ出産しました。ほぼ同じ時期に、3日違いで赤ちゃんを出産しました。夜の間に、もう一人の女性が産んだ子が死にました。眠っている間に、その女性は自分の子供と死んだ子供を取り替えてしまいました。よく見ると、自分の子供ではないことに気づいた、という話です。
もう一人の女性も訴え、22節で「生きているのが私の子で、死んでいるのがあなたの子です」と言い始め、先の女性も「死んだのがあなたの子で、生きているのが私の子です」と、お互い王の前で言い合ったと書かれています。
その中で、ソロモンはどう判断したか。24節、王が「剣をここに持ってきなさい」と言ったので、剣が王の前に差し出されました。王は言いました。「生きている子を二つに切り分け、半分をこちらに、もう半分をそちらに与えよ」と。
剣を持ってきて「生きている子を半分ずつにしなさい」と命じたのです。その時、26節、生きているこの母親は自分の子を哀れに思って胸が熱くなり、王に申し立てて言いました。「我が君、どうかその生きている子をあの女にお与えください。決してその子を殺さないでください」と。一方、もう一人の女性は「それを私のものにもあなたのものにもしないで、断ち切ってください」と言ったのです。
この時点で、どちらが母親かは明白ですよね。子供を殺そうなんて思っていない方が本当の母親です。母親であれば必ず、自分の子供が命の危険にさらされたら、絶対に命を救おうとします。たとえその子供が自分のものにならなくても、必ず命を守ろうとします。ソロモンはそれを知っていました。
そのようにして、ソロモンは見事な判断を下しました。これは自分から出てきたものではなく、神様がとっさに判断力を与えてくださった、聞き分ける心を与えてくださったからです。神様から与えられた知恵と判断力によって導かれた、ということが文脈でも明らかです。
最後の結論、28節です。「全イスラエルは王が下した裁きを聞いて王を恐れた。神の知恵が彼にあって裁きをするのを見たからである」と書かれています。イスラエルの人たち全員がそのことを見て王を恐れ、その理由は神の知恵がソロモンにあったことが分かったからです。
そのようにして、ソロモンは経験もなく、ダビデから引き継いだ王位を継いで、本当に自分には何もできない小さな者でしたが、神様から知恵と力をいただき、務めを果たすことができました。主が導いてくださった、そのことをみんなが知ることができたということです。
そのような結論に導かれたことが分かります。箴言9章10節に「主を恐れることは知恵の初め、聖なる方を知ることは悟ることである」という言葉があります。私たちも主により頼みたいものです。
ということで、3章をここまでにして、感謝してお祈りして終わりたいと思います。
「私たちの信仰をどうぞいつも支えてください。絶えず終わりまで一緒にお仕えできるように、そして主が与えてくださる知恵と判断力によって、この難しい世の中を、日常の歩みの中を、的確に信仰をもって歩んでいけるように、どうか助け導いてください。御言葉による導きに感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。」