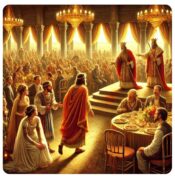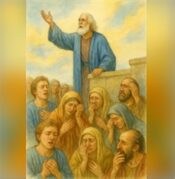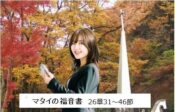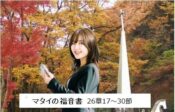マタイの福音書21章33~46節

今日の箇所は 33 節からですが、「もう一つの例えを聞きなさい」というイエス様の問いかけから始まっています。では、これは誰に対して語られた言葉だったでしょうか。
これは、イエス様のもとにやってきた祭司長や長老たちに対する問いかけの言葉であることがわかります。23 節には、すでに学んだ箇所ですが、「それから、イエスが宮に入って教えておられると、祭司長たちや民の長老たちがイエスのもとに来て言った。『何の権威によって、これらのことをしているのですか。誰があなたにその権威を授けたのですか』」と記されています。
この場面では、長老たちがイエス様のもとにやってきて、イエス様が権威ある者のように行動しているのが気に食わなくて仕方がなかったのです。イエス様が権威をもって教えられる姿がどうしても受け入れられず、「何の権威によって」「誰の権威によって」と問い詰め、まるで攻撃するかのように詰め寄ってきました。
このとき、祭司長や長老たちはすでにイエス様を殺す相談を始めていたことが、『マルコの福音書』に記されています。彼らの心の中は、怒りと憤りで煮えくり返っていたのでしょう。本当に激しい憤りを抱き、イエス様を殺したいとさえ思っていました。有罪にし、裁判にかけ、神への冒瀆罪で訴えようと挑戦してきたのです。
前回の箇所で、イエス様は 28 節において、「ところで、あなた方はどう思いますか」と彼らに問いかけました。そして、その後に話されたのが、「父親と二人の息子」のたとえ話でした。
このたとえ話では、ぶどう園の主人である父親が、二人の息子に働くよう頼みます。兄は最初「嫌だ」と断りますが、思い直してぶどう園に行き、働きました。一方、弟は「行きます、お父さん」と立派な返事をしますが、結局行きませんでした。
この話の意味について、イエス様は明確に解き明かしておられます。兄は、周辺にいた取税人や遊女たちを表しています。彼らは最初、神様から遠く離れ、罪に汚れた者と見なされ、神の救いの計画には含まれていないかのようでした。しかし、彼らは悔い改め、神の国に入ったのです。
では、弟は誰を表しているのでしょうか。それはまさに、イエス様が語りかけている祭司長や長老たち、すなわち当時の宗教指導者たちです。イエス様は彼らにこう言われました。「ヨハネがあなた方のところに来て義の道を示したのに、あなた方は信じなかった。しかし、取税人や遊女たちは信じた。あなた方はそれを見ても、後で思い直して信じることをしなかった。」
イエス様ははっきりと、「取税人や遊女たちは信じたのに、あなたたちはそれを見ても悔い改めなかった」と指摘されたのです。しかし、どうもこの言葉は彼らに十分に伝わっていなかったようです。ピンと来ていなかったのでしょう。
そこでイエス様は 33 節の場面に入り、「もう一つの例えを聞きなさい」と新たな話を始められたのです。「どう思いますか?」と問いかけをして、一つの話が終わったのですが、さらにもう一つの例え話が続きます。「もう一つの」というのは、そういう意味ですよね。一度語られた後で、イエス様は「もう一つの例えを聞きなさい」とおっしゃっています。
この導入の部分で、本当にイエス様という方は粘り強く、丁寧にこの人たちに関わっていることに驚かされるのではないでしょうか。この人たちは、本当に扱いづらい人たちだと思います。なぜなら、イエス様に敵意を抱き、攻撃し、挑戦してきているからです。まさに、向き合いたくもないような相手ですよね。私たちだったら、「こんな人とは話もしたくない」と思ってしまうでしょう。
しかし、イエス様は一度話しただけで諦めることなく、さらにもう一つの話をして、「もう一つの例えを聞きなさい」と語られました。イエス様は決して諦めず、粘り強く関わり続けておられます。このことに、まず私たちは驚かされるのではないでしょうか。
彼らに何を言っても通じません。真理をどんなに語っても、伝わらないのです。しかし、イエス様はこのたとえ話を通して、彼らが今どういう状態にあるのかに気づかせようとしておられます。そして、彼ら自身の姿に気づき、悔い改めてほしいと願っておられるのです。だからこそ、イエス様は向き合いづらい相手であっても、粘り強く関わり続けておられるのです。ここに、イエス様の大きな愛が表されていることを感じます。
私たちだったら、すぐに逃げたくなるような場面だと思います。しかし、イエス様は本当に関わるのが難しい人たちに対しても、丁寧に、丁寧に、諦めずに対応されています。そのイエス様の姿から、まず私たちは学びたいと思います。
その上で、イエス様はたとえ話を語られます。
「ある家の主人がいた。彼はぶどう園を作り、垣根を巡らし、その中に踏み場を掘り、見張りやぐらを立て、それを農夫たちに貸して旅に出た。収穫の時が近づいたので、主人は自分の収穫を受け取ろうとして、農夫たちのところにしもべたちを遣わした。しかし、農夫たちはそのしもべたちを捕らえ、一人を打ち叩き、一人を殺し、一人を石打ちにした。」
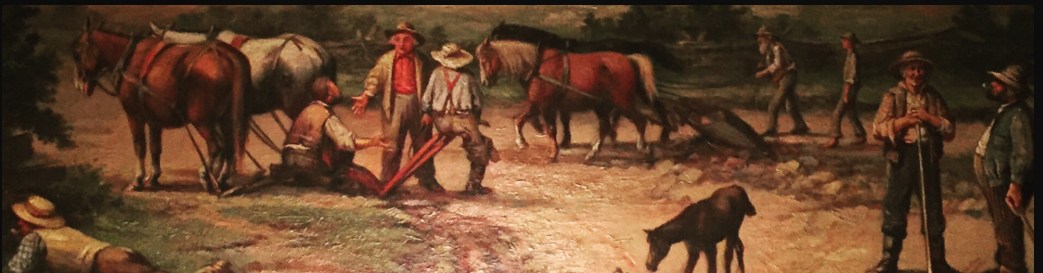
この話も、ぶどう園のたとえ話です。ぶどう園の主人が丁寧にぶどう園を作り、垣根を巡らし、踏み場を掘り、見張りやぐらを立てる様子が描かれています。これは、神様がイスラエルの民を形成していく姿を表していると考えられます。本当に愛情が込められており、一生懸命に作り上げたぶどう園を、農夫たちに管理を任せます。そして、主人は旅に出ました。
しかし、収穫の時が近づいたので、主人は自分の収穫を受け取ろうとして、しもべを遣わします。ところが、農夫たちはそのしもべを捕らえ、一人を打ち、一人を殺し、一人を石打ちにしました。彼らは、本当にひどいことをしているのです。
さらに、主人は前よりも多くの別のしもべたちを再び遣わしました。しかし、農夫たちは同じように扱いました。このことが 36 節に記されています。それで、その後主人はどうしたかというと、37節にこうあります。「その後、主人は『私の息子なら敬ってくれるだろう』と言って、息子を彼らのところに遣わした。」つまり、最後に主人は自分の息子を送り込むのです。「私の息子なら敬ってくれるだろう」という発想のもとで、その息子を送り出しました。
皆さん、これをどう思いますか? ちょっと判断が甘いんじゃないでしょうか。「息子を送れば敬ってくれるだろう」と言っていますが、実際には絶対に敬ってくれない相手ですよね。私はこの判断、甘いんじゃないかなと思います。もし自分の息子がいたとして、絶対にこんなところには送りたくないですね。長野県の松本のような良いところに送り出したいですが、こういう危険な場所には送りたくありません。
この主人の判断は、やはり少し甘いのではないでしょうか。「敬ってくれるだろう」と期待していますが、絶対にそうはなりません。しかし、私たちはそこに、主人の強い期待が込められていることを感じます。「息子を敬ってほしい」ということは、結局は「自分を敬ってほしい」ということなのです。この主人が何を願っているかというと、農夫たちとの関係の回復です。農夫たちとの関係はすでに壊れてしまっていますが、それでも主人は関係を取り戻したいと願っているのです。「息子を送れば、きっと彼らも謝ってくれるだろう」と期待しているのです。
これは、父なる神様の思いが表れていると考えることができるのではないでしょうか。神様もまた、私たちに対して常にそのような思いを持っておられるのだと思います。私たちは神様に背を向け、反発し、反逆して歩んでいます。しかし、それでも神様は私たちとの関係を取り戻したいと願っておられるのです。だからこそ、たった一人の息子を送ってくださいました。イエス様の姿がそこに表されています。そして、そこには神の深い思いが込められているのです。私たちは、その思いをしっかりと受け取る者でありたいと思います。そして、その愛に応えていく者でありたいと願います。
しかし、結果は最悪のものとなります。息子が送られてきましたが、農夫たちはどうしたでしょうか。38節にはこうあります。「すると、農夫たちはその息子を見て、『あれは跡取りだ。さあ、あれを殺して相続財産を手に入れよう』と話し合った。そして、彼を捕らえ、ぶどう園の外に放り出して殺してしまった。」
主人の期待は見事に裏切られました。「息子を送れば、きっと謝ってくれるのではないか」と期待して送り出したのに、その期待は完全に裏切られ、息子はぶどう園から追い出され、殺されてしまいました。まさに最悪の結果です。
そして、最終的にはどうなるのでしょうか。イエス様は最後に問いかけます。「ぶどう園の主人が帰ってきたら、その農夫たちをどうするでしょうか?」 すると、人々は答えます。「悪者どもを情け容赦なく滅ぼし、収穫の時が来れば収穫を納める別の農夫たちに貸すでしょう。」
これは、最初に長老たちが答えた言葉です。彼らもその結末をよく理解していました。誰が考えても明らかなことです。もしぶどう園の主人が帰ってきたら、どうなるか? 当然、主人は激怒し、容赦なく農夫たちを滅ぼすでしょう。そして、もうそんな者たちには任せられないので、ぶどう園を別の農夫たちに託すことになるのです。別の人にも委ねることになるのですね。それは誰にでもわかることです。最初に答えた人たちも、そのことを理解していました。このような展開になっているのがわかります。
ここで私たちが注目したいのは、40節です。「ぶどう園の主人が帰ってきたら、その農夫たちをどうするでしょうか?」という問いかけがあります。この「ぶどう園の主人が帰ってくる」という言葉に、私たちは気づかされます。これは例え話の中の出来事ですが、「主人が帰ってくる時が来るのだな」ということを意識させられるのです。
ここに、イエス・キリストの再臨が示されているのではないでしょうか。イエス様はまだ帰ってきていません。しかし、いずれ帰ってくる時が来ると聖書には約束されています。再臨の時が来るのです。そして、その時に「その農夫たちをどうするでしょうか?」という問いかけが、そのまま「再臨の時に、主人は私たちをどうするでしょうか?」という問いにつながってくるのではないかと思います。
つまり、その時、私たちは問われるのです。今、私たちはぶどう園を委ねられています。この働きを任されているのです。それは、本当に主人の御心にかなった働きになっているでしょうか? 主人が帰ってきた時、私たちの働きが本当に喜ばれるものであるかどうか。最後の時に、それが問われるのです。そのために、今の時を大切にしなければなりません。私たちの働きが、御心にかなったものになっているかどうかを、しっかり考えなければならないのです。
ここで、ぶどう園を委ねられた農夫たちの問題点について考えてみたいと思います。彼らの問題は何だったのでしょうか。それは、彼らがぶどう園を「借りているだけ」だったということです。ぶどう園の所有者は、間違いなく主人です。ぶどう園は主人のものであり、農夫たちはただ借りているにすぎません。しかし、彼らの問題は、このぶどう園をあたかも自分のものであるかのように、私物化してしまったことにあります。
彼らは勘違いしていました。ぶどう園をまるで自分の所有物であるかのように扱っていたのです。そして、主人が遣わしたしもべたちに対して、ひどい仕打ちをしました。さらに、最後に息子が送られてきた時、彼らはこう言いました。「あれは跡取りだ。さあ、あれを殺して、あの相続財産を手に入れよう。」つまり、息子を殺してしまえば、ぶどう園はすべて自分たちのものになると考えたのです。これは、まさに「乗っ取り」です。主人のものを奪おうとしているのです。
私たちも、気をつけなければならないことがあるのではないでしょうか。それは、教会をあたかも自分のものであるかのように、私物化してしまう誘惑です。私たちは教会を本当に大切な場所として考えています。そして、教会は私たちにとって、居心地の良い場所であってほしいと願っています。ここに来て、イエス様と出会い、本当の自分を見出し、行き詰まっていた人生が吹き返し、見失っていた自分を取り戻す――そういう場所であってほしいと思います。
しかし、私たちの気持ちは、そこで満足するだけではなく、さらに膨らんでいくことがあります。願いがどんどん大きくなり、自分の快適な空間に作り替えたいという欲求が生まれてしまうことがあるのです。だんだん教会が、自分の「居場所」としての意味を、本来の良い意味から逸脱してしまうことがあります。つまり、自分が何でもわがままに振る舞え、思い通りになる場所であるかのように、教会を作り替えてしまう――そんな誘惑が、私たちに働いているのではないかと思うのです。
そして、気がつけば、まるで自分が教会の主人になってしまったかのような状態に陥ってしまいます。自分がその領域の主であるかのように振る舞い、イエス様を追い出してしまっているのです。しかし、教会とはキリストの体であり、神の御住まいであり、聖霊の宮である場所です。ここは間違いなく神様のものなのです。神様がご臨在する場所であり、常にその中心にイエス様がいなければなりません。それなのに、イエス様がどこかに追いやられ、代わりに人間が中心に居座ってしまう。そうして、人間中心の教会になってしまう――こうしたことは、いくらでも起こり得るのです。
実際、教会の歴史を学ぶと、そうした例は数え切れないほどあります。そのため、私たちは決してそのような状態にならないよう、本当に気をつけなければならないと思います。
黙示録3章20節には、とても有名な言葉があります。
「見よ、私は戸の外に立ってたたく。」
この言葉は、イエス様が外に立って戸をたたいているという情景を表しています。「誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入り、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする」と続くこの御言葉は、伝道集会などでよく用いられます。まだイエス様を信じていない人に向けて、「イエス様は皆さんの心の扉をたたいています。ぜひ心を開いて、イエス様を受け入れましょう」と促す際に引用されることが多いのです。
しかし、この言葉の本来の意味をよく考えてみると、これは未信者に向けたものではありません。黙示録3章20節のこの言葉は、ラオデキアの教会に対して語られたものなのです。
本来、イエス様は教会の中におられるべき存在です。しかし、この場面では、イエス様が教会の外に立ち、戸をたたいているのです。これは本来あってはならない異常事態です。つまり、イエス様が教会から追い出されてしまっているのです。
さらに、この箇所を丁寧に読んでみると、「暑くもなく、冷たくもない、生ぬるい教会」であると指摘されています。そこにはもはや神様の清さがありません。イエス様が中心ではなくなり、人間の願望が支配するようになった結果、教会が生ぬるくなってしまったのです。これは、神様が教会の外へと追いやられてしまった証拠ではないでしょうか。
そのような非常事態が起きていたのが、ラオデキアの教会だったのです。
私たちは、聖書の御言葉を文脈から切り離し、良い形で活用することがよくあります。しかし、文脈に即して読んでいくと、実際にはまったく異なるメッセージが語られていることもあるのです。よく丁寧に読んでいくと、これはまさに教会に対して語られている警告の言葉だとわかります。そのように見えてくるのではないかと思います。
私たちは、本当に知らず知らずのうちにイエス様を追い出してしまっていないだろうか――。そのことを考えなければなりません。教会はキリストの体であり、キリストが頭であり、また、聖霊がそこに住んでくださる宮であると意識し、そのつもりで教会に来て礼拝をするものです。しかし、よく考えてみると、自分の願望が支配し、人間の思いが中心になっていることがあります。もしそうなってしまったら、それは、まさにここで語られていることと同じ状況なのです。そのことを私たちは深く自覚し、気をつけなければならないと思います。
人間の願望というのは、どんどん膨らんでいくものです。そして、私たちは自分の思い通りに物事を進めたくなるものですが、その思いは必ず私たちの中にあるのです。そのことをよく自覚しながら、絶えず主が教会の中心におられるようにしなければなりません。
やがて、イエス様は帰ってこられます。そのときに、イエス様に評価され、喜んでいただけるような教会を形成していくことが、私たちの目標であるべきです。そのような教会を目指して歩んでいきたいと思います。
このことを、私たちははっきりとメッセージとして受け止め、それを認める者でありたいと思います。
さて、この話の後半に入っていきたいと思います。このたとえ話は、基本的には祭司長や長老たちに気づいてほしい、という意図で語られたものです。しかし、彼らは最後になってようやく気づくのです。今日の箇所の最後で、「ああ、この話は自分たちに対して語られているのだ」と、やっと気づくのです。それまでは気づかなかったということです。そのために語られているたとえ話なのですが、このたとえ話が非常に奥深く、不思議なものであると感じる理由があります。
それは、このたとえ話の中に、これから起こることが示されているという点です。つまり、神様のご計画がこのたとえ話を通して表されているのです。これが、このたとえ話の非常に興味深い点ではないかと思います。
では、この後、何が起こるのでしょうか? それは、父なる神様が私たちのために送ってくださったひとり子が、殺されてしまうということです。この時点では、まだその出来事は起きていません。しかし、イエス様はご自身のことをここでお話しされているのです。
父なる神様は、イスラエルとの関係の回復を願い、イスラエルの人々の救いを願って、ひとり子を遣わしてくださいました。しかし、彼らはどうしたでしょうか? 彼らは、ぶどう園の外にそのひとり子を追い出し、そこで殺してしまうのです。つまり、イエス様がここで語られた通りのことが、これから実際に起こるのです。
このたとえ話には、ある意味で予言の要素があります。そして、そうした悲しい結果を迎えることになりますが、イエス様はここで詩篇の御言葉を引用し、それもまた神様のご計画の一部であったことを語られています。
42節には、詩篇118編の御言葉が引用されています。
イエスは彼らに言われました。
「あなたがたは、聖書に次のように書かれているのを読んだことがないのですか。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。」
ここで引用されているのは、詩篇118編22節と23節の御言葉です。「家を建てる者たちが捨てた石」とは何を指しているのでしょうか?「いらない」と捨てられた石があります。それが、実はイエス様なのです。
その捨てられた石が、要の石となる。つまり、その石を中心に、新しい建物が建てられていくということが、ここで予言されているのです。
「これは主がなさったこと。私たちの目には不思議なことだ。」
これは、とても理解しがたいような展開ですが、不思議でありながらも、やはり神様の素晴らしさが表れているのです。
そして、43節にはこうあります。
「ですから、私は言っておきます。神の国はあなたがたから取り去られ、それにふさわしい、実を結ぶ民に与えられます。」
イスラエルのために、神様は本当に心を尽くし、ぶどう園を作り、イエス様を送ってくださいました。しかし、彼らは実を結ばない「いちじく」でした。葉っぱだけが生い茂っているのに、実が結ばれていない。命がなく、中身のない信仰を持つ者たちは、滅ぼされてしまうのです。
そのため、神の国は彼らから取り去られ、実を結ぶ新しい民に与えられます。ここで、新しい教会が形成されていくという、神様のご計画が表されていることがわかります。
そして、44節にはこうあります。
「この石の上に落ちる者は粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちれば、その人を押しつぶします。」
ここでは、「石の上に落ちる者は粉々に砕かれる」「石が人の上に落ちると、その人を押しつぶす」と、両方の表現が出てきます。どちらにしても、非常に恐ろしい、考えるだけでゾッとする描写です。
これは、神の裁きの厳しさを表しているのだと思います。
このように、神様のご計画はこれから進展していきます。
確かに、イエス様は十字架につけられ、惨めな最後を遂げられます。しかし、それこそが「要の石」となり、そこから新しい神の御業が始まるのです。
そして、教会が建てられていき、やがて最後には、神の裁きが行われます。このように、神様のご計画の全体像が示されており、その中に私たちも生かされているのです。そのことを、最後に心に留めたいと思います。
さて、最後の場面に目を向けると、ついに彼らは気づきます。
「祭司長たちとパリサイ人たちは、イエスのこれらのたとえを聞いたとき、自分たちに向けて語られたことだと気づいた。」
やっと気づいたのです。イエス様は、ここに至るまで彼らが気づかなかったことを、むしろ不思議に思われたことでしょう。そこには、彼らの霊的な鈍さが表れているのだと思います。
「気づいてよかった」と思います。しかし、その気づきが、悔い改めへとつながればよかったのですが、残念ながら、そうはなりませんでした。
45節には、こうあります。
「それで彼らは、イエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れた。群衆はイエスを預言者と認めていたからである。」
つまり、彼らは悔い改めようとはせず、ますます怒りを募らせ、イエスを捕らえようとしました。しかし、この時は、まだ行動には移しませんでした。なぜかというと、「群衆が怖かった」からです。
彼らは、人々の目を恐れていたのです。だからこそ、この時点ではブレーキがかかりました。
しかし、自らブレーキをかけたわけではありません。環境がブレーキをかけただけなのです。
そして、このブレーキが取り去られる時が、もうすぐやってきます。その時、彼らは暴走し、ついにイエス様を十字架にかけてしまうのです。そして、イエス様は十字架にこうつけられていくという展開になるんですけども、人間の心がいかに硬くなり得るかっていうね。本当に神に閉ざされた心というのは、ここまで頑なになるのかと。これだけ丁寧に、親切に、間接的に、丁寧に本当に問いかけて、「気づいてほしい」「理解してほしい」「戻ってきてほしい」と粘り強く、一生懸命、一生懸命話しているのに、でも全然伝わらない。その結果、ますます激しく怒っていくという人間の心の頑なさが、ここに示されているんだと思います。
私たちもそうならないように気をつけたいなと思いますね。知らず知らずのうちに、私たちの自己中心がどんどん膨らんでいって、そして頑なな心になっていかないように。私たちは本当に砕かれていかなきゃいけないしね。御言葉によって、本当に清められていかないといけない。そのようにして、私たちが日々成長するものとして、霊的な成長を遂げていくものでありたい。そのように、ぜひ御言葉と御霊によって導いていただきたい。そのように祈るものでありたいなと思います。
今日の学びを終えてね、ぜひ教会が本当に神の宮として、キリストの体として、神の住まいとして。教会はいろんな言葉で表されますけども、やっぱり神が住んでいる場所なんですよね。ここに神がおられないといけないんです。イエス様がここにおられないと教会じゃないんです。それがいつの間にか教会じゃなくなってしまうという戦いが、いつもあるんですね。
そういう戦いをいつも意識しながら、主が真ん中におられるように。そのような教会形成を目指していきたいと思うし、私たちの思いがそれを阻んでしまうことがないように。私たちもぜひ注意しながら、御霊によって整えていただくものでありたいと思います。
お祈りをして終わりたいと思います。
愛する神様。聖書を通して私たちの姿を示してください。また、あなたの御愛の深さを教えてください。そして、その中で私たちを何とかして主のもとへ導こうとしてくださっているあなたの愛の深さを覚えることができることを感謝します。
どうぞ、その主の御前で私たちがいつも応えて歩んでいくことができますように。知らず知らずのうちに私たちの願いや願望が広がり膨らんでいき、それによってあなたを追い出したり、自分中心になってしまうことがありませんように。どうぞ私たちの心を守り、教会を守ってください。そして、この教会が本当に神宮として祈りの家としてこれからも豊かに祝福されていきますよう助けてください。
御言葉による導きに心から感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。