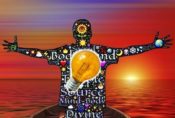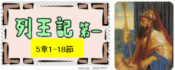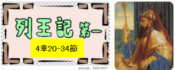マタイの福音書22章34~46節

そして彼らのうちの一人、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。
「先生、律法の中でどの戒めが一番重要ですか。」
イエスは彼に言われた。「『あなたは心を尽くし、いのちを尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。』
これが、重要な第一の戒めです。
『あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい』という第二の戒めも、それと同じように重要です。
この二つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのです。」
パリサイ人たちが集まっていたとき、イエスは彼らにお尋ねになった。
「あなたがたはキリストについてどう思いますか。彼はだれの子ですか。」彼らはイエスに言った。「ダビデの子です。」
イエスは彼らに言われた。「それでは、どうしてダビデは御霊によってキリストを主と呼び、
『主は、私の主に言われた。
「あなたは、わたしの右の座に着いていなさい。
わたしがあなたの敵を
あなたの足台とするまで」』
と言っているのですか。
ダビデがキリストを主と呼んでいるのなら、どうしてキリストがダビデの子なのでしょう。」
するとだれ一人、一言もイエスに答えられなかった。その日から、もうだれも、あえてイエスに質問しようとはしなかった。
( マタイの福音書 22:34-46 JDB )
パリサイ人たちは、イエスが、サドカイ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まったとこういう言葉から今日は始まります イエス様がサドカイ人たちを黙らせたんですねで前回の内容ですけども サドカイ人たちが イエス様のところにやってきて難しい質問をしてきました でもそれに対して イエス様 見事に素晴らしい お答えをされましたね それでもう彼らは黙るしかなかったという そういう結論ですね。サドカイ人たちがここに出てくるんですけど、その前にはパリサイ人たち もやってきましてね それで イエス様に対して難しい 問いかけをしてきますが その時にもイエス様は見事にお答えになりまして その結果として 22節 彼らはこれを聞いて驚嘆したっていういう結論でしたよね ですから今まで パリサイ人が来たり、ヘロデ党の人たちも一緒に来たり サドカイ人たちが来たりいろんな人たちが次から次に押しかけてきて まあ 狙ってることはイエス様を何とかして 言葉の罠にかけよう そして イエス様を訴える口実を見つけようという そういう 魂胆で悪い思い 悪い 動機でやってくるわけですよね それで、あからさまに捕まえることはできませんでした 群衆たちがみんな イエス様のことを預言者として認めていましたし イエス様のお話を聞くことをみんな喜んでましたのでもうあからさまにとらえることできないので何とか言葉尻を捉えて罠にかけようという そういう魂胆で来るわけですが まあ一つ一つ イエスは見事にお答えになるわけですね それで驚嘆したり 黙ってしまったりということで とても見事な対応だったな ということを今まで学んできたところかな と思います。
これで懲りたのかな と思ったら どうもそうでもないんだな というのが 今日のところでして パリサイ人たちはイエスがサドカ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まった そして彼らのうちの1人 律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねたということなんですね 次に質問が出てくるんですけども その質問はまあ一見もっともらしい質問なんですが でもそこには です ね やっぱり試そうとしているっていうのが、 悪い 動機が そこに潜んでいるということなのかなと思います。
36節です 「先生 律法の中でどの戒めが一番重要ですか 」ということで律法の中でたくさんの 戒めがありますがどの戒めが一番重要ですか という問いかけでした それで 律法の中にはたくさんのことが教えられてるんですけれども 実はユダヤ人たち パリサイ人はそれにさらに 律法に基づいて さらにいろんな 戒めをつけたして作っていたということが言われていまして 一説によると その時 613の戒めを作っていたという説もあります 守るべき言葉も、してはいけないこと いろんなルールですね 色んな 掟を自分たちで作るんですね それで 神の教えを人間の教えにしてしまっているとイエス 様から 指摘されているような箇所もあるんですけれども 本来律法で教えられていることが人間の教えにこうすり替わっていく っていう、そういう問題を抱えていたわけですが いずれにせよ いろんな教えがある中でね どれが一番大事で、どれほど 優先すべきかということが彼らの中の一つの議論になっていたということが言われていること なんですね。でおそらく彼らはイエス様をその議論の中に巻き込むと言うんでしょうかねまあそういうことを狙っていたんじゃないかということが指摘されていることであります それであの律法の専門家がその前に、 パリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らせたと聞いて、「一緒に集まった」ってこう出てくるんですね この「一緒」っていうのは誰と一緒だったか自然に理解するならばおそらく パリサイ人とサドカイ人たちが一緒になってやってきたっていう意味だろうなと思います。自然に取ればね 全然立場が違って、考え方が違っていて普段は全然仲の良くない 両者なんですが 一緒になってやってきたっていうところにやっぱり なにか魂胆があって ですね イエス様が何か言った時にどっちかが批判できるような 状況を備えていたということも考えられる その前に あの パリサイ人がヘロデ党の人たちを連れてきたっていうのも そういうことがあったんですけれども まあとにかくですね イエス様の言葉尻を捉えてですね なんか 訴える きっかけをつかみたいというですね 。そういう下心って言うんでしょうかね、魂胆があったんだろうなということが考えられるんですね でも悪い 動機でかれらは 近づいてきてるんですが結果的にはイエス様は一番大事なことを教えたんですね 彼らは悪い動機でイエス様のところにやってくるんですけども まあ 結果を見れば ですね 聖書で一番大事なこと が教えられてるんです
ここで最も大事なことを、ある意味では「引き出した」って言うんでしょうかね。まあ、パリサイ人たちは引き出すつもりはなかったと思うんですけれども、とても大事なことをイエス様がここでお教えになられた。これもまた、見事な対応だったということになるんじゃないかなと思いますね。
それで、イエス様の答えなんですが、37節。
「イエスは彼に言われた。『あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神を愛しなさい。』これが重要な第一の戒めです。」
ということで、「あなたの神を愛しなさい」、これが一番大事な戒めですよっていうことですね。そのことを、ここでお伝えしております。
これは、これまでユダヤ人たちはよく分かっていることでした。とても大事にされている戒めで、申命記6章5節の御言葉の引用なんですけれども、ユダヤ人がとても大事にしてきた御言葉でした。
それで、それはですね、本当に、ユダヤ教の礼拝の中では必ず朗読される御言葉だったそうですし、子どもたちに最初に暗記させなければならない御言葉として、大切にされてきた御言葉です。とても重んじられてきた、そういう教えだった。
それは、ユダヤ人の人たち、パリサイ人たちが聞いても、よく分かる、納得できるお答えだったのかなと思います。
でも、彼らが抱えている問題は、神を愛すると意識は持っていながら、隣人を愛することができないという、そういう課題を抱えていたんですね。神を大事にするということを強調するあまり、その一方で、異邦人とか、あるいは罪人と呼ばれている人たちとか、サマリア人とか、取税人とか、そういう人たちはひたすら見下していた。隣人を全然顧みない、というね。そういう課題を抱えていたんです。
サマリア人と一緒に食事なんかしちゃいけなかったんですね。ですから、イエス様がサマリア人とお話ししているのを見て、みんなびっくりしたっていう記事があるんですけれども、まあ、そういう状況なんですね。
ですから、神を愛しているつもりだったのかもしれませんけれども、実はそれは本当の意味で神を愛しているということにはなっていない。神を愛すると言いながら、実は人を憎んでいる。そういう問題を、彼らは抱えていた。
それで、イエス様は続けて、もう一つの教えを教えられました。39節。
「あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい」という第二の戒めも、それと同じように重要です。
ということなんですね。神様を愛することをユダヤ人たちはとても大事にしていたんですが、それと同じように第二の戒めも重要なんですよ。
そして、この二つの戒めがどれだけ大事な教えであるかということを強調するために、最後、40節でこう言われます。
「この二つの戒めに、律法と預言者の全体がかかっているのです。」
これ、分かりやすい言い方をするとですね、「旧約聖書の全体は、この二つの言葉で要約されます」というような意味かなと思いますね。
もう旧約聖書って、膨大な量で理解するのもとても大変ですよね。たくさんのことが教えられているんですが、でもこの二つの戒めが分かれば、もう旧約聖書も理解したのと同じですよ、という——ちょっと極端な言い方ですけれどもね——それくらい大事な、大事な教えなんですよ、ということを、ここでイエス様に教えられたと思います。
ですから、パリサイ人たちは悪い思いでこう近づいてきているんですけれども、でも結果的には一番大事なことを教えられている。
そしてユダヤ人たちが当時抱えていた、その問題も指摘しながら、「神を愛する愛」と「隣人を愛する愛」というのは両方大事なんだと。そして、その両方を大事にできてこそ、神を愛することだし、人を愛することなんだという、そういうことを教えられたということだと思います。
私たちにとっても、これはとっても大事な戒めで、旧約聖書全体はこの二つの御言葉にかかっているって言うんでしょうかね、そういうことになるんですけれども、私たちのことを考えると、
神を愛する愛を大事にするけど、ちょっと人を愛することは軽んじてしまうとか。あるいは、人を愛する愛はとっても大事にするんだけど、よく考えてみると神を愛していないとか。どっちかに偏りやすい傾向というものが、私たちの中にもしかしたらあるんではないかなと思いますね。
で、教会に来て一生懸命、「神様を愛する! 一生懸命努力して愛します!」っていうふうに告白しながら、家に帰ると家族に意地悪をしていたりとかですね。いろんな人間関係の問題を抱えて、心の中では憎しみいっぱいで、でも「神様は愛します」と口では言ってるのに、人間関係においてはいろんな課題を抱えているという、そういう一つの傾向があるかなと思います。
その逆に、人間への愛はとっても大事にしていて、とっても優しい人もいるんですね。本当に一人ひとりに関わるんですけれども、でも神に対する愛が十分ではないために、やっぱりその愛が、どこか自己中心的な愛になってしまっているという、偏りやすい傾向を私たち、持ってるんじゃないかなと思うんですね。
ですから、この二つがとっても大事だということと合わせて、この「順番」が大事なんだと思うんですよね。
まず、神を愛するという愛があるからこそ、それが人に対する愛に広げられていくという。そういう「順番」も大事なんだと思います。
ですから私たちは、本当にここで教えられているようにですね、まずは
「あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神を愛しなさい」
って、教えられていますよね。
「心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし」、これはもう本当にですね、私たちの思いも、あるいは私たちの生き方も、感情も動機も、もうすべての領域において、全生涯において、本当に心から神様に仕えなさい、愛しなさいっていう意味だと思いますけれども。
その愛があってこそ、やっぱり人にこう広げられていくという、そういう順番になっていく。そのことも覚えてですね、まあ、今年、新年度、私たち始まります。あの、最初にね、これ確認しておく、とても大事なことかなと思います。
これからいろいろ、私たち新年度、いろんな奉仕をしたり、いろんな働きに関わっていったり、それは何のための奉仕なんだろう、何のための礼拝なんだろう、何のための献金なんだろう。いろいろな活動をこれから始めていきます。新年度でね、いろいろ役割分担もして、「今年はこの奉仕で行こう」とか、いろいろそういう、皆さんいろんな思いがあると思いますけれども。
でもやっぱり、それは全部ですね、神様に対する心からの愛の表れであるということですよね。それが形になって現れるのが、奉仕だし、礼拝だし、献金だし。そして、それが本当に表されてくるからこそ、その愛が交わりの中に広げられていく、っていうね、そういう順番になっているんだと思います。
ですから、今年1年始めるに際してですね、もう一度、私たち「何のために神様を信じているのか」、「何のために礼拝に来ているのか」、「何のために献金しているのか」、その動機ですよね。私たちの心の一番深いところに何があるか、神に対する愛があるか、人に対する愛があるか、ということですね。
そのことを、イエス様はとても大事なこととして、ここで教えてくださっている。それを私たちも、自分自身のこととして受け止めて、新年度を始めていきたいなと思います。
けれども、次の箇所はですね、このイエス様がパリサイ人に向かって質問を投げかける場面なんですね。
で、今まではどちらかというと防戦一方というか、もうひたすらイエス様が問われる側だったんですね。パリサイ人たちも、なんとかしてイエス様を言葉の罠にかけようと、いろんな策略を巡らしてきていて、それをすべて、イエス様は見事にお答えになっていくんですけど。
最後はですね、イエス様の方から質問を投げかけたというのが、最後の場面かなと思います。
41節「パリサイ人たちが集まっていた時、イエスは彼らにお尋ねになった。『あなた方はキリストについてどう思いますか? 彼は誰の子ですか?』」という問いかけをしたんですね。
これも、とても本質的な、とっても大事な質問を投げかけているということがわかります。「あなた方はキリストについてどう思いますか?」って。これはイエス様が今、お話ししてますが、「イエス様のことをどう思いますか?」っていう意味じゃないんですよね。
まあ、「キリスト」は「救い主」って意味ですけども、「救い主ということについて、あなたはどういう理解を持っていますか? キリストについてどういうふうに理解していますか?」という、まあ、そういう意味の問いかけだと思います。
それに対して、「彼らはイエスに言った。『ダビデの子です。』」キリスト、つまり救い主はダビデの子孫として生まれるということは、旧約聖書で預言されていることですし、みんなが知っていることでした。ユダヤ人の人たちみんなで共有されている理解でした。
ですから、イエス様が来た時にですね、たとえば今までの箇所でも、たとえばマタイの福音書20章31節を見ると、2人の目の見えない盲人がいましたね。イエス様が通ってきた時に、彼らは声を上げるんですね。
「主よ、ダビデの子よ。私たちを憐れんでください。」
それは「救い主」という意味なんですね。エルサレムに入城した21章の15節では、子供たちが「ダビデの子にホサナ」って賛美してるんですね。で、子供たちもそういう理解を持ってるわけですね。イエス様が来た時に、「ダビデの子が来た! ホサナ!」って賛美したんですね。
ですから、子供たちでも理解している、教育されている、広くユダヤ人たちに理解されている方なんだということですね。ですから、彼らもそう答えているわけですね。イエス様の問いかけに対して「ダビデの子です」と。
キリストはダビデの子だというのは、みんなに共有されているその理解でした。それでよかったんだと思うんですけれども、イエス様は彼らに続けて言われました。
「それでは、どうしてダビデは御霊によってキリストを『主』と呼び、『主は私の主に言われた。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまで』と言っているのですか?」
ということでもう一つ問いかけをしてきてですね。ここでイエス様は、ダビデの詩篇110編1節の御言葉を引用してきまして。
まあ、彼らは律法学者の専門家ですから、よく知っているあの御言葉を引用してですね、ダビデの子としてキリストは認識されているわけですけれども、そのダビデがですね、どうして「主」と呼んでいるのか、と聞いています。
ダビデの子と呼んでいるのなら、どうしてキリストはダビデの「主」なのか?という、そういう問いかけをしたんですね。
詩篇110篇では「主は、私の主に言われた」という言葉が出てきます。この最初の「主」は神様、父なる神様のことを表していると考えられる――
そして、父なる神様である「主」は「私の主に言われた」。後の「主」は、キリストを表していると考えられます。父なる神様とキリストとの間に、このような会話があるということですね。
つまり、キリストのことをダビデが「私の主」と呼んでいるということなんです。自分の「主」と呼んでいるのであれば、どうしてキリストはダビデの子供なのですか、という問いかけです。
皆さん、答えられますか? 彼らも答えられなかったんですね。
「すると誰一人、一言も答えられなかった。その日から、もう誰もあえてイエス様に質問しようとはしなかった」ということで、誰も答えることのできない質問をイエス様はここで投げかけたのです。
ちょっと人間の常識ではわからないことなんですね。キリスト、救い主はダビデの子として生まれると、みんな信じていました。そしてそれは、人間になるということ。人の子になるという意味なんですね。
ですから、イエス様がお生まれになった時には、「ダビデの子が来た」と、つまり人の子として来てくださったと、みんなでお祝いして喜んだわけです。それは正しい理解なんです。
でも、それだけではないんですね。
実は、人の子としてお生まれになったんですけれども、それと同時にこの方は「神の子」としても来られたんです。人の子であり、神の子でもある。ですから、ダビデにとっての「主なる方」なんですよ、ということですね。
ちょっと私たちの知性や理性では理解できないようなことを、イエス様はここでおっしゃっているんです。
でも、イエス様ってそういう方ですよね。イエス・キリストって、私たちが信じているお方はそういう方です。
人の子になられました。完全に私たちと同じ人間になられました。だからこそ、私たちの罪の身代わりになってくださいました。
でも、それだけだったら救い主にはなれないんですね。この方は人の子であり、同時に神の子なんです。神の子なんですよね。
ですから、私たちの「主」になるわけです。
その救い主であるからこそ、人の子であり、神の子であるからこそ、贖いを成し遂げ、私たちの身代わりとなって、そして救いを成し遂げてくださいました。
それは、イエス様が完全に「人の子」であり、「神の子」であったからこそ成り立つ、そういう御業だったということ。それを私たちは信じているんですね。
ところが、普通に理性で考えると、とても信じられないことなんです。これは私たち人間の頭では理解できないことを、私たちは信じているんですね。
だからこそ「信仰」と言うのだと思います。
そのようなお方として、キリストというのは、そういうお方なんだよ、ということ。それはとても大事なこととして、イエス様が示してくださっている、大切な教えだと思います。
実はこのことがですね、ちゃんと教えられていたにもかかわらず、教会の歴史を見てみると、「イエス・キリストが人の子であり神の子である」ということが、教会の心からの告白になるまでに、何百年も時間がかかっているんですね。
もう、何回も何回も教会会議を開いて、「キリストは神なんだ」「いや、人なんだ」「いや、どっちもだ」と議論が繰り返され、なかなか収まらなかった。そして本当に、「イエス・キリストは神の子であり人の子なんだ。両方なんだ」ということが、教会の心からの告白になるまでに、何百年という時がかかるという、そういう教会の歴史があるんですよね。
それだけ、人間の頭では理解できない、そういう内容なんだと思うんです。でも、聖書には間違いなく、そのように示されている。
私たちはそのことを、信仰をもって受け止める時に、そこに救いの道が開かれていく、ということなんですね。
二つの記事を、今日学んできました。この二つの記事に共通していることがあるな、ということを思いました。
それはですね――神様というお方、イエス・キリストというお方は、私たち人間の「理解」というものをまず確認した上で、私たちの中である程度理解されている内容を踏まえた上で、でも、それを遥かに超えるお方なんだよ、ということを示される方なんだ、ということです。
最初の記事では、ユダヤ人たちは「神を愛する」ということは、常識として知っていたわけです。本当に神を愛していたかどうかはちょっと疑わしいかもしれませんが、「神を愛さなくてはいけないんだ」ということ自体は、しっかり守っていた。そのために、いろんな戒めを作っていたんですね。
でもその結果、人を愛すること、隣人を愛すること、その「愛」が軽んじられているという矛盾に陥っていた。ですから、半分はちゃんと理解しているんです。ある程度、「愛さなければならない」ということは理解されていた。
でもその理解を、もっと遥かに超えたところに、神様の真理があるんだよ、ということを、イエス様がここで示してくださっている――これがひとつ言えることだと思います。
そしてもうひとつは、その時のユダヤ人たちは、「キリストはダビデの子である」という意識を持っていたということ。
これも、とても良い、正しい理解なんですよね。とっても大事なんです。でも、その理解にもう縛られるあまりですね、イエス・キリストが来た時に、地上のメシアとして期待する人があまりにも多かった。
地上の王様のようになってくださって、それでローマ帝国の支配から解放してくださる、そういう偉大な支配者としてイエス様に期待する人がたくさんいたんですよね。それは、自分たちが「キリストというのはダビデの子なんだ」という、その発想にとらわれているために、そこから出ることができず、その範囲の中でしか理解できないという、そういう限界を持っていたと思うんです。
でも、イエス様は「キリスト」ということは、そういう理解も大事なんだけれども、それをはるかに超えた方なんですよ。私たちの理解をはるかに超えた、そういう豊かなご性質を持っている偉大な方なんですよ、ということですね。
そのことを教えてくださっている、そういう記事じゃないかなというふうに思います。
今日の記事を通して、私たちに一つ教えられていることは、「納得してしまうことの危険」なのかなということを思いました。私たちの中にはやっぱり、「分かりたい」「理解したい」「納得したい」という思いがあるんですね。
それで、聖書が示された時に、「ああ、そうだ。この通りだ」と納得してしまうとですね、その納得したところから、だんだん離れられなくなるというんでしょうか。そこに、さらに新しい真理が示されても、だんだん受け付けなくなってしまうというんでしょうか。さらに、それを超えた真理が示されても、それを受け入れられなくなってしまう。
そういう傾向を、私たちは抱えていることがあるんじゃないかなと思うんですね。
そして、「もう自分は分かった」「もう納得したので、これが全てです」と、自分の知識を絶対化してしまって、ちょっと教えられづらい。新たな神様の真理が示されても、あんまりそれを受け付けようとしないような、そういう偏った聖書理解になってしまうということも、私たちは気をつけなくちゃいけないことかな、と思うんですね。
納得したいという思いが私たちの中にあって、真理とか神様とかイエス様とか、全部理解したいという思いがあるんですね。でも、私たちはよく覚えておかなくちゃいけないことですが、神様は私たちの頭の中に収まるような方ではないんですね。
聖書の真理も、私たちの頭の中に収まるような真理ではない。もっともっと素晴らしいものですよね。私たちの思い、常識、理解をはるかに超えた豊かな真理が聖書の中にはある。
そのことに、本当に謙虚な思いで心を開いていかないとですね、自分の理解だけが完全になってしまって、「あまり聖書の学びはしなくてもいいかな」とか、「もう十分分かってますから大丈夫です」とか、そういう反応になってしまうことがあります。
聖書の学びを、だんだんおろそかにするような態度になっていくとするならば、それはちょっと気をつけなくちゃいけない傾向かな、というふうに思います。
私たちは一生、聖書から教えられていかなければいけないと思います。もう、それだけの豊かな内容だと思います。聖書というのは、本当に私たちの思いをはるかに超えた素晴らしい方なんですね。
その、いつでも教えてもらえるような、謙虚な、柔らかな心って言ったらいいでしょうかね。そのような心で、私たちはいつも教えられ続ける必要があるかなと思うんですね。
そのようにして、私たちも聖書から、イエス様から、教えられ続けるものでありたい。そのようにして、成長していくものでありたいな、ということを思います。
ということで、22章終わりましたので、今日はここまでとして、お祈りをして終わりたいと思います。
お祈り
神様、イエス様が難しい問いかけをされても、そこで見事にお答えになって、本当に福音の一番大事なところを示してくださいました。
なかなか、私たちにはそのような対応ができません。けれども、御霊がともにいてくださって、その時、どう答えたらいいか、どう話したら良いか、神様、知恵を与えてください。話すべきことも、主が示してくださると聖書で教えられています。
どうぞ私たちが、あなたの導きの中でふさわしく対応していくことができるように。そして、自分で納得しすぎないで、本当に絶えず主が教えてくださるその思い、そのことを心を開いて、学び続けることができるように導いてくださるようにお願いいたします。
そして、本当にあなたを愛し、隣人を愛し、今年も心を尽くしてあなたを愛することができるように、励ましてくださるようにお願いいたします。
御言葉による導きに感謝し、イエス様の御名によってお祈りをいたします。
アーメン。