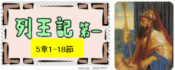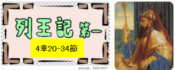マタイの福音書25章1~13節

まとめ
皆さん、今日ご一緒に味わってきた聖書箇所は、終わりの日に備えるようにというイエス様のたとえ話、「十人のおとめのたとえ」です。私たちの信仰生活においても、このたとえは非常に大切なメッセージを含んでいます。
油を用意していた五人の賢い娘と、用意していなかった五人の愚かな娘。その違いが、最後には大きな結果をもたらしました。門が閉じられた後、愚かな娘たちが「開けてください」と叫んでも、花婿である主人から「あなたがたを知らない」と言われてしまった。これほど悲しいことはありません。
イエス様はこのたとえを通して、私たちに警告しておられます。「目を覚ましていなさい。その日、その時がいつなのか、あなたがたは知らないのだから」と。だからこそ、私たちは賢い娘のように、日々油を備えておくことが求められているのです。
では、その“油”とは何でしょうか。いろいろな解釈がありますが、多くの場合、油は聖霊を象徴していると考えられます。また、イエス様との個人的な関係、あるいは神様との親しい交わり、そういったものを指しているとも言えるでしょう。
つまり、私たちが「油を備える」とは、日々イエス様に繋がり、御言葉に生かされ、御霊の力を受けながら、神様との親しい交わりの中にとどまることだと理解することができます。そうして私たちは、暗闇の中でも信仰の灯火を燃やし続けることができるのです。
このことを裏付けるように、第一ヨハネの手紙2章26節、27節には、次のように書かれています。
「私は、あなたがたを惑わす者たちについて、以上のことを書いてきました。しかし、あなたがたのうちには、御子から受けた注ぎの油がとどまっているので、誰かに教えてもらう必要はありません。その注ぎの油がすべてについて、あなたがたに教えてくれます。それは真理であって、偽りではありませんから、あなたがたは教えられたとおり、御子のうちにとどまりなさい。」
この箇所では、終わりの時代において「反キリスト」が現れること、そして人々を惑わす存在が出てくることが警告されています。そのような混乱の中にあっても、私たちは「注がれた油」、すなわち聖霊の導きと御言葉によって真理を識別し、キリストにとどまることができるのです。
私たちは皆、信仰が弱くなったり、つまずいたりすることがあります。ときには眠ってしまうこともあるかもしれません。しかし、花婿なるイエス様が来られるその時に、しっかりと信仰の火を灯していられるように、日々備えていきたいと思います。
いつも私たちは、御言葉により頼みながら、その御言葉を通して働かれる御霊の導きの中で、本当に信仰の火を燃やし続け、灯し続ける。そのような歩みを、日々続けていくものでありたいと思います。
筆耕
裁きの時がやってくるということが、イエス様から示された上で、「じゃあ、どのような備えをしてその日を待ったらいいでしょうか?」ということが、前回学んだことでした。
「時が近づいていますよ。そんなことをよく知りなさい。御言葉に対する信頼を深めなさい。目を覚ましていなさい。用心していなさい。そして、与えられた務めに忠実でありなさい」ということですね。
そういうことが、前回教えられていたことかな、と思います。
そして今日の話もまた、マタイ25章の内容もその続きである、ということが言えると思います。
25章では、イエス様は3つのたとえ話をしてくださいました。最初のたとえ話は、今日の「10人の娘」の話。その後、「タラントのたとえ」の話ですね。そしてその後に、「弱い最も小さい者たちの一人にしたことは、私にしたのです」という話、つまり「小さな者にしたかどうか」というような内容の話が出てきます。全部で3つのたとえ話が出てくると思います。
今日は最初の「10人の娘」の話に注目していきたいと思います。
「そこで、天のみ国は、それぞれ灯火を持って花婿を迎えに出る10人の娘に例えることができます」とありますので、これは天のみ国のたとえである、ということが分かります。
今までも何度も、天のみ国の姿について教えてこられました。そしてそれは、「それぞれ灯火を持って花婿を迎えに出る10人の娘」に例えられるとあります。
結婚式、婚礼の話が出てきますけれども、このたとえ話は、当時のユダヤ社会で行われていた結婚のしきたりが意識された上で語られていると考えられます。
当時、ユダヤ社会では結婚式の祝宴は夜に開かれることが多かったと言われています。そして、花婿の家で祝宴が開かれることが多いのですが、花婿はまず花嫁の家に行って、花嫁を迎えに行くという習慣がありました。そして花嫁を迎えに行って戻ってきて、そこで花婿の家で祝宴が開かれるという、そういう習慣が多かったようです。
このことが、背景として意識されているのだと思います。
「花婿を迎えに出る」ということですので、花婿は今出かけていて、戻ってくるのを待っているわけですね。
2節を見ると、「そのうちの5人は愚かで、5人は賢かった」とあります。
ここで「愚か」「賢い」という言葉が出てきますが、どういう意味で愚かだったのか、どういう意味で賢かったのかというと、3節、4節を見ると分かると思います。
「愚かな娘たちは灯火は持っていたが、油を持ってきていなかった。賢い娘たちは、自分の灯火と一緒に、入れ物に油を入れて持っていた」とあります。
両方とも灯火は持っていたんですね。夜ですから、花婿が帰ってきた時に、ちゃんと照らすための灯火は用意していたのです。
ところが、愚かな娘たちは油を持ってきていなかった。一方、賢い娘たちは灯火と一緒に、入れ物に油を入れて持っていた。つまり、この賢さというのは、「油を用意していたかどうか」、すなわち備えができていたかどうか、ということになると思います。
その後の展開ですが、5節には「花婿が来るのが遅くなったので、娘たちは皆、眠くなり、寝入ってしまった」とあります。
もっと早く来ると期待していたのかもしれませんが、花婿が帰ってくるのが遅くなってしまった。夜もだんだん遅くなっていきますので、皆眠くなってしまい、10人全員が寝てしまった、ということです。
すると、6節です。「ところが、夜中になって、『さあ、花婿だ。迎えに出なさい』と叫ぶ声がした」とあります。
夜中と書いてありますから、本当に遅かったのだと思います。暗闇の中で、叫ぶ声がして、「さあ、花婿だ。迎えに出なさい」という呼びかけの声がした、ということですね。
バッハの有名なコラール『目覚めよと呼ぶ声あり』という曲がありますが、このたとえ話から取られたものだと言われています。あれは「目覚めよ、花婿が来た」という呼びかけの声ですね。バッハはそこからインスピレーションを得て曲を作っています。
さて、声が聞こえたということで、「さあ、それでは迎えに行こう」となったわけですが、7節には、「そこで娘たちは起き直して、自分の灯火を整えた」とあります。
愚かな娘たちは賢い娘たちに言いました。「私たちの灯火が消えそうなので、あなた方の油を分けてください」と。
おそらく、ずっと灯火を灯し続けていたのでしょうが、帰ってくるのが遅くなったこともあり、油がだんだん尽きてきたのだと思います。
油を用意していなかった愚かな娘たちは、灯火が今まさに消えそうになっているという状態だったわけですね。
それで、「私たちの灯火が消えそうなので、あなた方の油を分けてください」と、油を用意していた賢い娘たちにお願いしに行くのです。
ところが、9節……いや、しかし賢い娘たちは答えました。
「いいえ、分けてあげるにはとても足りません。」
「それより、店に行って自分の分を買ってきてください」ということで、もう分けてあげる油も十分にはなかった、ということですね。結局、もらうことはできなかったのです。油を分けてもらうことができませんでした。
それで仕方がなく、直接その場を離れて娘たちは買いに行きました。その間に花婿が来たのです。用意ができていた娘たちは、彼と一緒に婚礼の祝宴に入り、戸が閉じられたということです。
つまり、油を買いに出かけていた間に、花婿が戻ってきたわけですね。それで、5人の娘たちは花婿と一緒に祝宴の席に入りました。すると、その後で戸が閉じられてしまったのです。
それから、どこかで油を買ってきたのでしょうが、娘たちが戻ってきた時には、すでに戸が閉じられており、入れなくなってしまったわけです。そして彼女たちは、「ご主人様、ご主人様、開けてください」とお願いしました。
すると主人は、「まことに、あなたがたに言います。私はあなたがたを知りません」と答えました。
結論として、13節でイエス様はこうおっしゃっています。「ですから、目を覚ましていなさい。その日、その時を、あなたがたは知らないのですから」。
つまり、目を覚ましていることがいかに大事であるかということを、このたとえ話は教えているのです。「目を覚ましていなさい」というメッセージは、24章の42節でも語られていました。「その日がいつ来るか、あなたがたは知らないのだから、目を覚ましていなさい」と。
このように、同じメッセージがここでもう一度繰り返されているということがわかります。そしてまた、「忠実でありなさい」というメッセージもありました。やはり、日々、きちんと備えていなければならない、ということです。
このたとえ話から私たちが学ぶべきことは何か。それが今、私たちに問われているのだと思います。このたとえからどのようなメッセージが語られているかというと、まず、花婿がイエス様を表しているということは、よく分かると思います。
そして、10人の娘たちは、私たち自身を表しているのだと思います。信仰者たちのことですね。このたとえ話から、いくつかのことが確認できると思います。
まず、私たちに与えられている「勤め」というのは、イエス様が戻ってこられるときに、お迎えをするという役割である、ということが言えると思います。
「そこで、天の御国は、それぞれ灯火を持って、花婿を迎えに出る10人の娘に例えることができます」とあるように、この10人の娘たちは皆、勤めを与えられているのです。その勤めとは、花婿が戻ってきたときに、お迎えに出るというものです。
そのために、灯火の油をちゃんと用意しておかねばなりませんでした。この「勤め」は、私たち一人一人に等しく与えられているものなのだと思います。
イエス様は、いつか必ず戻ってこられます。そのとき、眠っていることがないように、目を覚ましていなければなりません。そして、イエス様が来られた時に、きちんとお迎えできるような「備え」が、私たちには求められているのです。
そのために、私たちはそれぞれ灯火が与えられている、ということではないかと思います。第一節には、「天の御国は、それぞれ灯火を持って、花婿を迎えに出る10人の娘に例えることができます」とあります。ここで「それぞれ」と出てきますから、私たち信仰者一人一人に灯火が与えられている、ということです。
この「灯火」とは何でしょうか。さまざまに考えることができますが、やはり「信仰の灯火」であると思います。これは、自分の努力で獲得したものではなく、与えられたものです。信仰も、与えられたものです。
信じるように導かれて、イエス様に対する信仰が与えられました。そして、その灯火を、私たちは日々輝かせ続ける必要があります。イエス様が来られるその日まで、毎日、その灯火を燃やし続ける。そのような「お迎えの務め」が、私たちには与えられているのです。
でも、今日のたとえ話から教えられることは、この「灯火」は、放っておくと次第に弱くなる、ということです。灯火は、常に元気に燃えているわけではありません。やはり、油が必要なのです。
油をきちんと補充しなければ、灯火は消えてしまいます。ですから、いつでも油を備えておかなければならないのです。
私たちも、イエス様を信じたときには信仰の灯火が燃え上がり、本当に熱心に信じていた時期もあったかもしれません。しかし、いつもそうとは限りません。だんだん灯火が弱くなっていくことは、誰にでもあるのです。
さまざまな試練やトラブル、祈れなくなるようなこと、落ち込んでしまうこと、抱える問題、疲労感や元気が出ないといったこと……。そうした中で、灯火が次第に弱まっていくことは、避けられないかもしれません。
けれども、そういうときに大事なのは、「油をちゃんと用意しているかどうか」です。油を用意していれば、安心して灯火を燃やし続けることができるのです。
そしてもう一つ、大切な点があります。10人の娘のうち、5人は賢く、5人は愚かだったということです。
5人の娘は愚かだった、というふうにね。確率50%って言ったら、ちょっと変な言い方になりますけれども、これはたとえ話なんですよね。それを示される時に、私たちも考えることがあるんじゃないかなと思います。「私はどっちの娘なんだろうか。もしかしたら、愚かな娘になっちゃってるんじゃないだろうか?」と。
確率50%、半分半分みたいな。それが、もし全員が愚かだったら、「みんな愚かだな」ってある意味安心できるのかもしれません。でも、半分は賢くて、半分は愚かだっていうところが、なんとも言えない示唆的な割合なんですよね。それを示される時、私たちは「自分はどっちなんだろうか」と考えさせられる。賢い娘でいたいんだけれども、でも意外と愚かな娘になってしまっていないだろうか。そういうことが問われるような、そういうメッセージなんじゃないかと思います。
ですから、私たちは本当に油がちゃんと用意できているのかどうかが大切です。信仰者すべてに灯火は等しく与えられています。ところが、その灯火を燃やし続けるための油の供給がちゃんとできているかどうか。それが、賢いか愚かかの違いなんですね。
ですから、そういうところで、私たちは本当にいつも「賢い」と呼んでもらえるような備えをしておくこと。それが大事なことかな、というふうに思います。
また、今日のたとえ話を通して、もう一つ気づかされることは、「油は他の人からは分けてもらえない」ということです。油が足りなくなってきて、自分の中に油がないと気づいたとき、人に求めても、それは与えてもらえないということですね。
愚かな娘たちは油がなくなってしまったので、油を持っている娘たちのところに行って、「分けてください」とお願いするんですけれども、分けてもらえなかったんです。「なんて冷たいんだろう」と思う人もいるかもしれません。「分けてあげればいいのに」と思う人もいるかもしれません。でも、ここで教えられているのは、「油」というのは人から与えられるものではない、ということなんですね。
人に期待しても、それは与えられるものではないんだ、ということが、ここに教えられているのだと思います。
私たちも元気がなくなってくる時、教会の交わりによって励まされるということは、確かにあります。教会に来て、人との関わりの中で励ましをいただくことは、確かにあります。でも、その励ましというのは、もしかしたら一時的な励ましで終わってしまうことが多いのではないでしょうか。ある意味、それは油のようでありながら、油になりきれないものなのかもしれません。
もちろん、交わりもとても大事で、人との関わりによって励まされるということも確かです。でも、それは単なる人間同士の仲良しグループのような交わりではなくて、「イエス様を共に共有している」からこそ燃やされていく交わりなのだと思います。
ですから、教会の交わりというのは、普通の集団とは違います。人との会話や関わりも確かに励ましになりますが、そこで元気を与えてくださっているのは、実はイエス様なのだと思います。イエス様とともにあるからこそ、私たちは力づけられるのです。
それが、本当の意味での「キリスト者の交わり」なのではないかと思います。
ですから、油というのは、人に期待してももらえない。やはり、それはイエス様から直接いただくものなのだ、ということを覚えたいと思います。
そして、このたとえ話を通して、もう一つ気づかされることは、「油を用意しているかしていないかの結果は、あまりにも違う」ということです。
その違いは、花婿が帰ってくるまでは、あまり意識されなかったかもしれません。油があってもなくても、とりあえず灯火はついていましたので、違いが目立たなかったのです。でも、花婿が帰ってきた時、その油がないということが、いかに大きな結果をもたらすかということが、ここではっきりと表されています。
油をちゃんと用意していた賢い5人の娘たちは、花婿が来たときにお迎えに出て、そのまま祝宴に入ることができました。その喜びの輪の中に加えられ、結婚式の祝福にあずかることができたのです。
ところが、油を買いに行っていた5人の愚かな娘たちは、戻ってきたときには扉がすでに閉じられていました。もう、入れなかったのです。
それは、本当に悲しいことだったと思います。「入れなかった」ということは、大きな悲しみですが、それよりもさらに大きな悲しみが、ここで示されています。
それは、主人に「あなたがたのことを知らない」と言われてしまうことです。
これは、本当に悲しいことです。
でも、それだけじゃないですよね。主人に仕えてきたわけですけども、その主人に「あなた、知らないよ」って言われてしまうことくらい、本当に悲しいことはないような気がするんですよね。ですから、この結果がどんなに大きいか、どんなに違うかということですよね。そういうことが、ここに示されていて。
まあ、そういう、例えばの話をイエス様は語ることによって、私たちに警告してるわけですよね。愚かな娘にならないように、ちゃんと賢い娘であるように。そのために、ちゃんと油を用意しておくようにって。そういうことがね、ここでイエス様から教えられているということを、私たちは心に留めるものでありたいなと思います。
じゃあ、最後にね。何度も言ってるんですけれども、「油って何なの?」「油を用意するって、どうすれば油を用意できるの?」って。そこに行くわけですよね。
油は、精霊を表していることが多いので、「油ってのは精霊の現れなんだ」と考える人もいますし、またそれは、やっぱりイエス様との個人的な関係だと考える人もいます。まあ、いろんな解釈があるところなのかなと思いますけれども、でもやっぱりこれは、神様との精霊であるかもしれませんし、イエス様とのこの個人的な深い交わりということも言えると思います。
けれども、やっぱり私たちが、ちゃんとイエス様に繋がっているということですよね。そして、御言葉に生かされているということ。そしてそこから御霊の力を日々いただいて、そして本当に神様との親しい交わりの中に生かされているという、その関係性。それが「油」と考えていいんじゃないかなというふうに思います。
それで、これはマタイが書いている福音書になるんですけど、ヨハネがですね、ちょっともう一つの箇所を開きたいと思います。ヨハネが、やっぱり終わりの時のことを意識しながら「ちゃんと備えをしていなさいよ」っていう、こうメッセージを語っている箇所があるので、それを開いて今日は終わりにしたいと思います。
ヨハネの福音書ではなくて、ヨハネの手紙の方なんですが、第一ヨハネの、終わりの方ですね。第一ヨハネの2章、26節と27節をお読みしたいと思います。新約聖書の480ページですね。では、26と27をお読みします。
「私はあなたがたを惑わす者たちについて、
これは、18節を見ると、「幼子たち、今は終わりの時です」っていう言葉がありまして、終わりの時が意識されているんですね。そしてその終わりの時って、どういう現象が見られるかというと、「反キリストが来る」と、あなた方が聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって「今が終わりの時である」とわかります、ということで。
反キリスト、つまりキリストを否定するような人たち。そして「キリストは神ではない」「救い主ではない」と否定するような人たちが現れる。そしてそういう人たちが惑わすんだと。惑わす者たちが多く現れるんだ、ということが警告されているんですね。
それで、そのことをずっとヨハネは語ってきて、それで26節で「私はあなた方を惑わす者たちについて以上のことを書いてきました」ということで、この終わりの時代の姿について、ヨハネはこう書いてきてるんですけれども、そういう時代の中にあって、今まさに終わりの週末の時代の中にあって、どういう生き方が必要であるかということで、27節の言葉が語られているわけですね。
ここで、「しかし、あなた方のうちには御子から受けた注ぎの油がとどまっているので、誰かに教えてもらう必要はありません」とあります。ここに「御子から受けた注ぎの油」って出てきますね。これは精霊を表していると考えられますけれども、やっぱりイエス・キリストを信じた私たち一人ひとりには、御子から油が与えられている、注ぎの油が与えられている、精霊が与えられている、ということだと思います。
その注ぎの油が、すべてについてあなた方に教えてくれます。御霊が私たちに教えてくださるんですよね。それは真理であって、偽りではありません。「あなた方は教えられたとおり、御子のうちにとどまりなさい」って。御霊が私たちに何が真理であるかを教えてくださる。その教えられた通りに、御子のうちにとどまりなさい。御言葉が教えてくださったその教えの通りに、イエス・キリストと繋がっていること、イエス様にとどまっていること。
そのことによって、この終わりの日の中にあっても、私たちは惑わされることなく、与えられた信仰の火を灯していくことができるんですよ、ということですね。
そういうことを、ヨハネも教えていて、イエス様が教えてくださったことと重なるような内容かなと思います。やっぱり、そこに精霊の働きもあるし、御言葉によって教えられていく。その中に、イエス様と共に歩む。イエス様にとどまり続ける。そんなことによって、私たちは信仰の火を灯し続けることができるんだということですね。
そのことが教えられていると思います。
次に、私たちも愚かな娘になることがないように、本当に目を覚ましていましょう。その日、その時、いつかは分かりません。いつ来るか分からない。遅くなるかもしれない。真夜中になるかもしれません。眠ってしまうこともあるんですけれどもね。でも、ちゃんと呼び起こしてもらいますので、その時にちゃんと用意できているように。
いつも私たちは、御言葉により頼みながら、その御言葉を通して働かれる御霊の導きの中で、本当に信仰の火を燃やし続け、灯し続ける。そのような歩みを、日々続けていくものでありたいと思います。
では、お祈りをして終わりたいと思います。
愛する神様、
今日は「終わりの日の備え」について教えてくださって、感謝いたします。
信仰が弱く、すぐにつまずいてしまい、また、その灯火を弱めてしまいやすい私たちではありますけれども、どうかいつも、あなたが御霊を与えてくださいましたから、その御霊の導きの中で、御言葉に教えられたとおり、あなたに従い、イエス様にとどまり続けることができるように。
そのようにして、与えられた信仰の火を灯し続け、あなたがお帰りになるその日を待つことができるように、助けてくださるようお願いいたします。
どうぞ、愚かな娘になることがありませんように。
賢い娘であることができるように、私たち一人ひとりを導いてください。
御言葉に感謝し、イエス様のお名前によって、お祈りいたします。
アーメン。