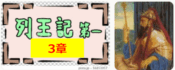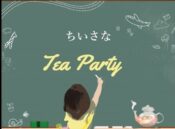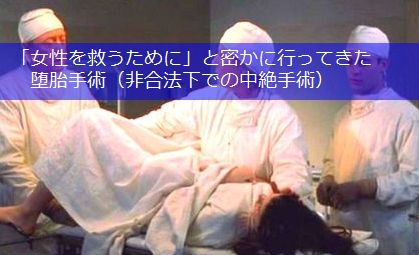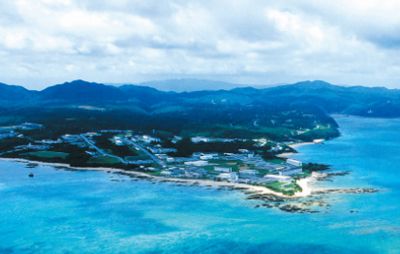「神の国」というパラダイムの回復

以下の記事は「飯能キリスト聖園教会」11/22(土)23日(日)で行われる秋の修養会の学びが深められるために、講師の津嶋理道師から前もって配られたレジメです。これは大作かつ内容が非常によく構成された神学的エッセイです。なお非公開としますのでURLを知っている人だけがご覧いただけます。
簡潔な要約:
「神の国」というパラダイムの回復
-
神の国(御国)とは何か
「神の国」とは、神が王として慈しみ深く支配される領域を指し、死後の天国だけでなく、地上の社会や人の心にも現れる現実です。イエスとパウロは、単なる来世の希望としてでなく、現実に関わる喜びと責任として「神の国」を説きました。 -
神の国の歴史的展開
創造の初め、エデンの園は神の国でしたが、人間の堕落で失われました。アブラハムの子孫イスラエルに回復が託されましたが、成就せず、イエスの到来によって本格的な回復が始まりました。現在は教会を通して神の国が宣教され、将来の完成を待ち望んでいます。 -
救いと神の国の関係
「救い」とは単に死後の天国に行くことではなく、イエスを王と仰いで今(この現実の中で)神のご支配に生き、永遠に神の国の一員となることです。その入国には、イエスの十字架と復活を信じ、「イエスは王だ」と告白する信仰が必要です。 -
神の国の恵みと責任
神は全創造(被造物)に「一般恩寵」を、信仰者には「特別恩寵」を注がれます。教会の使命は救いとともに、この世界全体に神の国の原則・力を実現し、管理者として社会にも貢献することです。 -
神の国の視点がもたらす変化
正しい神の国の理解は、世界観・ライフスタイル・救いの理解・神のビジョンを新しくします。死後だけでなく、今この時代、この地上で神のご支配がどのように現れるかを重視し、日常や社会でも福音を体現します。 -
福音宣教と神の国
福音宣教は単なる個人の救いの案内ではなく、「神の国」をこの世界に拡げる働きです。イエスの宣言・使徒の教えはともに、神の国の到来と成長を中心に据えています。 -
宣教の5つの側面
-
福音自体(イエスの十字架の救い)を伝える
-
神の国のライフスタイルを教える
-
キリスト教世界観を育てる
-
神の国を現す実践的活動
-
神の国の完成(新天新地)を待望する
この体系は、教会の活動すべてと信者の生き方を、神の大きなストーリー(創造→崩壊→回復→完成)の中に位置づけ直すための“枠組み”となります。
本文
「神の国」というパラダイムの回復
はじめに:「神の国」の再発見―私の証し
「神の国」──それは、決して新しい思想ではありません。それは「御国」や「天の御国」という同義語とともに、聖書の中に数多く記されています。
しかし、私たちはその言葉を本当の意味で理解してこなかったのかもしれません。少なくとも、かつての私はそうでした。
「神の国」とは、以前の私にとって「信者が死後に行く世界(いわゆる天国)」とほぼ同じものでした。
ただし、イエス様が「見なさい。神の国はあなたがたのただ中にあるのです」(ルカ17:21)と教えられたので、地上で生きている間もその前味を少し味わえる世界なのだろうと理解していました。
けれども、理解はその程度だったのです。
つまり「神の国」とは、死後にならないとメインディッシュを味わえない晩餐会のようなものであり、地上で生かされている意味は、その晩餐会への招待状と「前味(試食品)」をできるだけ多くの人に配ること──そのくらいに考えていたのです。
「死後にならないとメインディッシュを味わえない」というのは、ある意味では正解です。パウロもピリピ人への手紙の中でそのような願望を吐露しています。
「私の願いは、世を去ってキリストとともにいることです。そのほうがはるかに望ましいのです」(ピリピ1:23)。
ただし、だからといって「地上の世界は、神の国に入るための単なる準備期間や通過プロセスにすぎない」と聖書が教えているわけではありません。
それにもかかわらず、私たちはいつの間にかそのような理解を抱き、それがキリスト教の常識のように思ってきたのではないでしょうか。
だとすれば、なぜそうなったのでしょう?
それは、「神の国」に対する誤解のゆえに、教会の中で真の「神の国」という視点が見失われてしまったからではないかと思います。
イエス様もパウロも、あれほど熱心に「神の国」を語られたにもかかわらず……。
「神の国」の再発見までの導き
数年前、寒河江での教会形成を思い巡らす中で、「私たちは何のために教会を営み、何のために福音を伝えるのか」という根源的な問いを突きつけられました。
当時の寒河江教会は、どんなに頑張っても教勢が伸びず、むしろ減っていくという沈滞期にありました。
「受浸者を生み出せない教会は存在する意味があるのだろうか」と葛藤する日々が続きました。
その一方で、教会には、この世の不条理に打ちのめされ、深く苦しむ人たちも出入りしていました。
彼らにどのように聖書の救いを伝えるのか──いや、それ以前に「彼らにも与えられている神の救いとは何なのか」を自分自身が本当に知っているのか、祈りながら問わされる日々でもありました。
ただ「天国行きの切符を配るだけの伝道」ではどうにもならない現実を、私たちは彼らと共に背負わされたのです。
そのような中で、私は「教会を形成するとはどういうことか」「伝道とは何をすることなのか」と神に問い続けずにはいられませんでした。
「神の国」との出会い
ある日、2015年度の教会目標を立てるために聖書を研究していた時、ふと「神の国」「天の御国」という言葉が、突然に新しい光を帯びて飛び込んできました。
「そうだ! イエス様もパウロたちも、あれほど熱心に伝えていたのは、他でもない『神の国』『天の御国』だったのだ!
福音とは、『神の国』を人々の現実の中にもたらすものだったのだ!」
イエス様が「御国に行けますように」ではなく「御国が来ますように」と祈りなさいと教えられたのは、そのためだったのです。
「神の国」とは、単に死後の世界ではなく、「今ここから」地上に芽生え、成長し、拡大していく世界。
それは、神の究極的な被造世界の回復──すなわち「天地の新創造ヴィジョン」そのものだと。
そのようにして、まさに目から鱗が落ちるような啓示が与えられました。
理解の転換
「もしそうであるなら、福音を伝える目的は、人々を『今』から神の救いのご支配へと招き入れること。
教会を形成するのは、そのような神の国をこの世界に広くもたらし、将来の完成を待ち望みながら生きる民を育てるためなのだ」と強く思わされました。
この理解の転換が、私の信仰と働きに決定的な変化をもたらしました。
教会形成とは、単に教勢拡大を目指すことではありません。
福音宣教とは、単に「天国行きの切符」を配ることではありません。
私たちは今この時から、「神の国」をこの世界と人々の中にもたらしていく──そのような教会と宣教へと召されているのです。
「神の国」という枠組みの再発見
こうして、「神の国」という視点こそ、教会のあらゆる営みを正しく方向づけ、統合する大きな枠組みであることに気づかされました。
たとえば──
-
伝道・教育・奉仕・交わり・礼拝などの教会活動
-
救いと福音、ライフスタイルとの関係
-
福音宣教と社会的責任のバランス
-
創造と新天新地の幻
これらはすべて「神の国」という枠組みの中で一つに統合されるのです。
それはまるで、「神の国」という名のジグソーパズルのようです。
今までバラバラだったピースが、「神の国」という大きな絵の中で、一つの美しい全体像を形作り始めました。
私たちは、その古くから与えられていたはずの枠組みを、ただ使い方が分からず忘れていたに過ぎなかったのです。
「神の国」とは何か
1)定義
「神の国」は、「御国」「天の御国」と同義語です。
ギリシャ語では「ヘー・バシレイア・トゥー・セウー(hē basileia tou Theou)」といい、「バシレイア」は「王国」または「支配の領域」を意味します。
つまり、「神の国」とは「神の王国」、すなわち「神が王として統治される領域」を指します。
ここで言う「国」は、国境で囲まれた地理的な領土のことではなく、王なる神の慈しみ深い支配が及んでいる全領域のことです。
それゆえ、「神の国」はイスラエルという国家を超え、地上と天の両方にまたがる現実であり、個人の心の中にも社会の中にも存在します。
したがって、「神の国」とは死後の天国そのものではなく、「天国」と呼ばれる死後の世界は「神の国」の一部分に過ぎません。
なぜなら、将来完成する神の国──新天新地──には、復活した人々と再臨を迎えた生ける者が共に暮らす世界が約束されているからです(黙示録21:4)。
神の国の推移─創造から完成へ
創造─はじまりの「神の国」
神様は、地上における最初の「神の国」として「エデンの園」を設けられました。
そこに置かれた人間アダムにも、神様の支配に喜んで従う心=霊的「神の国」が与えられていました。
しかし、人間の堕落によって、エデンの園という物質的・地理的な「神の国」と、アダムの中にあった霊的「神の国」の両方が失われ、地上の「神の国」は崩壊したのです。
崩壊と回復への希望
その後、神様は、アブラハムの子孫である「イスラエル」を神の民として選び、「神の国」の回復を託されました。
けれども、イスラエルは旧約聖書に記された歴史の通り、その使命を完全には果たし切れませんでした。
その結果、「神の国」の回復は、「王」である主イエスの到来を待つこととなったのです。
王の到来と回復の完成
時が満ち、二千年前のある日、「王」として主イエスが到来され、ご自身が直接「神の国」の宣教を始められました。
そして「十字架と復活の業」によって、決定的に「神の国」を回復し、その永遠の土台を築かれたのです。
「王」なる主イエスが天に戻られた後は、「王」を信じて神の国の民とされた教会が、「王」が再臨されるその時まで、神の国の宣教・育成・拡大を託されました。
やがて、「王」が再臨される時、「神の国」は究極的な姿に完成します。ただ、その時までは「神の国」は未完成のまま推移します。
しかし、「神の国」の民である教会は、「王」が再び来られる日を待ち望みつつ、その繁栄のために労し続けます。
私たちは、今まさに、そのような使命に召されているのです。
神の国と救い
天にあった「神の国」の地上への到来
「神の国」は、創造以前から天にあった世界です。
主イエスの降誕と共に、「神の国」は地上にもたらされました。「時が満ち、神の国が近づいた」(マルコ1:15)という言葉からも分かるように、それはすでに旧約時代から待望されていたのです。
ただし、主イエスの到来まで、その真の姿は誤解されたままでした。
初代教会は、主イエスの教えと十字架の福音によって「神の国」の真の姿を啓示された神の民となりました。
教会の使命
主イエスは教会に次の使命を託されました。
-
「神の国」を宣べ伝え、人々を招き入れる(宣教)。
-
「神の国」にふさわしいライフスタイルを教える(育成)。
-
神の国を、ますます地上にもたらす(拡大)。
ところが、長い教会史のなかで「神の国」への神様のビジョンはしばしば歪められ、見失われてきました。
現代の教会でも、「神の国」を正しく説明できなかったり、誤解されている現実が見られます。
例えば、「神の国」=「死後の世界の天国」と考える場合や、「神の国」=「地上天国」とだけ考える場合などです。
人間は生来、「神の国」よりも「自分の国」を追求する自我をもっています。
その中で「十字架の救い」を聞いても、その「救い」が歪められてしまう危険が生じます。
「救い」は、単に「死後に天国へ行けること」や、「地上天国の建設」、あるいは「自分の国が祝福されること」だけではありません。
主イエスの十字架の救いは「神の国」を正しく理解してこそ、真価が分かります。「救い」とは、主イエスを「私の王」と仰ぐ人に新生が与えられ、主の支配=「神の国」に、今から永遠に入れられて、「神の国」にふさわしいライフスタイルに生かされ、「神の国」のために仕える者となることです。
ただし、私たちは、その「救い」を自力で得ることはできません。生来の罪人である私たちは、「自分の国」の王でありたいと願い、主イエスを「王」と仰ぐ「神の国」への入国を拒みがちです。また、神様もそのような私たちを、そのままでは神の国への入国を許すことはできません。
だからこそ、主イエスの十字架と復活が不可欠なのです。十字架と復活によって、私たちは「自分の国」の王であろうとする罪をきよめられ、主イエスを王と仰ぐ信仰が生まれ、神の国への入国が許されるのです。
神の国と福音
福音の本質
「福音」とは「救いの良い知らせ(グッドニュース)」です。
ギリシャ語「ユーアンゲリオン」は、1世紀ローマ時代に「ローマ皇帝のような絶対的な王が絶対的支配によって全世界に救いをもたらす」という意味合いを持ちました。
聖書では、「王の支配」は「神の支配」です。
つまり、「福音」とは「神の国=神の支配が地に到来し、誰にでも憐れみ深く開かれて、誰でもそこに入って暮らすことができる救いの知らせ」です。
けれども、堕落した人間は自力で「神の国」に入ることができません。
それゆえ、神様ご自身が一方的な恵み(特別恩寵)によって、そのことを可能にしてくださいました。
それが「王」である主イエスの十字架の贖いによる救いであり、主イエスを信じるだけで、どんな人にも無償で与えられるのです。
「福音」とは、「神の国に入れられる救いが、王なるイエスの十字架の贖いによって、すべての人に無償で与えられている──という良き知らせ」なのです。
「イエスは王だ」と信じる信仰
信仰の本質
「神の国」「救い」「福音」が上述のとおりだとすると、救われるために必要なのは「イエスは王(主)だ」と信じる信仰であることがわかります。
これは次の聖句で裏付けられます。
「なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです」(ローマ10:9)。
初代教会では、「イエスは王(主)だ」と信じる信仰が救いの前提でした。なぜなら、それは「イエスが王として支配される神の国」に入る国籍を得る信仰だからです。
ただし、「イエスが十字架で死に、復活された」と信じることがそのまま「イエスは王だ」と信じることに等しいとは限りません。
「十字架で死に復活したイエス」を単なる「願いを叶えてくれる存在」としか捉えなければ、その人は「イエスは王だ」とまだ信じていないからです。
「救われる信仰」とは、「イエスは王だ」と告白し、主イエスの前にひれ伏す謙遜な信仰です。
この信仰は、聖霊によって初めて生まれます。
「聖霊によるのでなければ、だれも『イエスは主です』と言うことはできません」(Ⅰコリント12:3)。
「イエスは王だ」と信じるとは
「イエスは王だ」と信じるとは、イエスが天地創造の前から王であったこと、また地上で王として即位し、王の権威ある奇跡を示されたことを含みます。
しかし、最も本質的なのは「イエスが十字架で死に、復活された」ことを信じることです。
「キリストが死んでよみがえられたのは、死んだ人にも生きている人にも、主となるためです」(ローマ14:9)。
「イエスは十字架の死と復活を通して、死後の世界までをも征服し、真の王となられました。
そのため、「イエスの十字架の死と復活」を伝えることが、「イエスは王だ」と信じる信仰へ人々を導くうえで欠かせません。
神の国と「一般恩寵」「特別恩寵」
一般恩寵と人間の使命
天地創造の初めから、神様は地上の全被造物に良きものを恵み与えられました。
これを「一般恩寵」と呼びます。人間は「一般恩寵」あふれる世界の管理者として造られました。
しかし、人間の堕落によって、この使命にふさわしくなくなってしまいました。
特別恩寵と新しい使命
それでも神様は、堕落した人間・被造世界にも「一般恩寵」を与え続けました。しかし、救われるには「主イエスの十字架による救い」(特別恩寵)が不可欠となりました。
「神の国」とは、「特別恩寵」によって救われた神の民だけの世界でなく、「一般恩寵」を受け続ける全被造世界をも包含します。
イザヤ書もそのような包括的な「神の国」のヴィジョンを示しています(イザヤ11:6-9)。
救われた神の民は「神の国」の管理者として現にこの地上で責任を果たすことが求められています。
この使命を通して、神の国をこの世界にもたらすのです。
「神の国」の視点で変わること
真の世界観を得る
「神の国」への正しい理解は、この世界を見る目=世界観を変えます。
「神の国」は、死後の天国だけではなく、天と地の両方を含みます。
聖書は、最終的な滅びの時にも、創造世界が回復され新天新地になると約束します(Ⅱペテロ3:13、ローマ8:19-21)。
新しいライフスタイルへ
この視点を持つと、「神の国」にふさわしいライフスタイルを求めて生きるようになります。
それは、神の国の国民として王なる神に忠誠を尽くし、喜ばれる者となる生き方です。
個人的な主従関係だけでなく、「神の国」という広い共同体の中での奉仕や交わりに目が開かれていきます。
「救い」の理解が深まる
「神の国」を知ることで、「救い」とは願いが今すぐ叶うことではなく、「神のご支配の中に委ねて安心して生きること」だと気付かされます。
神のビジョンの理解
神様の目的は、天国に人を集めることだけではありません。
天と地が統合された「神の国」の完成へと導くことが究極のビジョンです。
この全体図を知ることで、信仰と働きの方向性も刷新されます。
神の国と福音宣教
宣教の中心テーマ
主イエスは福音宣教の第一声として「時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい」(マルコ1:15)と宣言されました。
使徒の働きも「神の国」が最初から最後まで貫く主題となっています。
「神の国」の建設こそ、福音宣教の本質です。
単に多くの人が救われること以上に、その結果「神の国」が全被造世界に麗しく実現されることが神の御心となっています。
福音宣教における5つの局面
主要な5局面の概要
-
福音を伝える(ケリュグマ)
主イエスの十字架の福音を伝え、罪の赦しによる救いに導き、「イエスは王」と信じさせる。 -
神の国のライフスタイルを教える(ディダケー)
「神の国」の国民として生きる生き方を教え、育てる。 -
キリスト教世界観を養う
時代や文化に左右されず、「神の国」の目と知恵で社会課題に向き合う力を育てる。 -
神の国をもたらす活動への献身
この世界の現実に実際の奉仕・活動で「神の国」を現す。 -
神の国の完成の待望
新天新地=完成された「神の国」を待ち望み、未完成の今を信仰で励まし合う。
局面の優先と聖書的バランス
この5つはすべて重要ですが、優先順位をつけると――
第一はA「福音」を伝える(ケリュグマ)、
第二はB「神の国のライフスタイル」を教える(ディダケー)です。
C「キリスト教世界観」やD「神の国をもたらす活動」は、特に現代の教会が社会と向き合う際の課題に応えます。
E「完成の待望」はどの局面にも密接に関わります。
特に、A・B・Eはあらゆる時代・文化に共通する真理であり、聖書自身も多くのスペースを割いて語っています。C・Dは適用の分野として、時代や状況によって姿を変えます。