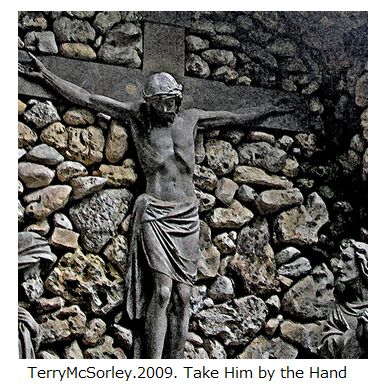人工妊娠中絶とキリスト教

「サイダハウス・ルー ル」という映画があります。人工妊娠中絶に関わる大きな問題を私たちに提示し、「生きる」ということについて、深く考えさせてくれる作品です。(1999年製作のアメリカ映画)。
1.あらすじ

見たことのない世界に感動するホーマーであったが、生活のため、ウォリーの実家のサイダーハウス(リンゴ農園)で働くことを決める。「①ベッドではタバコ禁止、②酒を飲んだら粉砕器を操作せぬこと、③……」。「白人」雇用主が決めたルールが貼ってある小屋「サイダーハウス」で寝起きしながら、貧しぃ「黒人」の季節労働者たちとともに、リンゴの収穫作業に精をだす。
そんなある日、事件がおこる。ボスのミスタ-・ローズが、自分の娘を妊娠させてしまったのだ。望まない妊娠をした女の絶望的な状況を目の当たりにし、ホーマーは苦悩する。何もしなくてもぼくは悪くない……。しかし、ホーマーはついに、拒否しつづけてきた堕胎手術に踏み切るのだった。
2.中絶に手を貸すキリスト者
中絶を軸に展開するこの映画には、中絶を容認し、手を貸すキリスト者が登場する。看護婦のエドナとアンジェラだ。毎晩、子どもたちとともに神に祈りを捧げる二人は、ラーチ医師の助手として堕胎手術を助けるぼかりではない。産んでも育てられない女たちの心に寄り添う、カウンセラーの役目も果たす。
エドナとアンジェラの背後には1950年代アメリカで、中絶合法化に向けて運動した聖職者たちや、医師や法律家たちの 姿が垣間見られる。
1940年代から中絶禁止法の運用が厳しくなったアメリカでは、中絶希望者を犯罪者のように扱う審査員の姿勢、闇堕胎の失敗で病院にかつぎ込まれたり、死んでいく女のおびただしい数、これらすべてに関係する人種や階級による差別などに直面しながら、施行後半世紀以上たっても、中絶を抑制するどころか、女に「不必要な苦痛や死」を与えつづけている中絶禁止法は、問題だと考えるようになったのでした。この運動に参加した人たちは、「現に悩み苦しんでいる女性たちがいる以上、それを救ぅのが聖職者としてのやるべき仕事」であり、中絶の問題は「絶対的な善悪基準によって判断するのではなく、状況倫理的に判断しよう」と考えたというのです(荻野美穂著「中絶論争とアメリカ社会 身体をめぐる戦争」岩波書店)。
3.中絶は殺人か?
望まない妊娠をした女たちの救済策として、中絶を認め、手を貸す……。このよぅなキリスト者のあり方を、意外に感じる人が多いかもしれない。
なぜなら戦後、刑法堕胎罪を残したまま「優生保護法」(1996年に「母体保護法」に改正)を施行することにより、中絶を実質的に自由化した日本では、表に現れたキリスト者の声は以下のようなものでした。
つまり、胎児は「精子と卵子とが結合して母体に受胎した瞬間」から「人間生命体」であり、中絶は「罪である」という考え方が主流を占めていたのです。 プロテスタントでは、1984年に、福音派のグループに属する聖職者たちが中心になって「小さないのちを守る会」を発足させ、中絶撲滅運動を推進しています。
これとは反対に、I989年に 来日した英国教会の主教、H・モンテフィオレは「中絶と人工授精」と題した講演のなかで、受精卵,胎児を、神経や脳の構造の発達、刺激反応の発生など、身体の成長にともなって魂が付与され、しだいに人間としての人格的な性質を備えていく存在)とする自分の立場を、生物学的かつ神学的に説明。
(しだいに人間になっていく)受精卵・胎児は、尊重されなければならないが、絶対ではないとしたうえで、中絶せざるを得ない場合には、「当事者としての女性がだれよりもよく、そうした状況を判断する立場にあり」、彼女がよく考えて決めたことを、他の者が「非難する権利はない」と女性の決定権を擁護したのです(技術社会と信仰」所収、新教出版社)。
4.当事者としての女が、だれよりも状況判断する立場にある……。
「サイダーハウス・ルール」の最後の場面では次のように描かれている。
「③屋根の上で昼食をとらないこと、④屋根の上で寝ないこと……」。
壁に貼ってあった紙をホーマーが読み終わると、文字が読めないため、何が書いてあるのか訝っていた仲間たちは怒りはじめる。馬鹿にしている。当たり前のことじゃないか。ミスター・ローズは立ち上がっていう。「ここに住んでいるのはだれだ? 汗水流して働いているのはだれだ? その規則は、ここにすんでいないヤツが作った。俺たちじゃないか。規則を決めるのは俺たちだ」。
共感できる場面である。
妊娠するのはだれなのか? 9力月間体の中に胎児を抱えるのは誰なのか? 産むのは誰なのか? 中絶手術を受けるのはだれなのか?べッドに縛り付けられ、足を開いて血を流すのはだれなのが? 痛みに耐え、眠れぬ夜を過ごすのはだれなのか?
出産ばかりでなく中絶にだって、女たちは命がけで臨んでいるのです。
「中絶はよくない」なんて、女は身体で知っている。「胎児の命は大切だ」。そう思っていても産めないときが女にはある。そのとき、どうするのか 。それは自分の身体・生命・人生をかけて、妊娠・出産に臨む女だけが判断し、決定できることではあるまいか。
「そうだ」。ホーマーは肯くと、ルールの紙をストーブの火にくべる。そしてエドナとアンジェラの祈りの声が響く「孤児院」へと帰っていく。望まれない子の面倒を見、望まれない妊娠を中絶させるために。この二つは矛盾しない。どちらも、「女・子ども」に生きる道を用意することなのだから。
5.「それでいい」と、キリスト・イエスもいうだろうか?
妊娠・出産が死活問題になるがゆえに、中絶・嬰児殺しを試みざるを得なかっただろう「娼婦」たち(マタイ21章・28一32)、制度にのっとらない性関係のゆえに、社会から疎外された外国の女(ョハネ4章・1一42)、12年もの間続いた不正出血の背後に、人に話せない事情を抱えた一人の女(マルコ5章・21-34)など、社会のしわよせを押しつけられた女たちとともに生きたイエス様。
イエス様が、性差別、「障がい」者差別、外国人差別、シングル・マザー差別など、差別社会のただなかで生きる女たちの、生き難さのなかでなされる精いっぱいの決断を、承認し尊重しないわけがないのではないだろうか。
女だけが決められる 。だから、女が生きやすい社会、産んでも大丈夫と思える社会をつくっていくことこそ、中絶を減らす道なのだ。最近キリスト教界のなかで批判の声が高まっている出生前診断の広がりと「障がい」を持つ胎児の中絶も、その道を通ってこそ、くい止められる。
(参考・引用文献:「現代キリスト教の視点」17P に掲載されている大嶋果織著「女だけが決められる」)。