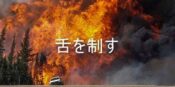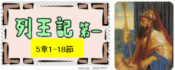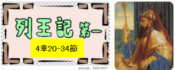マタイの福音書23章13~28節

<要約>
このメッセージは、マタイの福音書23章にある「六つの災い」に関するイエス・キリストの警告を中心に、特にパリサイ人や律法学者たちの偽善について語っています。彼らは外見を整えることに熱心で、杯や皿の外側は清めるが、内側は強欲や放縦、不法、偽善に満ちていると非難されています。
イエスは、まず内側を清めることの重要性を説いており、外側だけを整えても意味がなく、本質的な問題は心の中にある神に対する不従順だとされています。これは私たち自身にも当てはまり、人の目や評価を気にするあまり、心の状態には無頓着になりがちです。
また、偽善的な生き方の根本には、「人の前で生きる」という姿勢があり、神様ではなく他人の目を意識して生きてしまうことが原因だと指摘されています。このような生き方は、やがて自分自身をも欺き、心を苦しめるものとなります。
このような私たちの弱さと罪を正す唯一の道は、イエス・キリストの十字架による救いであり、私たちは日々悔い改め、御言葉に立ち返り、御霊に満たされながら、神の前で正しく生きていく必要があると締めくくられています。
<筆耕>
13節の「災いだ」という言葉も、非常に厳しい告発の言葉ではあるのですが、そこには本当に深い深い、イエス様の悲しみと痛み、そして嘆きの思いが込められているということですね。
そういうことを覚えながら、彼らが抱えていた問題がいかに深刻であったかということを、私たちは心に留める必要があります。
そして、偽善の律法学者、パリサイ人たちが登場しますね。「偽善」という言葉が使われていますが、彼らは見かけをよく見せようとする一方で、内面にはさまざまな課題を抱えているということへの、イエス様からの指摘がなされているのです。
「災いだ」という言葉は7回繰り返されますが、それと合わせて繰り返されているのが、「目の見えない者たち」という言葉です。
本日読んだ箇所の中でも繰り返されています。16節では「目の見えない案内人たち」、17節では「愚かで目の見えない者たち」、19節でも「目の見えない者たち」、24節でも「目の見えない案内人たち」、26節では「目の見えないパリサイ人」と記されています。
つまり、彼らが本当に抱えている問題の根本的な原因は、「目が見えない」ということであると、イエス様は繰り返し語っておられるのです。
もちろん、彼らは実際に目が見えなかったわけではありません。これは霊的な意味で、「本当に大切なものが見えていない」状態を指しています。
そのような霊的盲目こそが、さまざまな問題を引き起こす原因であるということが、ここから見えてきます。
そして、より深刻なのは、彼ら自身が「自分たちは見えている」と思い込んでいるという点です。そこに、さらに大きな問題があるのではないかと思います。
このことについては、ヨハネの福音書でもイエス様が指摘されています。ヨハネの福音書9章41節で、イエス様はパリサイ人たちに対してこう語られました。
「もしあなたがたが盲目であったなら、あなたがたに罪はなかったでしょう。しかし今、『私たちは見える』と言っているのですから、あなたがたの罪は残るのです。」
盲目であるという自覚があれば、まだ救いの余地があったはずです。盲目であることに気づいていれば、「見えるようになりたい」という願いが生まれたでしょう。
しかし、自分たちは見えていると思い込んでいるため、救いの必要性を感じない。そうであれば、悔い改めようとすることもなく、その態度は非常に深刻だと言えるのです。
ここまでも、律法学者とパリサイ人の問題が、何度も何度も繰り返し指摘されてきました。イエス様は、その点を徹底して語っておられます。
なぜそれほどまでに強く語られているのか?それは、私たち自身もまた、パリサイ人のようになってしまう可能性を持っているからではないでしょうか。
私たちも、いつでもパリサイ人のような心に陥ってしまうことがあります。ですから、この聖書の言葉を通して、私たちの内側が探られ、照らされていく必要があります。
神様には、私たちの内面のすべてが見えている。そのことを意識しながら、このイエス様の言葉を受け取り、悔い改めに導かれていきたいと思います。
さて、イエス様が「災いだ」と言われた6つの事柄について、今日はそのうちの2つを取り上げたいと思います。7つ目については、また来週に。
まず最初は、13節です。
「災いだ、偽善の律法学者、パリサイ人たち。お前たちは人々の前で天の御国を閉ざしている。お前たち自身も入らず、入ろうとしている人々も入らせない。」
ここでは、彼らが「天の御国を閉ざしている」という問題が指摘されています。自分たち自身も天の御国に入らず、しかも、入ろうとしている人々さえも入らせない。
この「入ろうとしている人々」とは、救いを求めている人々のことです。つまり、彼らは自分が救われようとしないだけでなく、救われようとしている人々の前にも立ちはだかって、道をふさいでしまっているのです。
これは非常に重大な問題です。
私たち自身の振る舞いが、同じように、救いを求めてやってきた人々の前で、天の御国を閉ざしてしまうようなことになっていないか?そのことを、自分に問いかけなければなりません。
また、教会として、本当に救いを明確に提示できているかどうかも問われています。救いを求めて教会に来た人が、救いが見えず、わからずにそのまま帰っていってしまう。そんな残念なことが、実際に起こっているかもしれません。
ですから私たちは、イエス様のこの指摘をしっか��と受け止めて、自分自身が救いの妨げになることがないよう、救いを求めてやってくる人々に、きちんと福音を提示できる備えを常にしていたいと思います。
次に2つ目、15節です。
「災いだ、偽善の律法学者、パリサイ人たち。お前たちは一人の回収者を得るために、海と陸を巡り歩く。そして、回収者ができると、その人を自分より倍も悪いゲヘナの子にするのだ。」
ここでは、彼らが回収者を得るためには非常に熱心だったものの、その回収者をかえって自分たちよりも悪い存在にしてしまっている、という問題が指摘されています。
せっかく回収した人を、律法主義や形式主義に引き込んでしまい、かえって神から遠ざけてしまうという、深刻な結果を生んでしまっているのです。
これは、単なる熱心さだけでは解決しない問題です。大切なのは、正しい方向へ導くことができているかどうか。そのことを、私たちも問われているのだと思います。
次に、16節〜22節に記されている3つ目の「災い」です。
「災いだ。目の見えない案内人たち。あなたがたは言う。『神殿にかけて誓うのは何でもないが、神殿の黄金にかけて誓うなら、それを果たさなければならない』と。愚かで目の見えない者たちよ。どちらが大事なのか。黄金か、それとも黄金を聖なるものとする神殿か。またあなたがたは言う。『祭壇にかけて誓うのは何でもないが、その上にある供え物にかけて誓うなら、それを果たさなければならない』と。目の見えない者たちよ。どちらが大事なのか。供え物か、それとも供え物を聖なるものとする祭壇か。祭壇にかけて誓う者は、祭壇とその上にあるすべての物とにかけて誓うのです。神殿にかけて誓う者は、神殿とそこに住まわれる方とにかけて誓うのです。また天にかけて誓う者は、神の御座と、その上に座しておられる方にかけて誓うのです。」
ここで指摘されているのは、誓いの扱いにおける偽善的な姿勢です。
彼らは、「神殿にかけての誓いは果たさなくてもよいが、神殿の黄金にかけての誓いは果たさなければならない」といったように、自分たちの都合で誓いの重さを使い分けていました。
しかし、イエス様は、何が本当に重要かを見失っている彼らの態度を、「目の見えない案内人たち」として非難しておられるのです。
神殿にかけて誓うことは、それ自体が神聖なことであり、それを聖なるものとしているのは黄金ではなく、神の臨在です。また、供え物よりも、それを聖なるものとする祭壇のほうが重要です。
つまり、彼らは「外側の価値あるもの(黄金、供え物)」にばかり目を向け、神そのものや神の御業を軽んじていたということが問題なのです。
私たちもまた、「本当に重要なもの」を見失ってしまう危険があります。目に見えるもの、価値があるように見えるものばかりに目を奪われてしまって、神ご自身のご臨在や、神との関係をおろそかにしてしまうことがないように、自分自身を省みたいですね。
続いて、4つ目は、23節〜24節です。
「災いだ、偽善の律法学者、パリサイ人たち。あなたがたは、ミント、ディル、クミンの十分の一を納めながら、律法の中で、もっと重要な正義とあわれみと誠実をなおざりにしている。これこそ行うべきことであり、しかも他のこともおろそかにしてはならないのだ。目の見えない案内人たち。蚊はこし取るが、らくだは飲み込んでいる。」
彼らは、細かい律法の実行(たとえば香辛料の十分の一を納めること)には非常に熱心でした。しかし、神が本当に求めておられること――正義、あわれみ、誠実――といった神の御心の核心となる事柄をなおざりにしていたのです。
「蚊はこし取るが、らくだは飲み込んでいる」という表現は、イエス様の皮肉を込めた強い批判です。つまり、取るに足らない細部にはこだわるのに、圧倒的に大きな問題には無頓着であるという矛盾した姿勢が、ここで指摘されています。
信仰生活においても、細かいルールや儀式にばかり集中しすぎて、本来大切にすべき愛や憐れみ、正義、誠実さといった神の本質的な要求を忘れてしまうようなことが、私たちの中にも起こりうるのです。
ですから私たちは、「どちらもおろそかにしてはならない」ことを覚えつつ、何が神にとって優先すべきことなのかを、いつも心に留めて歩んでいきたいと思います。
本当に神様から引き離してしまっていると、それは確かに愚かなことだな、というふうに思いますよね。
ですから、聖書で示されている真理――それは本当に神様からの真理なのですが――私たちもそれを受け取る上で、気をつけなければいけません。
いろんな人間レベルの決めごとにしてしまって、「これをちゃんと守っているかどうか」「どれだけしっかりやっているかどうか」――それが、まるで神様の前での基準のように扱われてしまって、一番大事なことが抜け落ちてしまうんですね。
「ちゃんとやっているか、やっていないか」「どれだけ忠実にやっているか、やっていないか」、そういうところばかりに関心が向いてしまって、私たち自身も、そうした傾向に陥りやすいのではないかと思います。
ですから、私たちもこのイエス様の指摘からよく気をつけて、注意するものでありたいなと思います。
さて、4番目に行きたいと思います。4番目、23節です。
「災いだ、偽善の律法学者、パリサイ人たち。あなたがたは、ミント、イノンド、クミンの十分の一を納めているが、律法の中で、はるかに重要なもの――正義と憐れみと誠実――をおろそかにしている。十分の一もおろそかにしてはいけないが、これこそ実行しなければならないことだ。」
これはどういうことかというとですね、「小さなことにこだわる一方で、本当に重要なことをおろそかにしてしまっている」、そういう愚かさがあるということです。
ミント、イノンド、クミンというのは、植物でしょうかね。お料理に使ったり、香りのよい香料として使われることもあります。そういうものを収穫したときに、彼らはその十分の一を神様に納めていたというんですね。これはすごいことだと思います。
私たちも、収入の十分の一を神様に献金する、ということがあるかもしれませんし、聖書でもそのように教えられています。与えられたものに対しての感謝として、十分の一をささげるという姿勢は、大切なことです。
でも、自分で育てた植物の収穫から、十分の一を神にささげるという感覚は、私たちにはあまりないかもしれません。それでも、当時のパリサイ人たちは、そういうところまでしっかりとやっていた。そこは本当に「すごいな」と思うのです。
そういう小さなことにまで忠実に、神様にささげていたという姿勢は素晴らしいと思います。けれども、ここでイエス様が指摘しておられるのは、「もっとも肝心なことをおろそかにしている」という点なんです。
正義と憐れみと誠実――これらをないがしろにしている。もちろん、十分の一をささげることも大切です。神様に対する感謝のしるしとして、大切な行為です。
けれども、それ以上に、「もっとしなければならないことがあるのではないか?」「もっと大事なことがあるのではないか?」と、イエス様は問いかけておられるのです。
つまり、細かな律法やルールには非常に忠実だった彼らですが、「正義を行うこと」「人に憐れみをかけること」「神の前に誠実であること」といった、もっとも大切なことが抜け落ちていた――そのことをイエス様は非難しておられます。
私たちも、小さなことを大切にすることは重要です。聖書にも「小さなことに忠実な者は、大きなことにも忠実である」とありますから、小さなことをおろそかにしてよいということではありません。
しかし、あまりにも細かいことばかりに気を取られてしまい、すぐ人を批判したくなるような傾向があれば、それは問題です。
「そこに本当に憐れみがあるのか?」「神様の前で誠実さがあるのか?」――そのことが問われているのだと思います。私たちは、そこに意識を向ける者でありたいと思います。
そしてもう一つ、次に出てくるのが、「蚊をこして、らくだを飲み込んでいる」という、少し面白い表現ですね。
蚊というのは、とても小さな虫です。当時のユダヤ人たちは、ぶどう酒を飲むときに小さな虫が混じらないように、こして飲む習慣があったそうです。本当に純粋なぶどう酒を飲むために、虫などの混ざり物が入らないように気をつけていたわけです。
そのように、小さな部分にはとても気をつけている一方で、「らくだを飲み込む」とはどういうことか――つまり、明らかに大きな問題、重大な罪や不正には無頓着である、ということです。
イエス様は、別のたとえでも「他人の目の中のちりを取ろうとしながら、自分の目の中の梁(はり)には気づかない」と語られましたね。
あるいは、「らくだが針の穴を通るよりも、金持ちが神の国に入るほうが難しい」といった表現もありました。
少し大げさな言い回しではありますが、言いたいことはとてもはっきりしています。細かいことには注意を払っていても、一番大事なことがなおざりにされている――この点が、ここでも繰り返し語られているのです。
これは、私たち自身もまた、よく気をつけなければならないことだと、改めて思わされます。
そして、5番目と6番目は、常に25節、27節以降のところです。ここはまさに、彼らの偽善の問題ですね。
まあ、さっきから「偽善の律法学者」というふうに表現されていて、彼らの偽善が問題だというふうに言われていますけれども、ここではまさに、その偽善のことが指摘されていることが分かると思います。
25節、「災いだ、偽善の律法学者、パリサイ人。お前たちは杯や皿の外側は清めるが、内側は強欲と放縦で満ちている。目の見えないパリサイ人、まず杯の内側を清めよ。そうすれば、外側も清くなる」。
ということで、彼らはですね、外側は一生懸命清める。杯や皿の外側は一生懸命清めるんですけれども、でも中身はよく見えない。見えない中には、実は強欲と放縦でいっぱいになってしまっている。
だから、「まずは内側を清めなさい。そうすれば、外側も清くなりますよ」というふうに、彼らの偽善者としての生き方、行動、そのことがここで指摘されているということですね。
で、私たちも、外側を清めることには一生懸命なんだと思うんですけれどもね。要するに、「人によく見せる」ということでしょうか。良い印象を与えることに関しては一生懸命なんだと思うんです。
でも、私たちは内側に関しては無頓着であることが非常に多いんじゃないかなと思います。実はよく自分の内側を見てみると、強欲とか放縦とか、非常に自己中心な思いでいっぱいになってしまっている。
そのことは、あまり気にならない。一方で、外側ばかり気にしている。これが人間の姿だと思うんですけれども、そういうことが、イエス様によって指摘されているということです。
そして、最後の27節も偽善のことです。
「災いだ、偽善の律法学者、パリサイ人。お前たちは白く塗った墓のようなものだ。外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れでいっぱいだ」。
同じように、お前たちも、外側は人に正しく見えても、内側は偽善と不法でいっぱいだ、ということです。
さっきの5番目のその間のところの指摘は、偽善者としての行動とか生き方、振る舞いというものが指摘されていたと思いますけれども、この27節のところでは、より深く、その偽善者としての「本質」とでも言うべき、人の在り方や生き方、そのもっと内側にある、本質的な部分の指摘がされていると言えるでしょう。
もっと深いところに、同じ偽善があるんですね。イエス様は、もっと深いところに偽善があるとおっしゃっているわけです。
そこから偽善が生まれてくる。ですから、どんなに私たちが頑張ろうと思っても、直らないんですよね。そういう私たちの本質の中にあるわけですから、もう直らないんです。
「お前たちは白く塗った墓のようなものだ」と。お墓の外側は綺麗にしてるけど、内側には死人の骨やあらゆる汚れでいっぱいだ。
同じように、お前たちも外側は人に正しく見えても、内側は偽善と不法でいっぱいだ。さっきは、「内側は強欲と放縦で満ちている」という言い方でしたね。
その話の中では、私たちの心の中にある、人間の持っている非常に欲深い、自己中心な思いに注目が置かれていましたが、今回はこちらでは「偽善と不法でいっぱいだ」という言い方になっていて、やはり神様の御心に背いているところから、いろんな問題が起こってくるんだなと思います。
私たちの中心、心の中にあるのは、もちろん欲もあるし、自分勝手な思いもある。でも一番中心にあるのは、やっぱり「神様の御心に従わない」という不従順。それが根本なんですね。
そこから来ている。私たちはつい人間の思いにとらわれて、本当に自分勝手な思いにとらわれてしまう。
その深いところには、やはり神に対する反逆、反発。そういうものがあるということなんです。
イエス様は、見事に私たちの心の現実というものを見抜かれて、聖書でご指摘されている。まさにその通りだと思います。
私たちは、そうなると本当に救いようがないんです。もう、自分の努力でどんなに頑張っても、内側がきれいにできない。
内側がきれいにできないと、外側はすぐ偽善になる。みんな、自分をごまかし、人をごまかしながら生きているんだと思います。
私たちは皆、どこかでそういう生き方は変わらないし、そういう社会も変わっていかない。救いがないんですね。
だからこそ、私たちには本当にイエス様が必要です。だからこそ、イエス様の十字架にすがるしかない。
だからこそ、イエス様の十字架というのは、私たちにとって、ありがたく、尊く、本当に救いなんだということですね。
そんなことを、ぜひ覚えていてください。イースターが終わったばかりですけれども、私たちはまた改めて、イエス様の十字架を仰ぎ見ながら、そこに本当に悔い改めを持って、許されて、内側からイエス様によって清めていただく。
イエス様の十字架の血によって清めていただく。そして、御霊によって満たしていただく。そういう生き方に導かれていくものでありたいなと思います。
彼らがどうして偽善になってしまうのか。やはり、ここをずっと読んで分かることは、「神様の前で生きる生き方」ではなく、「人の前で生きる生き方」になってしまっている、というところに問題があるんだと思います。
この間学んだところの5節でも、「彼らがしている行いはすべて人に見せるためです」という指摘がありました。イエス様の言葉でね。
彼らがしている行いは、いかにも敬虔そうに見えて、神様の前で生きているかのように見えるんですけれども、実際にはすべて「人に見せるため」なんです。
全然、神様のことを意識していない。ただ、人のことしか意識していない。人に見せるための信仰になってしまったら、すぐに偽善になってしまうんです。
そして、すぐに私たちもパリサイ人のようになってしまうんですね。
私たち日本人には「世間体」という言葉がありますが、これは非常に日本的な言葉だと言われています。私たちはすぐに世間体を気にします。
世間で人からどう見られているか、どういう評判になっているか。人から悪く言われていないかを気にするあまり、つい外側のことばかり考えてしまう。
そういう傾向、日本人には特に強いのかもしれません。けれども、そういう課題があるんだと思います。
そういう意味で、私たちはすぐに見えなくなってしまう。イエス様がここで「目の見えない者たち」と何度も何度も指摘されているのは、やっぱりそういうことなんだと思います。
本当に大事な神様が、見えなくなってしまうんですね。人のことばかり見て、この世の目に見えることばかり見ていると、一番大事なものが見えなくなる。神様が見えなくなる。真実が、真理が見えなくなる。神の恵みが見えなくなる。神の愛がわからなくなる。
そうすると、私たちはすぐに「人々を愛すること」ではなく、「愛されること」ばかりを期待するようになってしまう。そして、愛されないと不満になって、人を批判したり、どんどん悪循環に陥っていくんですね。
それでも、よく見せようと頑張るので、どんどん苦しくなっていく。偽善にすぐに陥ってしまう。
そういう弱さを、私たちはみんな抱えているんじゃないかなと思います。
だからこそ、いつも目の前に神がおられるということ、神様の前に生かされているということ、その神の前での信仰が、私たちにはいつも問われているんだということを、忘れないようにしたいと思います。
神の前で、私たちと共に歩んでいく信仰生活をしていきたいなと思います。
はい、ということで今日は、「災いだ」という6つの災いの言葉の内容でした。来週また続きを続けていきたいと思います。
愛する神様、
御言葉によって、私たちの内側に何があるのかを示してくださって、そして、本当に私たちに救いが必要であることを教えてくださっていることを感謝いたします。
すぐに自惚れ、そして自分が見えなくなって、神様が見えなくなって、人のことばかり気になってしまう愚かな私たちを、どうかお赦しください。
そして、どうか御言葉により頼み、あなたの御手の中で支えられながら、神の前で、神に向かって、神のために生きることができるよう、導いてくださるようにお願いいたします。
御言葉による励ましと導きに感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。