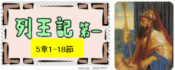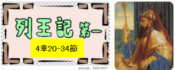マタイの福音書23章29~39節

まとめ
「絶望の中にあっても、神の愛は届く」
聖書には、私たちから見れば「もう希望がない」と思えるような人々に対しても、神の深い愛と忍耐が注がれていることが繰り返し語られています。
たとえば、イエス様が語られたイスラエルの民に対して、彼らは預言者を拒み、神の愛を何度も拒絶し続けてきました。にもかかわらず、神はなおも「深い深いスライムのような愛」で彼らを包み、待ち続けておられました。なんと理不尽で、身勝手な態度でしょうか。それでも、神の愛は決して止むことがありません。
イエス様が語られた、「お前たちの家は荒れ果てたまま、見捨てられる」という言葉は、厳しい裁きの宣言です。しかしそこには警告だけではなく、「愛を失ってしまった神の家が、私物化された現実への悲しみ」も込められています。
けれど、最後の節、「祝福あれ、主の御名によって来られる方に」とあなたがたが言うときが来るまで、あなたがたはわたしを見ることはない(マタイ23:39)という言葉には、私たちにとって大きな希望が含まれています。
この言葉は、イエス様がエルサレムにロバに乗って入場したとき、人々が喜び叫んだその時と同じ言葉です(マタイ21:9)。かつて賛美の声を上げた人々が、再びその賛美を口にする日が来る。―これは、頑なで反逆していた人々にも、回復と再会の時が来るという約束です。
私たちの周りにも、信じることから遠く感じる人、何度伝道しても心を閉ざし続ける人がいるかもしれません。ときに「もう無理では」と思ってしまうこともあります。でも、神のなさることに不可能はないのです。
ある兄弟が「もう望みがない」と思われていたにも関わらず、今は心で神を賛美する者へと変えられました。それは人の努力ではなく、神の奇跡です。
だからこそ、私たちにできることはただ一つ。諦めずに祈り、信じ、愛し続けることです。
「主の御名によって来られる方に、祝福あれ!」と、やがて多くの人が賛美する時が来ます。たとえ今は暗くても、その時を信じて希望を捨てずに歩みましょう。
筆耕
イエス様が立法学者、パリサイ人たちに関して「災いだ」「災いだ」と繰り返し非難をしている記事を、これまでずっと学んできました。全部で7つの「災いだ」という言葉が出てきますが、6つまでは前回学び、今日は最後の「災いだ」という言葉。そして、パリサイ人たちに対するイエス様の非難も、これが最後となります。ここでクライマックスに至る、そういう内容になると思います。
「災いだ」と訳されているギリシャ語の言葉ですが、「災いだ」という訳が本当にふさわしいのかどうか、なかなか難しいところです。昔の新改訳聖書では、ここは「忌々しいものだ」と訳されていたと思います。今の訳では「災いだ」となっていますね。
あるいはこの言葉、同じギリシャ語がマタイの11章21節では「ああ」という嘆きの言葉で訳されています。いつまでも悔い改めようとしないコラジン、ベツサイダという町に対するイエス様の嘆きの言葉です。
また、次の章、マタイ24章19節では「哀れです」という訳になっています。そこでは、「それらの日、身重の女たちと乳飲み子を持つ女たちは哀れです」と訳されており、これは最後の日、神様の厳しい裁きが下されたときに、本当に哀れなのはそうした女性たちだという意味で使われています。
つまり、この「災いだ」というギリシャ語の言葉には、実に多くの意味が含まれているのです。単に「災いだ」と訳すと、パリサイ人たちの邪悪さへの厳しい非難として聞こえるかもしれませんが、それだけでなく、イエス様の嘆きや、心からの哀れみの感情も込められているということです。とても訳しにくい、深い意味を持った言葉であることを覚えておきたいと思います。
イエス様がここで問題にしているのは、彼らの偽善の問題です。偽善というのは、外側はとても信仰深く見えるのに、内側は邪悪で、醜いもので満ちているという状態です。イエス様は、そうした彼らの姿を繰り返し指摘してきましたが、今日はその最後の指摘となります。
7番目の「災い」の内容は、どんな偽善かというと、まずイエス様は29節でこうおっしゃっています。
「災いだ、偽善の立法学者、パリサイ人たち。お前たちは預言者たちの墓を建て、義人たちの記念碑を飾って言う。『もし私たちが先祖の時代に生きていたなら、彼らと一緒に預言者たちの血を流すことはしなかっただろう』と。」
彼らの振る舞いは、預言者たちのお墓を建てたり、義人たちの記念碑を飾ったりして、先祖をとても敬っているように見える行為です。そして、自分たちも「もしあの時代にいたら、預言者を殺すようなことはしなかった」と証言しているわけです。
ところがイエス様は、31節でこうおっしゃいます。
「こうして自分たちが、預言者を殺した者たちの子孫であることを、自ら証言している。」
つまり、彼らの言葉そのものが、自分たちがその流れの中にある存在であることを示しているのです。イエス様は、その背後にある隠れた思いや動機を鋭く見抜いておられます。
彼らは「預言者の仲間だ」と言いますが、実際には預言者を殺してきた者たちの子孫なのです。見かけはとても信仰深そうに見えても、心の中は神に対する反逆に満ちている。イエス様は、その矛盾した姿をここで指摘しているのです。
そして、まさに彼らはこれからイエス様を殺そうとしているのです。その行為によって、自分たちが預言者たちを殺した者たちの子孫であることを、自ら証明しようとしているわけです。
これは今に始まったことではありません。昔からずっと、預言者たちは殺されてきました。その歴史の一連の流れの中に、彼らもいるのです。
さらにイエス様は、32節でこう言われました。
「お前たちは、自分の先祖の罪の升(ます)を満たすがよい。」
「ます」とは、はかり、つまり測るための器です。この言葉からわかるのは、罪の積み重ねが「ます」の中に蓄積されてきており、もうすぐいっぱいになる、そういう状態にあるということです。
その、もうちょっとでいっぱいになりそうな、その罪の蓄積をですね、彼らがこう満たすことができる、もうそういうところに来ているんだ、と。で、この「枡(ます)」がいっぱいになったら、どうなるんでしょうか?それは要するに、神の時が来るってことですね。そして、それはもう、厳しい裁きの時がやってくるということです。
そういうことが、ここで指摘されている。もう、罪の枡がどんどんどんどん溜まりに溜まって、もうちょっとでいっぱいになるという、そういうギリギリのところで、そこでまさに神の裁きが下されようという、そういう時が近づいているということですね。
そういう警告の言葉です。
そして、さらに33節。
「蛇よ、蝮(まむし)の子孫よ。お前たちはゲヘナの刑罰をどうして逃れることができるだろうか。」
これは非常に、イエス様の厳しい言葉だなと思いますね。まあ、「偽善の立法学者」というそういう言い方も厳しいですが、ここでは「蛇」と、例えられている。
蛇っていうのは、もうサタンの象徴です。悪魔の象徴ですね。その「蛇」と呼び、さらに「蝮の子孫よ」ということで、蛇にもいろいろありますけど、蝮というのは毒を持っています。
皆さん、教会の周りでも時々蛇が出ることがありますので、これからの季節、気をつけてください。マムシがいるかどうか分かりませんが、もしかしたらいるかもしれません。
噛まれたら非常に危ないですので、サンダルなどで歩かないように、気をつけないといけないかなと思います。
蝮っていうのは毒を持っていますね。非常に猛毒で、噛まれたら本当に危険です。
でも、まさにそういう存在であるということを指摘しています。
そしてここで、イエス様が指摘しているのは、もう彼らは神の裁きを逃れることができない、ということですよね。
もう、必ず神の裁きを受けなければいけないんだ、と。それくらいお前たちの罪は重いんだ、ということです。
そういうことが、ここで警告されている言葉だなと思います。
そして、34節に行くと、「だから、見よ」という言葉に繋がっていきます。
「だから、見よ」と。
今までの話が全部、今までの内容を受けた上で、「だから、見よ」と話が展開していくことが分かりますね。
偽善者としての生き方がずっと続いてきた。先祖代々、続いてきた。そういうことが全部続いてきた。その流れの中で、その生き方を彼らは、もうやっぱり変えることができないんだと思うんですよね。
ですから、「だから、見よ」。「注目しなさい」と。
そこでご指摘されていることは、結局これからもずっとそれは変わらないんだ、と。そういうことが続いていくんだ、という指摘が34節でされていると思います。
「だから、見よ。私は預言者、知者、律法学者を遣わす。だがお前たちは、そのうちのある者を殺し、十字架につけ、またある者を会堂で鞭打ち、町から町へと迫害して回る。」
これからも神様は、預言者、知者、律法学者を遣わすとおっしゃっていて、今までも遣わされてきたけれども、これからも遣わされる。
イエス様はまさに、これから処刑されて、十字架につけられて死んでしまうわけですけれども、その後も、ずっと続いていくんですよね。
『使徒の働き』を読んでも、そうですね。
ステパノが殉教しました。ステパノも、ユダヤ人たちから石を投げられて殉教したという話が続いてきます。ヤコブ、ヨハネの兄弟のヤコブも殉教しますね。
そして、ペテロもパウロも殉教したと言われています。十二弟子のほとんどは殉教したとも言われていますけれども、結局、同じなんですよね。
イエス様が遣わした預言者とか、知者とか、本当に大事な大事な働き人たちを、ユダヤ人たちは徹底的にやっつけてしまう。
それが、ずっとこれからも続いていく。イエス様もそうですし、その後も続いていくということなんですね。
そのことが、ここで語られている。
そして、それは35節。
「それは義人アベルの血から、神殿と祭壇の間でお前たちが殺したバラキアの子ザカリヤの血に至るまで、地上で流された正しい人の血がすべて、お前たちに降りかかるようになるためだ。」
ここを読むとですね、もうこれは『創世記』のカインとアベルの話から始まっているとわかります。義人アベルの血、これはカインによって殺されたんですよね。
何度も何度も繰り返されて、そして「ザカリヤの血」とされる人物。このザカリヤという人は、おそらく『第二歴代誌』24章20節に出てくる、祭司エホヤダの子ザカリヤではないかと言われています。
「ザカリヤ」という名は聖書の中に何人も出てきますので、どの人物か、いろんな議論があるようですが、『第二歴代誌』24章に出てくるザカリヤだと考えられています。
そこを読むとわかるのですが、この人もやはり、イスラエルの民の罪を指摘したことによって、殺されてしまう人物なんですね。
🔥 裁きと罪の蓄積
「罪のます」がもうすぐ満杯:これは旧約からの預言的イメージであり、神の忍耐が限界に達することを象徴します。これまでに送られた預言者たちを拒み、殺してきたイスラエルの歴史は、裁きの「時」の到来を早めています。
33節の「マムシの子ら」:これは単なる侮辱ではなく、彼らの霊的な状態、すなわち毒を持ち、人を害する存在であることの象徴。サタンとのつながりを示唆しています。
⚖️ 歴史に現れた裁き
AD70年のエルサレム陥落:イエスが警告した通り、ユダヤ戦争の結果としてエルサレムは破壊され、神殿も失われます。これは単なる政治的事件ではなく、霊的な裁きの完成として理解されています。
「お前たちにすべて降りかかる」(36節):それは単に一世代への怒りというより、長い歴史の中の頑なさへの報いです。
💔 神の深い愛と忍耐
37節の「めんどりとひな」:この比喩は非常に感動的です。神の愛は、子ら(イスラエル)を守りたいという深い母性的な情熱に満ちています。裁きが語られる文脈の中でも、これは「諦めない神」の姿を強く打ち出しています。
「望まなかった」:イエスは何度も呼びかけたが、それを拒否したのは人間側であるという明確な指摘。自由意志の問題がここにあります。
裁きの中にある愛
この章を通して見えてくるのは、「愛の神」がただ甘やかす存在ではないということです。真の愛は、悪を放置せず、罪をそのままにしません。しかし、その裁きは常に回復の希望を前提にしています。イエスの涙は、諦めではなく「悔い改めて戻ってきてほしい」という最後の呼びかけです。
🔥【裁き】神の家が「お前たちの家」に変わる
イエスは、かつて「私の家は祈りの家」と呼ばれた神殿を、ここで**「お前たちの家」**と呼んでいます。
これは、神の臨在が取り去られたこと、つまり神の祝福と栄光からの「見捨てられた」状態に陥ったことを象徴しています。
形だけの信仰、商業主義、権威の私物化によって、神殿はもはや神の栄光の場ではなくなったのです。
この警告は、まさに現代の教会や信仰者にも強く響くものです。教会が「自分たちの都合の家」となってしまえば、祝福が離れ、荒れ果てる――それは霊的な現実です。
💔【神の愛】なおも拒絶されながらも、諦めない愛
何度も預言者を送り、何度も拒まれても、神は決してすぐに見捨てることはしませんでした。めんどりとひなの比喩に込められたのは、どこまでも守りたい、集めたいという神の母性的な愛です。
それでも拒まれ続け、ついには神の臨在そのものが取り去られるという、悲しみのクライマックスが「お前たちの家は荒れ果てたまま見捨てられる」という言葉に表現されています。
ここには、単なる怒りではなく、嘆きと涙の裁きがあるのです。神は愛しているからこそ、裁かなければならない。これは親が子を訓練するような、愛からくる正義です。
🌈【希望】「祝福あれ、主の御名によって来られる方に」
39節は裁きの宣言で終わっているようで、実は回復の希望がこめられています。
「あなたがたが『祝福あれ…』と言う時が来るまで」=言い換えれば、その時がやがて来るということ。
最終的にイスラエルがイエスをメシアとして受け入れる時が来る――これは終末的希望の預言でもあります(参照:ローマ11章)。
これはただの希望ではなく、神の約束に基づいた希望です。人の不信仰にもかかわらず、神の計画は変わらず、最後には愛と回復が勝利するという福音の核心です。
💡私たちへの適用
これは教会にとっても信仰者一人ひとりにとっても重要な警告と励ましです:
教会が祈りの家として神との交わりを失わないように。
神の声を拒まず、預言的な警告を無視しないように。
今は見捨てられたように見える人々、国々、教会にも、回復の時が来るという希望を持つこと。
1. ❌人間の頑なさと罪の重さ
ユダヤ人のように、「もう絶対に無理では?」と思えるほどの反発や無関心、罪の中に生きている人たち。
私たちの家族や周囲にも、そういう「手の届かない」ように見える人が確かにいます。
2. 💝それでも絶えず愛する神
それでも神は**「祝福あれ、主の御名によって来られる方に」という賛美が彼らの口から出る日をあきらめずに待っておられる**。
これはイエス様がエルサレムに入場したときの賛美(マタイ21:9)と同じ言葉。つまり、かつての賛美が、未来の希望として再び現れるということ。
3. 🌈証の力 – 神は人を変える
けさお兄弟の例のように、「変わるとは思えなかった人」が心で神を賛美する人に変えられた。これは人間の努力ではなく、神の恵みによる奇跡。つまり、希望は失われていない。
4. 🙏私たちにできることは、祈り続けること
諦めず、伝え続け、祈り続けること。
**神のタイミングで「その時が来る」**と信じて、希望を持って待つこと。
🕊️祈り:
愛する天の父なる神様、あなたの深い憐れみと忍耐に感謝します。人の目には不可能に見える状況にも、あなたのご計画と奇跡があります。どうか私たちが、希望を失わずに祈り、あなたの愛を信じ続ける者でいられますように。家族や友人の救いのためにも、どうかあなたの時を信じて、今年も祈りを持って歩むことができますように導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。