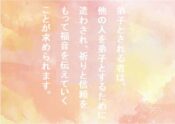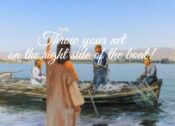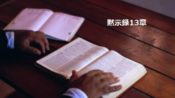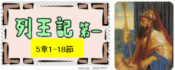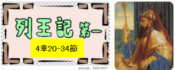マタイの福音書27章54~66節
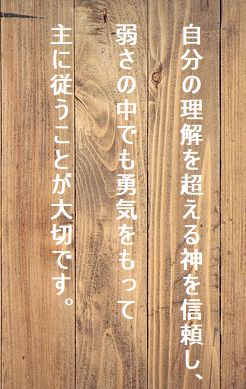
百人隊長や一緒にイエスを見張っていた者たちは、地震やいろいろな出来事を見て、非常に恐れて言った。「この方は本当に神の子であった。」また、そこには大勢の女たちがいて、遠くから見ていた。ガリラヤからイエスについて来て仕えていた人たちである。その中にはマグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼベダイの子たちの母がいた。夕方になり、アリマタヤ出身で金持ちの、ヨセフという名の人が来た。彼自身もイエスの弟子になっていた。この人がピラトのところに行って、イエスのからだの下げ渡しを願い出た。そこでピラトは渡すように命じた。ヨセフはからだを受け取ると、きれいな亜麻布に包み、岩を掘って造った自分の新しい墓に納めた。そして墓の入り口に大きな石を転がしておいて、立ち去った。マグダラのマリアともう一人のマリアはそこにいて、墓の方を向いて座っていた。明くる日、すなわち、備え日の翌日、祭司長たちとパリサイ人たちはピラトのところに集まって、こう言った。「閣下。人を惑わすあの男がまだ生きていたとき、『わたしは三日後によみがえる』と言っていたのを、私たちは思い出しました。ですから、三日目まで墓の番をするように命じてください。そうでないと弟子たちが来て、彼を盗み出し、『死人の中からよみがえった』と民に言うかもしれません。そうなると、この惑わしのほうが、前の惑わしよりもひどいものになります。」ピラトは彼らに言った。「番兵を出してやろう。行って、できるだけしっかりと番をするがよい。」そこで彼らは行って番兵たちとともに石に封印をし、墓の番をした。( マタイの福音書 27:54-66 SKY17 )
要約
私たちは時に、自分の理解や常識の範囲で神様を閉じ込めようとしがちです。しかし、復活や処女降誕のように人間の知恵を超えた神のわざこそが、神の偉大さを示しています。大切なのは、自分の理解に頼むのではなく、神に心を開き信頼することです。ヨセフのように弱さがあっても、神は私たちを用いて働かれます。私たちも勇気をもって主に従い、置かれた場所で主の働きに生きることが求められています。
筆耕
今日は、イエス様の十字架の場面が終わりまして、埋葬される場面、いわば「内装の場面」ですね。
それで、そのまま十字架の上で最後の息を引き取られて、そしてイエス様のご遺体を引き取って埋葬した人物は、アリマタヤのヨセフという人物だったんですけれども、その人について見る前に、ちょっと先週触れていないところがありましたので、そこから見たいと思います。
イエス様が十字架上で息を引き取られた時に、それを見て反応した方々が何人かいたということなんですね。
その一人は百人隊長でした。マタイ27章の24節から54節を見ますと、百人隊長や一緒にイエスを見張っていた者たちは、地震やいろいろな出来事を見て非常に恐れ、「この方は本当に神の子であった」と言った、と記されています。
イエス様が十字架上で息を引き取られたその場面を見た後に、天が暗くなる、地震が起こるといった現象もありました。そのような中で、ずっとイエス様を見ていた人たちが周りにいたわけです。
百人隊長、そして一緒にイエスを見張っていた者たち、つまりローマの兵隊たちだったと考えられます。彼らの中に「神に対する恐れ」というものが生じたのです。どれだけ意識できていたかは分かりませんけれども、何か恐れのようなものを感じた、ということですね。そして「この方は本当に神の子であった」という信仰告白に導かれた。そういう人たちが起こされていたんだ、ということなんです。
私たちも「恐れる」という感覚を忘れてしまうことがあります。けれども、地震や天変地異といった人間の力をはるかに超えた現象に触れる時、非常に恐ろしくなる感覚を抱くことがあります。それはとても大切なことではないでしょうか。人間が何でもできるかのように思っていても、その先に神がおられ、この神が天地万物のすべてを支配しておられるのだと感じる瞬間は、必ずあると思うのです。
イエス様を見て「この方は本当に神の子である」という信仰告白に導かれるなら、それは本当に幸いなことです。理屈ではなく、確信として「間違いなくこの方は神の子だ」と信じる、信仰とはそういうものだと思います。導かれた人々がいたというのは、なんと素晴らしいことではないでしょうか。今も各地でそのような人々が起こされているのだと思います。ですから、そういう方々がさらに起こされるように、私たちも祈っていく必要があるのです。
そして55節では、「大勢の女たちが見ていた」と書かれています。
そこには大勢の女たちがいて、遠くから見ていました。彼女たちはガリラヤからイエスについてきて、仕えていた人たちです。その中には、マグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼベダイの子たちの母もいたと記されています。
つまり、たくさんの女性たちが遠くから見守っていたのです。彼女たちはガリラヤからイエスについてきた人たちでした。ガリラヤで宣教されていたイエス様に従い、エルサレムまで約80キロの道を共にしてきたのです。本当に信頼し、イエス様に従っていた女性たちだったのでしょう。家族を置いて出てきたのかもしれませんし、それは大きな犠牲だったと思います。それでもなお、イエス様に従ったことは素晴らしいことです。
この女性たちは、その後の埋葬の場面にも登場します。そして復活の場面で大きな役割を果たすことになるのです。ですから、この記事は「女性たちがそこにいた」というだけでなく、次の神の御業に繋がっていく備えがすでに始まっている、ということを示しています。日常の小さな出来事のように見えても、神様の配置があり、御業のドラマへと繋がっていくのです。
そういう意味で、この箇所からも神様の導きや御業の素晴らしさを感じることができます。
このように、イエス様が亡くなられた時にはいくつかの反応があったことを確認した上で、次に埋葬の場面に入りたいと思います。
57節を見ますと、夕方になり、アリマタヤ出身で金持ちのヨセフという名の人が来ました。彼自身もイエスの弟子になっていたのです。ヨセフはイエス様の遺体を引き取って、埋葬したと記されています。
彼はどんな人だったのか。金持ちであり、イエスの弟子となっていた人です。12弟子ではありませんでしたが、イエスを信じて従っていた人物でした。マルコの福音書には「有力な議員で、自らも神の国を待ち望んでいた人」と記されています。また「正しい人であった」とも書かれています。さらにルカの福音書では、議員たちの計画や行動に同意していなかったことも示されています。
ユダヤ議会の多くの人々はイエス様を死刑にすることに必死でしたが、その中に同意しない人もいたのです。ヨセフはそういう人でした。ただ、彼はそれを公には言えなかったようです。ヨハネの福音書19章には、ユダヤ人を恐れて信仰を隠していたことが書かれています。
それでもイエス様が亡くなられた後、彼はピラトのもとに行き、イエス様の体の下げ渡しを願い出ました(58節)。
ピラトはヨセフの願いを聞き入れて、イエス様の体を引き渡すことを許しました。ヨセフはその体を引き取り、きれいな亜麻布に包んで、自分が岩を掘って作った新しい墓に納めました。そして、墓の入り口に大きな石を転がしておき、そこを去ったのです(マタイ27章59~60節)。
この場面は、イエス様が確かに死なれたことを証明するものでもあります。弟子たちは逃げ去ってしまいましたが、ここでアリマタヤのヨセフが立ち上がり、イエス様の体を引き取りました。今までユダヤ人を恐れて隠れた弟子であった彼が、この時には勇気をもって行動したのです。これは大きな信仰の証でした。
また、この時もう一人の人物が登場します。ヨハネの福音書によれば、かつて夜にイエス様のもとを訪れたニコデモが、没薬と沈香を混ぜた香料を持ってきて、イエス様を葬る準備をしました。彼ら二人が協力してイエス様を葬ったのです。
ここで注目すべきは、イエス様の死の直後に、公にはっきり信仰を表さなかった人々が前に出てきた、ということです。表立って仕えることができなかった人々が、最後の大切な場面で勇気を出し、役割を果たしました。神様は、こうした人々を用いられたのです。
そして、この埋葬の場面にも女性たちが登場します。マグダラのマリアともう一人のマリアが、墓の向かいに座って見ていた、と記されています(マタイ27章61節)。彼女たちは、イエス様の死から埋葬、そして後に復活の場面まで、ずっと見守り続ける証人となったのです。
このことから分かるのは、神様のご計画には「見守る者」も必要だということです。表立って行動する人だけでなく、静かに、しかし確かに主を見守る者が、神の御業を証しする存在となるのです。
そして、イエス様が墓に葬られたという事実は、復活の確かさを裏付ける重要な証拠となります。埋葬がはっきりと記録されているからこそ、「復活」という出来事が単なる噂や幻想ではなく、歴史的事実として受け止められるのです。
勝手にイエス様のご遺体を下ろすことはできませんでした。それはローマの権限の中で行われていることですので、必ずピラトの許可が必要だったのです。勝手にそういうことをしてはいけなかったのですね。
そこでヨセフはピラトのところに行き、下げ渡しを願い出ました。ピラトは渡すように命じました。ヨセフの話を聞いて「こんなに早く死んだのか」と驚いた、という記事も出ています。そして本当に死んだのかどうかを確認させました。その後で、間違いなく死んだと確認した上で、ヨセフに亡骸を渡すように指示した、という流れになっています。
マルコの福音書の記事を読むと、この下げ渡しを願い出た時に「彼は勇気を出してピラトのところに行った」と記されています。非常に勇気が必要だったのです。ただ行って許可をもらっただけではなく、勇気を振り絞って願い出たのです。ユダヤ議会の人々はイエス様を死刑にすることに必死でした。その中でヨセフがお願いに行けば、自分が弟子であることが知られてしまう、非常に恐ろしいことでした。
それはペテロが三度も「知らない」と言ってしまったことからも分かります。恐ろしくて仕方がなかったのです。もし願い出れば、「弟子だ」と白い目で見られ、評判も悪くなり、迫害を受ける危険もありました。本当に勇気が必要なことでした。けれども、彼はそこで勇気を出して一歩前に進み、その戦いに勝利して、イエス様のご遺体を引き取ったのです。
その後、59節に記されているように、ヨセフは体を受け取ると、きれいな亜麻布に包み、岩を掘って作った自分の新しい墓に納めました。そして墓の入り口に大きな石を転がして立ち去ったのです。彼はあらかじめ亜麻布を用意しており、それに包んでご遺体を整えました。墓も自分や家族のために用意していたものでしたが、それをイエス様に捧げたのです。
また、ヨハネの福音書には、かつて夜にイエス様を訪ねてきたニコデモが登場します。彼も再び現れて、多くの香料を持ってきました。そしてヨセフと共に、イエス様の亡骸に香料を塗り、丁寧に葬ったのです。
その後、61節を見ると、マグダラのマリアともう一人のマリアがそこにいて、墓の方を向いて座っていたと記されています。女性たちは十字架から墓まで移動し、埋葬の場面も確かに見届けていました。これが28章の復活の場面に繋がっていきます。
こうしてヨセフがご遺体を引き取り、埋葬したのは本当に大切なことでした。ヨセフは、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、四つの福音書すべてに登場します。しかし、そこにしか出てきません。つまり「イエス様を埋葬した人物」として記憶されているのです。埋葬がなければ復活に繋がらないので、この場面は十字架と復活を結ぶ大切な橋渡しの出来事でした。神様のご計画の中で用いられた人物、それがヨセフだったのです。
もし彼がピラトのもとに行って願い出なければ、イエス様の亡骸は放置されたかもしれません。弟子たちは逃げてしまっていましたし、女性たちは多くいましたが、埋葬をすることはできませんでした。墓もなく、力もなく、ただ見守るしかなかったでしょう。けれどもヨセフは、社会的地位を持ち、金持ちで墓を備え、議員としてピラトのもとに行ける立場にありました。そして彼は勇気を出してその時に行動したのです。
本当は弟子であるなら、イエス様の裁判に反対すべきでした。しかし信仰を表明できずに沈黙していた。それでも最後の時に、神様に用いられたのです。「今こそ自分が必要とされている」と信仰を与えられ、一歩踏み出しました。
さて、次の日、すなわち備えの日の翌日、祭司長たちとパリサイ人たちはピラトのところに集まって言いました。
「閣下、あの詐欺師が、生きていた時に『三日の後によみがえる』と言ったのを思い出しました。ですから三日目まで墓を確かめるようにしてください。弟子たちが来て盗み出し、『彼は死人の中からよみがえった』と民衆に言い出すかもしれません。そうなると、前よりもっとひどい欺きになります。」
ピラトは彼らに言いました。
「番兵を出してやるから、行ってできる限りの見張りをせよ。」
そこで彼らは出て行き、石に封印をして墓を確かなものにし、番兵を置いて見張りました。
この箇所は、イエス様が「三日目によみがえる」と語られていたことを、弟子たちよりも敵対していた祭司長やパリサイ人が思い出して行動している、というのが特徴的です。
弟子たちは悲しみと恐れで隠れていましたが、敵対者たちは「もし復活と噂されれば大変だ」と警戒し、番兵を立て、封印までしました。これは皮肉なことに、イエス様の復活の証拠をより明らかにする準備となりました。
なぜなら、弟子たちが盗んだのではなく、確かに神の御業として復活されたのだ、ということを示す背景となったからです。
ですから、とても臆病な、気の弱い人だったのかなというふうに思うんですけれども、でもその彼がね、やっぱりこの時に用いられた。そして勇気を振り絞って、一歩前に出て、本当に尊い神様のお働きをした。神様は、私たちのこともそういうふうにして用いてくださる方ではないかなというふうに思います。
私たちも臆病なんですね。実はね。もっと堂々と信仰をこのように表明しなくちゃいけないのかもしれないんですけれども、意外とそうでもない、そういう時も多いんだと思うんです。結構、臆病で弱くて、気が弱くて、本当に何もできないという弱い自分を意識していることが多いのかなというふうに思うんです。
でも、神様が用いられる方って、そういう人が多いんじゃないかなと思うんです。選ばれるというより、本当に弱い人、力のない人が選ばれて、そういう人を通して神様の働きがなされていく。普段はなかなかできないようなことでも、神様を見上げて「今がもしかしたらその時だ」と導かれる中で、勇気を振り絞って、私たちも一本、神様に用いていただける、そういうことがあるんじゃないかなと思います。
神様は、私たちを適材適所、いろんな形で用いられる方であるということですね。その点をぜひ覚えたいと思います。今、皆さんそれぞれ、どんな御心を持っておられるでしょうか。きっと御心があると思うんです。
それで私たちとしては、今の状況の中で、自分が置かれている場にいろんな制約や限界もあるんだと思います。しかし、そういう中にあっても、やっぱり主が私たちに委ねておられる務めや働きがあるのではないでしょうか。気づかされた時には、導いてくださることを信じて、一歩前に踏み出す。信仰によって応答していく。そういうことによって、神様の働きが素晴らしくなされていくのです。私たちは信仰を持って受け止める者でありたいと思います。
そしてその後ですね、次の展開になるんですけれども、また祭司長とパリサイ人たちが出てきます。「何だろう」と思って読んでいくと、62節、あくる日、すなわち備えの日の翌日、祭司長たちとパリサイ人たちがピラトのところに集まって、こう言いました。
「閣下、あの人を惑わす男が、生きていた時に『三日後によみがえる』と言っていたのを思い出しました。ですから三日目まで墓を見張るように命じてください。そうでないと弟子たちが来て彼を盗み出し、『死人の中からよみがえった』と民に言うかもしれません。そうなると、この惑わしは前よりももっとひどいものになります。」
彼らはまたピラトのところに押しかけ、そうお願いしたのです。要するに「イエス様が三日後によみがえると話していたのを聞いた。だから信じているわけではないけれど、弟子たちが盗んでいくかもしれないから、しっかり見張りを立ててください」とお願いに来たのです。
彼らはイエス様を死刑にすることが目的で必死でした。イエス様が十字架で死なれ、目的を達成したわけですが、安心したかというとそうでもなく、まだ不安でした。「もしかしたらよみがえるかもしれない。弟子たちが盗むかもしれない」と、まだ不安に取り憑かれている。いつまでたっても不安を解消できない人間の姿がここにあるのです。
「ことが果たされれば安心できるのか」と言えば、そうでもない。次の心配が出てくる。そしていつまでも心配から離れられない。まさに人間の姿ですね。
この不安を訴えた祭司長たちに対して、ピラトは言いました。
「番兵を出してやろう。行って、できる限りしっかりと見張るがよい。」
そこで彼らは出て行き、番兵たちと共に封印をして墓を固めました。つまり、リクエストを受けたピラトが「分かった」と兵を出し、見張りをさせただけでなく、石に封印までしたのです。もう絶対に盗まれないように、徹底的に対策を取ったわけです。
今日の話はそこで終わるんですが、私たちはこの後の展開を知っています。だからこそ分かるのです。この人間の努力が、いかに虚しいかということが。
来週のテーマ、復活の出来事において明らかになりますが、番兵を立てたり、封印をしたりする人間の働きが、実は神の御業を引き立てるための準備になっていたんです。
人間の努力や知恵や力を、はるかに超えて神様が御業をなされる。それが復活であり、その凄さがここで際立たされる。言い方を変えれば、人間の思惑すらも神様はご自身のご計画のために用いられる。ここはその引き立て役となる場面だったのだと思います。
私たちも時々、神様のことを自分の理解とか知恵とか、あるいは常識の中に閉じ込めて、自分の中で理解し、満足したいという要求を抱くことがあるんですね。
それで、時々聖書を読んでいても「これはちょっと分からないから」「理解できない」と片付けてしまったり、ある人は「復活なんか信じられない」とか、「処女降誕なんかありえない」とか、「再臨なんかないでしょう」とか、もう自分の人間の常識の範囲の中で聖書を理解しようとする人たちがいるんです。
でも、それは要するに自分が神様になっているのと同じだと思うんです。自分が絶対になっていて、自分の中にすべてを収めなければ理解できない、満足できない。そういう読み方、そういう神の理解の仕方は、結局自分が中心になっているんです。
しかし神様という方は、私たちの常識や理解や力や知恵をはるかに超えておられる。だからこそ神なんです。だからこそ、私たちはこの方を賛美できるんです。この方を信じることができるんです。
ですから、それくらい神様は素晴らしい方だということですね。それくらい復活というのは本当に希望なんだということを、この記事を通しても覚えることができるのではないかなと思います。
ぜひ、私たちの理解が「自分の頭の中に収めることで必死になって、それで終わってしまう」ということがないようにしたいですね。私たちの理解をはるかに超えた、あの素晴らしい方なんだということを覚えながら、謙遜な思いを持ちたいと思います。
自分で理解することや、自分で満足すること以上に、「教えてください」「示してください」と、真理に心を開いて、この方に信頼していくことが求められているのです。そのことをぜひ覚える者でありたいと思います。
今日はここまでにして、復活の場面に移りたいと思いますので、また期待して学びを進めていきたいと思います。
お祈りをいたします。
ヨセフが神様のご計画の中で用いられた場面を、共に学ぶことができました。私たちもヨセフのように、人目を恐れてしまったり、怖かったり、弱かったりする者であります。しかし、それでも私たちを通して神様の働きが進められていることを覚え、感謝いたします。
時に私たちも、勇気を出して前に出ることが必要かもしれません。どうぞその勇気をお与えください。そして主が導いてくださって、私たちの置かれたところで主の働きをし続けることができますように、どうか導いてください。
御言葉の学びに感謝します。この後の祈りの時も祝福してください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。