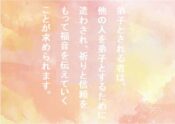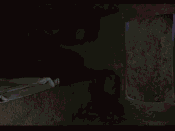マタイの福音書26章69~75節

要約
ペテロはもともと「シモン」という名で、イエスから「岩」という意味の「ペテロ」と呼ばれるようになりました。しかし、彼は初めから岩のように強い信仰者だったわけではなく、弱く不甲斐ない人物でした。特に、イエスを三度否認した出来事は、彼にとって人生最大の試練であり、信仰者として変わるために必要な経験でした。
このエピソードは、私たちにも重要な教訓を与えています。それは、自分の弱さや罪深さ、惨めさと向き合う時こそ、イエスの愛を深く知る機会だということです。しかし多くの場合、私たちは辛い時にこそ神の愛から離れ、自分を責めてしまいます。本当は、そのような時にこそイエスのまなざしと愛に気づき、信仰が深まるべきなのです。
ペテロの記事は、福音書すべてに記されており、それだけ重要な内容です。そして、イエスが十字架にかかる直前にこの出来事が挿入されていることに意味があります。つまり、イエスはこのような弱く罪深いペテロのために十字架にかかったということが、私たちに示されているのです。
私たちもまた、同じように弱く、失敗し、悩む存在ですが、そのような私たちをイエスは深く愛しておられます。そして、自分の力ではなくイエスの力により頼むことで、信仰者として成長することができます。パウロが語ったように、「弱いときにこそ強い」とは、神の恵みが私たちの弱さの中に働くからです。
この学びを通して、自分の弱さの中でこそ神の愛と力を体験し、信仰者として生かされ、導かれていく者となりたいと願います。
筆耕
皆さん、よくご存知のペテロが、「イエス様を知らない」と三回言ってしまう――ペテロの否認の場面です。
それで今日は、6章69節から始まるんですけれども、前回はイエス様が捕らえられて、カヤパ邸まで連れて行かれ、そこで裁判が始まるという、不当な裁判だったという話でした。
今、前回の箇所の中で、58節にこういう記事がありました。
「ペテロは遠くからイエスの後について、大祭司の家の中庭まで行った。そして中に入り、成り行きを見ようとした。下役たちと一緒に座った。」
と、そういう言葉が58節に記されてありました。
それで、イエス様が捕らえられたときに、たくさんの群衆たちがやってきて、弟子たちは一度みんな逃げたと思います。怖くなって、みんな逃げたと思うんです。
おそらくペテロも、一度は逃げたんだと思うんですけれども、でも気を取り戻して戻ってきたというんでしょうかね。イエス様の後をついて行ったということがわかります。
そして結局、イエス様は大祭司の家まで連れて行かれるんですけど、その後をペテロがついてきて、大祭司の家の中庭まで入っていき、そこにはたくさんの人たちがもう集まっていたわけですけれども、その中に入り、成り行きを見ようとした。そして下役たちと一緒に座った、と。そういうところまでペテロは戻ってきた、ということですね。
他の弟子たちはみんな逃げちゃったんだと思うんですけれども、ペテロだけは戻ってきたということで、「どうして戻ってきたのか」ということになるんですけども、それは、もしかしたらペテロの勇気だったかもしれないし、あとやっぱり、自分では一番弟子だと思っていたと思います。
ですから、イエス様が捕らえられてしまったわけだから、やっぱり最後までちゃんとイエス様について行きたい、という願いもあったことでしょう。
そしてもう一つ思い起こすことは、ペテロはイエス様に言っていたんですよね。
「たとえ皆がつまずいても、私はつまずきません。」
というふうに、もうすでにイエス様にお話をしていました。
「あなたと一緒なら、牢であろうと死であろうと、覚悟はできています。」
って、そういうふうにも話していたんですね。
その、イエス様が捕らえられる前の場面ですけれども、「最後までついてきます。もう覚悟はできています」と言ってしまった手前、このままやすやすと引き下がるわけにはいかなかった。それはそれで、とても勇気のある行動だったと思うんですね。
そしたら、一人の女の人が近づいてきたというのが69節ですね。
「ペテロは外の中庭に座っていた。すると召使いの女が一人、近づいてきて言った。『あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたね。』」
と尋ねられたことが出てきます。
ここに「召使いの女」と出てきますけれども、マルコの福音書の記事を見ると「大祭司の召使いの女」となって出てきますので、大祭司カヤパに仕えていたところの女中さんだったと思うんですが、その人が近づいてきて、
「あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたね」
と問いかけてきたということです。
ここには何も書いてないんですけれども、マルコの福音書に同じ記事が出てきます。その記事を見ると、彼女は彼を「じっと見つめていた」、という言葉がそこに書いてあるんですね。
なんとなく近づいてきて言った、というんじゃなくて、「じっと見つめた」んだそうです。
じっと見つめて、彼にこういう言葉を言ったということで、ペテロとしては、その視線を感じたと思いますよね。「じっと見つめられている……あんまり見つめてほしくないな」という感じだったかな、と思うんですけれども、そういうところで彼女がじーっと見て、「間違いない」と思ってこう近づいてきて、
「あなたも一緒にいましたね」
って問いかけてきたわけですね。
それに対してペテロはどう返答したかというと、最初の返答が次ですけれども、70節――
「ペテロは皆の前で否定し、『何を言っているのか、私には分からない』と言った。」
と、最初の返事は「何を言っているのか、私には分からない」という返事でしたね。
なんとなく、とぼけているような感じというんでしょうかね。
「あなた、何を言ってるんですか? 私には分かりません。」
という言い方ですが、分からないわけはないと思うんです。分かってるはずなんですけれども、でも、なんかそういうちょっと曖昧な返事というんでしょうか。
そして、なんとなく責任をその人に転嫁しているような言い方でもあるのかなって感じがしますけれどもね。
こうして最初の会話は終わるわけですが、その後、ペテロはどういう行動をしたでしょうか。
71節を見ると、
「そして、入口まで出て行くと」
ってあるんですね。
最初は庭の真ん中に彼はいたんですね。人々の中にいたんですけれども、その後「入口まで移動した」ということがここに書いてあるわけです。
これはですね、おそらく「顔が見られない位置に移動した」ということが考えられるんではないかなというふうに思います。
ルカの福音書の同じ記事を見ますと、
「その中央に焚き火が焚かれていた」
って書いてあるんですね。焚き火がそこに焚かれていた。夜です。この時は真っ暗です。そして寒かったと思います。
焚き火を焚いて、その周りにみんな集まっていたわけです。そこにペテロも入っていたんですね。
でも、焚き火の周りに集まると――キャンプファイヤーなんか経験したことある人は分かると思いますが――みんなの顔がよく見えるわけですよね。ですから、見られちゃったというわけですよね。
それで、顔を見られるとちょっと都合が悪いということで、おそらく焚き火から離れたということですね。入口のところまで行けば、もう真っ暗だったと思います。
ですから、闇の中に紛れるっていう意味もあったと思いますし、何かあった時はすぐ逃げられる場所、そういう場所であったかもしれません。
でも、ペテロにしてみると、そういうことで「顔が見られないような位置に退いた」ということだったと思うんですが、そしたらですね、違う女の人が近づいてきた、というのが次の展開かなと思います。
71節「そして入口まで出て行くと、別の召使いの女が彼を見て、そこにいる人たちに言った。『この人はナザレ人イエスと一緒にいました』」ということなんですね。
さっきの最初の召使いの女は、「あなたもガリラヤ人と一緒にいましたね」って問いかけだったんですね。クエスチョンだったんです。ペテロに向かって話している言葉ですね。
ところが、この2番目の召使いの女は、そこにいる人たちに言っているんですね。ペテロに聞こえるように言っているわけですけれども、ペテロ個人に向かって言っているのではなくて、周りの人たちに言いふらし始めた。そして、この人はナザレ人イエスと一緒にいた、と確信を持って言っているわけです。
ここで、状況が変わってきますよね。
自分にだけこっそり言われているうちは、まだ安心だったかもしれません。でも、それがみんなに言いふらされてしまっている。しかも、確信を持って言いふらされているということで、いよいよペテロの心配が募ってきたんだと思います。
では、ペテロは何て答えたかというと、
「誓って、そんな人は知らない」
と再び否定した、とあります。
ペテロは、さっきは「私には分かりません」とちょっととぼけたような言い方をしていましたけれど、ここに来るとはっきりと「私は知らない」と断定しています。しかも、「誓って」と言っている。
そして、73節に移動すると「しばらくすると」と書いてあります。
しばらくは何も変わらなかったんだと思います。「しばらくすると」って、どれくらいの時間かというと、ルカの福音書を見ると「それから1時間経ち」と出てくるんですね。ですから、1時間は何もなかったというか、ペテロはそこに踏ん張って留まっていたというか、粘っていた、そんな感じだったのかなと思います。
つまり、1時間そこにいたんですね。
そしたら、「立っていた人たちがペテロに近寄ってきて言った」とあります。
今度は、複数形になっていますね。もう1人じゃないんです。「人たち」、つまり何人かやってきたということですね。そしてこう言いました。
「確かに、あなたもあの人たちの仲間だ。言葉の訛りでわかる」
というふうに言われてしまいました。
「確かに」と言っていますから、もう確信を持って言ってきている。しかも複数で来て、あなたはイエスの仲間だと言い、さらに「言葉の訛りでわかる」と根拠まで示されています。
ペテロはガリラヤ地方の出身ですので、彼の話す言葉にはガリラヤ地方の訛りがあったということがわかるんですね。その訛りでバレてしまった。間違いなくイエス様と一緒にいた、と言われてしまった。これは本当に怖いことですよね。
そういうことで、もう完全にバレてしまったということになります。
そして、74節。
「すると、ペテロは『嘘なら呪われても良い』と言い始め、そんな人は知らないと言った」
ということで、もうこの否定の仕方は、これ以上ないくらいのはっきりとした否定ですよね。
「本当に知らない。嘘なら呪われてもいい」と言い、完全に否定している。
それくらい怖くなっているということですよね。そういう気持ちの表れだと思うんですけれども、完全に否定してしまったということになります。
そしたらその時に――
「するとすぐに、鶏が鳴いた」
という、そういう展開になったということが聖書で示されていることです。
ここに至るまでのペテロの「戦い」と言ったらいいでしょうか。内的な戦い、精神的な戦いについて、ちょっと振り返ってみたいと思います。
彼は戦っていたと思います。恐怖心と戦っていたと思いますね。
彼は頑張って、勇気を持って、本当にイエス様のすぐそばまで来た。それは大したものだなと思います。弟子たちがみんな逃げてしまっている中で、彼一人だけが戻ってきたというのは、素晴らしい、立派だなと思います。
でも、そういう彼の中にも、やはり恐怖心があるんですね。
最初は群衆の中に紛れ込んで様子を見ていたんですけれど、だんだん恐怖心が迫ってきた。いよいよ強くなってきた。
それをなんとか克服しよう、乗り越えようと彼は頑張っていた。でも、最後はもう頑張りきれなくて、結果的にはその恐怖心を処理できなかっただけでなく、自分の弱さをさらけ出す結果になってしまったということなんですね。
そして私たちは、この記事を読むときに、「これは全部、神様の支配と導きの中で起こっている出来事だ」ということを知ることができます。
なぜかというと、ペテロが3回目に「知らない」と言ったその時に、鶏が鳴いたんですね。もう、ありえないですよね。そのタイミングで鶏が鳴くなんて。偶然のようにしか見えないんです。でも、偶然じゃないですよね。やはり、それはそういうタイミングだったんです。
それを見るときに、「ああ、これも完全に神様の御手の中で起きている。神様の計画の中で起きていることなんだ」ということに、私たちは気づかされると思います。
ペテロの立場に立って考えると、困難が次々に押し寄せてくるように感じられていたと思います。
「なんでこんなに次々と人が来るんだ。本当にもうやめてくれ!」
って、言いたくなるくらいだったと思いますね。
でも、神様の側からこの場面を見ると、神様は明らかに、いろんな人々との出会いを通して、ペテロの弱さを次々に明らかにしようとしている。そういう神様の導きがある。神様の御手が、そのように働いているということに気づかされるんではないかと思うんですよね。
だんだん、迫っていくんですね。
ただなんとなく来ているように見えるんですけれども、やっぱり迫ってくる。そして、次から次に、その度合いがどんどん強くなっていくんですよね。
それに対してペテロの否定の度合いも、どんどん強くなっていきます。
だんだん、はっきりと否定するようになって、最後はもう「呪われてもいい」と――すごく強く、断定してしまう。
つまり、ペテロ自身の内側にある「弱さ」というものが、もうはっきりと現れていく。
そういう導きだったということが、今日の箇所を通して、神様の視点から見ると気づかされることではないかなというふうに思います。
私たちも、そういう経験をすることがあるんじゃないかなと思うんですね。
私たちの側から見ると、「なんでこう、次々に試練がやってくるんだ」「なんでこんなに困難ばかり続くんだ」「どうして神様はこんなことをされるんですか」と、思いたくなるようなことが時々あるんじゃないかなと思います。
「もうやめてほしい。なんでこんなに、次から次に困ったことが起きるのか……」と、悩んだり、苦しんだりすることが、時々あるような気がするんですね。
でも実は、神様の視点から見ると、その導きの中で、私たち自身の“生身の姿”が、よりはっきりと見えてくるんじゃないでしょうか。
私たちの弱さとか、脆さとか、頑なさとか、そういうものが、よりはっきりと見えてくる。――本当は、見たくないんですね、私たちは。そういうものをね。
でも、なんだか見せられていく。そこにも、神様の御手が働いている。そういうことを、私たちも経験することがあるんじゃないかな、というふうに思います。
でも、それって実は――ペテロにとっても大事な経験だったように、私たちにとっても、とっても大事な経験であるということですね。
最後、ペテロはその鶏の鳴き声を聞いて、どうしたでしょうか。
75節ですが、
「ペテロは、『鶏が鳴く前に、あなたは三度、私を知らないと言います』と言われた、イエスの言葉を思い出した。そして、外に出て行って、激しく泣いた。」
と、そういう最後になりました。
やっぱり、鶏の声を聞いたその時に、ペテロは思い出したんですね。イエス様がかつて言われた言葉を。
「鶏が鳴く前に、あなたは三度、私を知らないと言います。」
確かにイエス様、言っておられた。
その時、ペテロは「そんなことありません!」って言い張っていましたね。
「そんなことありません! 私は最後まで従って、ついて行きます!」と。
でも、この場面になって、その言葉を思い出した時に、本当に「ああ、イエス様は全部分かっておられた」と、気づかされたんですね。
そのことに気づいて、彼は外に出て行って、激しく泣いた。
――もう、崩れたんですね。その時に。陥落したと言っていいでしょうか。
それまで頑張っていたものが、全部崩されたんですね。そして、激しく泣いたという結果に至ったわけです。
涙を流しているんですけれども、この涙の意味――ペテロが流した涙の意味って、どういう涙だったのかなと思う時に、2つあったのではないかと思います。
1つは、やっぱり自分自身の情けなさから来る涙。
「自分ってこんなに惨めだったんだ。こんなに弱かったんだ。こんなに脆かったんだ。」
と、とことん自分の姿が見えてきたことによる涙ですよね。
もっと自分は強いと思っていた。もっと頑張れると思っていた。自分は結構、勇気があるんじゃないか。最後までイエス様に従っていきたい、と。そういう強気でずっといたんですよね。
ところが、それ全部、もう嘘だった。
自分の頑張りは、本当に儚い力だった。とことん分かった。
「本当の自分は、こんなに弱いのか。こんなに脆いのか。こんなに惨めだったのか。」
ってことが分かって、それで、激しく泣いた。
私たちにも、そういう時があるかもしれませんね。
自分の“みじめさ”のうちに涙するというか、本当に自分って情けないなと。
いつまで経っても、同じ失敗ばかり繰り返していて、全然成長しない……自分のことが分かれば分かるほど、惨めになる。
そういうことで涙するっていうことが、私たちにもあるんじゃないかなというふうに思います。
1つは、そういう意味があったと思います。
でも、もう一つ。この涙には、別の意味もあったと思うんですよね。
それは何かというと――
それは、本当にイエス様の深い愛を知らされたことによる涙、というんでしょうか。
「イエス様の愛って、ここまでとことん大きいのか。」
と、しみじみ分かるような、そういう経験だったんじゃないかなと思うんです。
「鶏が鳴く前に、3回、お前は私のこと知らないよ」って言われてた。
――イエス様は、ちゃんと分かっていた。ペテロのことを、全部分かっていた。
そんなに強くない。弱い。脆い。裏切る。――全部、分かっていたんですよね。
分かっていた上で、それでも全部、受け入れてくれていた。
そのことに気づかされて、イエス様の深い愛を知った。
――そういう意味での涙もあったんじゃないかなというふうに思います。
これはマタイやマルコには出てきませんが、ルカの福音書には出てきます。
ペテロが三回「知らない」と言った、その三度目に、「イエスは振り向く」と書いてあるんですね。
そして、そこで目が合う――そういう場面があるんです。
その眼差しを見た時に、鶏が鳴く。
その眼差しを見て、涙した、という面もあっただろうなというふうに思いますね。
イエス様の眼差しっていうのは、
「何やってんだ、お前!」
というような責めるような目ではなかったと思うし、
「お前は本当に情けないやつだな」
というような、見下すような目でもなかったと思います。
「全部分かってるよ、ペテロのこと。お前のこと、全部分かってる。」
――でも、全部分かった上で、
「お前のこと、愛してるんだよ。」
っていうね、そのイエス様の眼差しを見て、本当に感じて、泣いた。
涙した。
――そういう、2つの意味があったんじゃないかなというふうに思います。
これは本当に、ペテロにとって貴重な経験だったと思います。
絶対に、ペテロに必要な経験だったと思います。
それは、本当に「自分自身をよく知る」ために必要な経験だったと思うし、その中に、本当にイエス様の愛が深くあるんだ、ということを、深く知る経験だったと思います。
そしてまた、「変わる」ために、ものすごく大きな経験だっただろうなと思います。
ペテロは、元々の名前はシモンという名前なんですけれども、ペテロというのはあだ名です。イエス様からつけられたあだ名で、それは「岩」という意味なんですね。
でも、ペテロは全然岩でも何でもないんです。この時点では、本当に不甲斐ない、ふにゃふにゃした、そういう人物だったと思います。けれども、彼は変わるんですよ。この後、本当に岩のような信仰者に変わっていくんですね。その「岩」になるために、絶対に通らなくてはいけなかったのが、この経験だったということです。
ですから、これはペテロにとって本当に大きな、大きな、人生最大の経験だったと言っていいんじゃないかと思います。「私についてきなさい」と言われた時も、本当に大きな経験だったと思いますけれども、それにまさる大きな体験を、ペテロは与えられたんだろうなということを思います。
私たちが一つ教えられることとしては、私たちが自分の弱さ、惨めさ、罪深さを知って泣くという経験と、そこでイエス様と出会って、イエス様の大きな愛を深く知るという経験は、繋がっているということです。本来、一つの経験であるはずだということを、この記事から私たちは教えられるんじゃないかなと思うんですね。
ところが、この二つの経験は、私たちの中で多くの場合、離れてしまっているというか、別々の経験になっていることも、結構多いのかなと思うんです。
私たちがイエス様を感じる時って、どういう時かというと、何か良いことがあった時は感じるかもしれないですよね。病気が治るとか、手術がうまくいくとか、問題が解決するとか、受験に合格するとか、そういう良いことがあった時には、「自分は本当に神様に愛されている」と思ったりすることがあるかなと思うんです。それで、「こんなに愛されて感謝だ」「こんなに健康が守られて感謝だ」と、そう思うかもしれません。
でも、意外とですね、失敗した時、挫折した時、自分の惨めさと向き合って苦しんでいる時に、そういう経験をしているかというと、必ずしもそうではないということがあるのではないかと思うんですね。そういう時にこそ、本当にイエス様と出会って、イエス様の深い愛を体験しなくてはいけないのに、そういう時に限って、自分のこの世界の中に閉じこもってしまって、「もう自分は本当に惨めだ、自信がない、自分はダメだ」と、どんどんどんどん自分を責めていってしまう。そういう時こそ、イエス様のまなざしを感じなくちゃいけないのに、イエス様の深い愛を経験できるチャンスなのに、そういう時に限って、イエス様と出会えない、ということがあるんですよね。
それで、本当の神様の大きな愛に、なかなか気づかない、分からない。信仰がいつまでたっても表面的になってしまう、そういう信仰形態になりやすいということも、私たちは覚えたいなと思うんです。
本当に辛い時、自分が分かって辛い時って、本当に辛いんですよね。自分の惨めさとか、罪深さとか、「本当にダメだな」というのが分かった時の辛さって、本当に苦しい。でも、そこにイエス様がいてくださる、そこにイエス様のまなざしがあるということを知るということが、私たちの信仰の成長には本当に欠かせないことじゃないかと思うんですね。そういう時にこそ、イエス様をぜひ覚える者でありたいなというふうに思います。
この記事は、すべての福音書に出てくる記事なんです。これがとても大事な記事であるということが分かるんですね。そして、そこにやっぱり私たちの姿が表されているということなんだと思います。
また、このペテロの否認の記事は、イエス様が十字架につけられていく道をたどっていく、その過程の中に必ず出てくる記事なんですよね。今、イエス様がどのように十字架に向かっていかれたかという、そのプロセスをたどっていく中で、ふっと挿入されているのがこのペテロの記事なんですね。ちょっと不思議な感じがします。それまでずっとイエス様に焦点が当たっていて、イエス様の姿を私たちは追いかけてきたのに、なぜかこの場面だけペテロに焦点が当たって、ペテロにフォーカスが当たっている。
そういう繋がりを見ていく時に、「イエス様はまさにこのペテロのために十字架で死んでくださったんだな」ということが見えてくる。この、本当に惨めで、本当に罪深い、こんな弱い、情けないペテロのために、十字架にかかって死んでくださったということが、見えてくるんだと思うんですね。
それは、要するにイエス様の十字架って、こんな私たちのために、私のためにイエス様は十字架にかかってくださったんだ、ということが伝えられているんじゃないかなと思うんです。
やっぱり私たちは、この記事を通して自分自身の姿をそこに見るし、そして、そんな自分のためにイエス様が苦しんで、身代わりになって十字架にかかってくださった。でも、それくらい私たちのことを愛してくださったということを、教えられるんじゃないかなと思います。
そして、これがやっぱり私たちにとっても大事な経験なんですよね。私たちが本当に神様に信頼するために、自分の悟りに頼るのではなくて、自分の力にすがって生きていくのではなくて、本当にイエス様の力に頼って生きていくために、この経験が私たちにもやっぱり必要なんだと思います。そして、それによって私たちは変えられていくんだと思います。
ぜひ、私たちも、「自分が弱い時にこそ強い」というパウロの言葉がありますけれども、私たちが「弱い時にこそ強い」と言えるのは、それは神様の恵みが十分にあるからなんですね。そして、弱さのうちに神様の力が完全に働かれるから。それがこの理由になっているんですけれども、弱い時にこそ神様の愛が深く分かるし、そこに神様の力が豊かに現わされるということを、ぜひ体験しながら、私たちも本当にこの信仰に生かされていく、神様の愛に導かれていく者として成長していきたいなというふうに思います。
今日、学びましたことを感謝して、終わりたいと思います。
一言お祈りをいたします。
イエス様を三回「知らない」と言ってしまった場面から、丁寧に学ぶことができてありがとうございます。私たちも、自分の弱さ、惨めさ、そして本当になかなか成長していかない自分を責めたり、あるいは悩んだり苦しんだりすることがありますけれども、でも、そこにイエス様のまなざしが注がれていることを、そこにイエス様の愛のメッセージが述べられていることを覚え、感謝します。
どうぞその時に、あなたの愛を思い起こすことができるように、あなたに信頼することができるように、そして、あなたの愛に導かれて歩んでいけるように、私たちにもペテロのような体験と、そして成長を与えてくださるようにお願いいたします。
御言葉の学びに感謝し、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。