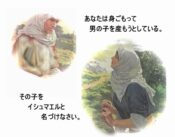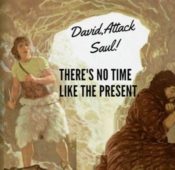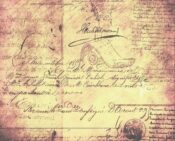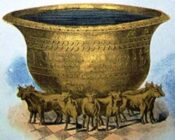第一列王記2章1~25節
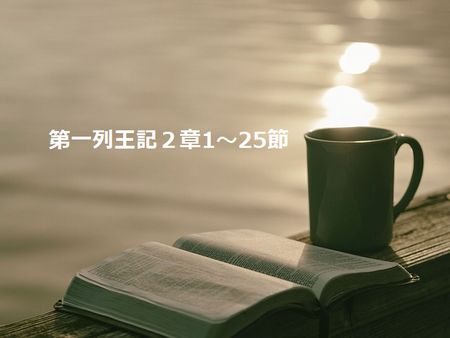
要約
ダビデの遺言
ダビデは死期が近づいたとき、息子ソロモンに「強く、男らしくあれ」と静かに、神の律法を守り、主の道を歩むように励みます。
ソロモンの徴兵とアドニヤの処刑
ダビデの死後、ソロモンが王位に就きます。 しかし、アドニヤが王位を狙っていた過去があり、ソロモンはその逆逆の可能性を警戒していました。 アドニヤはソロモンの母バテ・シェバに「アビシャグを」妻にしたい」と願い出ますが、これは王位を狙う意図と受け止められ、ソロモンは「アドニヤがこのようにして自分の命を知らなかったら、神が私を罰せられるように」と誓い、アドニヤを処刑させます。
要約
この部分は、ダビデの最終的な宣言と、ソロモンが王位を確立するために反逆の芽を摘む様子が描かれています。ダビデは神への忠実を強調し、ソロモンは王権の安定のために厳しい判断を下します。
筆耕
今日の箇所は、大きく二つの場面に分けられると思います。
一つは、ダビデがもう最後の時ですね。ダビデがソロモンに遺言を言い残している場面です。そして、彼が召されていく最後の場面です。
もう一つは──また出てきました──アドニヤが出てきましたけれども、このアドニヤが裁かれるという、そういう場面かなと思います。
それで一節ですね。「ダビデの死ぬ日が近づいた時」という言葉から始まります。いよいよダビデの最後の時が近づいてきたのだな、ということが分かります。
そしてその時、彼は何をしたか。彼は息子のソロモンに次のように命じました。すなわち、若いソロモンを呼び出して、遺言を残した、最後の言葉を伝えた、ということが分かります。
「私は世のすべての人が行く道を行こうとしている」──この言葉からも、ああもう死が近づいているのだな、ということが分かります。
そしてその時、ソロモンに残した言葉が、「まず、あなたは強く、男らしくありなさい」というものでした。
「強くあれ、男らしくあれ。」
その具体的な内容が、次の三節の言葉であると考えられます。
「あなたの神、主への務めを守り、モーセの律法の書に書かれているとおりに、主の掟と命令と定めと諭しを守って、主の道に歩みなさい。あなたが何をしても、どこに向かっても栄えるためだ。」
ということですね。
この世では、「強くあれ」「男らしくあれ」と言われると、なんとなく「威張りなさい」とか「力を誇示しなさい」というようなイメージに取られることが多いかもしれません。
しかし聖書で言う「強くあれ、男らしくあれ」という言葉の内容は、「主への務めを守りなさい」「律法に書かれているとおり、主の掟と命令と定めと諭しを守りなさい」「主の道に従いなさい」ということなのです。
これが聖書で教えているところの、真の強さ・男らしさということになるのだと思います。
それはヨシュアの時も同じでしたね。ヨシュアがリーダーになる時、神様は彼にもこう命じられました。「強くあれ、大しくあれ」と。
ヨシュア記の一章七節にはこうあります。
「ただ強くあれ、大しくあれ。それは、わたしのしもべモーセがあなたに命じた律法のすべてを守り行うためである。」
ヨシュアにも「強くあれ、大しくあれ」と命じられた後で、「それは神の言葉を守り行うためだ」と示されているわけです。つまり、神の言葉を守り行うことこそが、真の強さであり、大しさなのだということですね。
そのようにして神様の御言葉に聞き従いなさい、というのがこの言葉の意味です。
信仰を持って歩みなさい──そういう励ましの言葉であると言えます。
そうすると、どうなるでしょうか。
「あなたが何をしても、どこへ向かっても栄えるためである」と書かれています。
それは、ソロモンの人生が祝福につながっていく、ということです。
この「栄える」というのは、この世で言う繁栄や成功ということ以上に、神様からの祝福を豊かにいただく、ということです。
神様との関係の中における祝福がまず約束されているのです。
そしてそれだけではありません。
四節にはこうあります。
「そうすれば、主は私についてお告げになった約束を果たしてくださるだろう。すなわち、もしあなたの息子たちが彼らの道を守り、心を尽くし、命を尽くして誠実に私の前に歩むなら、あなたにはイスラエルの王座から人が絶えることはない。」
かつて神様はダビデにこのような約束をしてくださいました。
もしダビデの息子たちが本当に心を尽くして神に仕えるなら、イスラエルの王座から人が絶えることはない──そのような約束です。
つまり、ソロモンの人生が祝福されるだけでなく、イスラエルの王座そのものが祝福され、国全体が祝福される。
そしてそのことを通して、神様のご計画が着実に進展していく──そういう祝福につながっていくのです。
そういうことが「約束」である、ということが分かります。
本当にこの時は、ダビデからソロモンへと引き継ぎがなされている、大切な時だったと思います。
聖書を読んでいると、「引き継ぎの時」「大事な時」というのが時々ありますね。
モーセからヨシュアへ、ダビデからソロモンへ、エリヤからエリシャへ、そしてイエス様から弟子たちへ、さらにパウロから──いろいろあります。
どの引き継ぎの場面を見ても、本当に大事な時であることが分かります。
そしてどの箇所を見ても、やはり次に引き継ぐ人たちの信仰が問われている、ということが分かります。
「本当に神様に従っていきなさい。」
その信仰がしっかり引き継がれていくことによって、その人自身の人生も祝福され、
それだけではなく、神様のご計画そのものが正しく引き継がれていくのです。
聖書全体を通して見ても、神様のご計画が人から人へと受け継がれていく様子が示されている、そういうことを確認できるのではないでしょうか。
私たちも、いつか人生の終わりの時が来ますね。
その時に、どんな言葉を残すのか、どんなものを残していけるのか──。
財産を残すとか、家を残すとか、いろいろあると思いますが、
それ以上に「信仰を残すこと」ができたら幸いだなと思います。
そして、次の世代の方々に「本当に神様に従っていってください」と伝えたいですね。
そうすれば必ず祝福されますよ、という確信をもって、
そのような言葉を残して人生を終えることができたなら、本当に幸いだと思います。
そのことによって、神様の祝福が引き継がれていく──
そのようなことを覚えながら、与えられた人生を最後まで全うする者でありたいと思います。
さて、この箇所では三人の人物、そしてそれに関係する人々に対して「ふさわしく対処しなさい」ということが命じられています。
そのような内容になっています。
まず最初に出てくるのはヨアブです。
ヨアブはもともとダビデの家来でした。
以前、一章で学びましたが、最後の場面ではダビデを見限り、アドニヤについた人です。
長い間ダビデに仕えてきた人物ではありますが、このヨアブについてダビデは六節の最後でこう命じています。
「彼の白髪の頭を安らかに陰府(よみ)に下らせてはならない。」
これは、「彼をそのままにしてはならない。正しく裁きを行いなさい」という意味の言葉です。
つまり、ヨアブは裁かれなければならない、ということですね。
では、なぜこのようなことを言っているのか。その理由が五節に書かれています。
「また、あなたは、ツェルヤの子ヨアブが私にしたこと──すなわち、彼がイスラエルの二人の軍の長、ネルの子アブネルとエテルの子アマサにしたこと──を知っている。ヨアブは彼らを虐殺し、平和な時に戦いの血を流し、自分の腰の帯と足の靴に戦いの血をつけたのだから。」
この五節を読むと、「過去にこういうことがあったのだな」ということに気づかされます。
本来であればサムエル記の流れの中で読むとよく分かるのですが、ここに書かれているのはサムエル記下に出てくる出来事です。
ここで出てくる「ネル」という人は、ダビデの前の王であるサウルのいとこにあたる人物だと言われています。
サウルの軍の司令官でありましたが、ダビデとサウルは当時対立していました。
そのアブネルという人は、第二サムエル記三章に出てきますが、
彼はダビデと契約を結び、協力しようとした人物でした。
ところが、ヨアブはダビデの許可も得ずに、勝手にアブネルを殺してしまう──
そういう事件が起こったのです。これが第二サムエル記三章に記されている出来事です。
また、アマサという人も登場します。
この人は第二サムエル記二十章に出てくる人物で、ダビデの親戚にあたる人です。
アブシャロムの反乱が終わり、アブシャロムが死んだ後、ダビデはヨアブに代えてアマサを軍の長としました。
このようにして見ると、ヨアブは過去に多くの血を流し、
平和の時にも人を殺めた罪を持っていたことがわかります。
だからこそ、ダビデはソロモンに対して「正しく裁きを行いなさい」と命じたのです。
さて、「アマサ」という人がいますが、この人もまた、ヨアブに殺された人物です。
ヨアブはアマサに挨拶をして、非常に親しげに振る舞うふりをしながら、その腹を刃物で突き刺して殺してしまった──そういう事件が、第二サムエル記二十章に出てきます。
つまり、ヨアブはそういう人だったのです。
ダビデの許可も得ずに、勝手に人を殺してしまう。
そういう暴力的で残忍な一面を持っていた人物でした。
この二人の人、アブネルとアマサが殺されましたが、五節を見ると「ヨアブが私にしたこと」と書かれています。
ダビデ自身が直接殺されたわけではありませんが、彼にとっては自分に対してなされたのと同じほどの痛みだったのだと思います。
つまり、「ダビデに対してしたこと」と同じ意味で語っているのですね。
このように、ヨアブには過去にそうした罪がありました。
しかも、彼が二人を殺したのは“平和な時”だったと書かれています。
戦いの最中ではなく、平和な時にそのような卑劣な行為をしたのです。
だからこそ、その罪は正しく裁かれなければならない。
そのため、ダビデはソロモンに対して「ヨアブに裁きを下しなさい」と遺言として言い残した、というのがこの箇所の内容です。
次に七節に出てくるのは、バルジライの子たちです。
そこにはこう書かれています。
「バルジライの子たちには恵みを施してやり、彼らをあなたの食卓に連ならせなさい。
彼らは、私があなたの兄弟アブサロムの前から逃げた時、私のもとに来てくれたのだから。」
このことも第二サムエル記十七章に出てきます。
ダビデが息子アブサロムに責められ、命の危険を感じてエルサレムから逃げていく場面ですね。
その時、何の準備もできずに逃げたため、食べる物もなく、空腹と渇きに苦しんでいました。
そんな時に、バルジライはたくさんの食物を持って来て、ダビデを助けてくれたのです。
その出来事が十七章の二十八〜二十九節に記されています。
そこには、こう書かれています。
「彼らは小麦、大麦、小麦粉、炒り麦、そら豆、レンズ豆、炒り豆、はちみつ、バター、羊、牛乳などを、ダビデと共にいた民の食料として持ってきた。彼らは『民は荒野で飢えており、疲れ、渇いています』と言ったからである。」
──このように、まるでごちそうのような食物のリストが書かれています。
非常に興味深い記事ですね。
ダビデは本当に嬉しかったと思います。
苦しく、飢え、渇き、疲れ切っていた時に、多くの食物を携えて助けてくれた──その恵みを決して忘れなかったのです。
そこで、彼はソロモンに「バルジライの子たちに恵みを施してやりなさい」と命じました。
もしかしたらバルジライ本人はすでに亡くなっていたのかもしれません。
しかし、その子どもたちにまで恵みを施してあげなさい、と遺言に残しているのです。
これが、この場面で語られている内容です。
そして次に登場するのが、バフリム出身のベニヤミン人、ゲラの子シムイという人です。
九節の最後で、ダビデはこう言っています。
「あなたは知恵のある人だから、どうすれば彼の白髪の頭を血に染めて陰府(よみ)に下らせることができるか、わかるだろう。」
これも、先ほどのヨアブの件と同じで、「きちんと裁きを行いなさい」という意味の言葉です。
このシムイという人は、ダビデがアブサロムに攻められて劣勢になり、王として追われていた時に登場します。
彼はサウル家の出身でしたが、逃げるダビデを呪い、罵り、石を投げてバカにした人物です。
この出来事は第二サムエル記十六章に出てきます。
しかし、のちに形勢が変わり、ダビデが再び王として戻ってくると──
このシムイは態度をコロッと変えるのです。
それで、少し反省したような雰囲気もあったのですけれども、
やはりダビデはその時のことを覚えていました。
自分が生きている間には裁きを下さなかったけれども、
ソロモンが王になった時には、きちんと対処しなさい──
そのように命じたのです。
これはやはり、ソロモンの王位がしっかりと安定し、確立されるための、
一つの配慮であり、準備であったと考えられます。
そしてこの段落の最後の言葉が、十二節にあります。
「ソロモンは父ダビデの王座につき、その王位は確立した。」
この一文が結論です。
つまり、この段落全体は「ソロモンの王位が確立した」という結末を示すために、
そこに至るまでの準備や経過を描いているのです。
ですから、ダビデは決して個人的な恨みを晴らすためにソロモンに命じたのではなく、
ソロモンの王位が本当に安定したものとなるように、
不安な要素を取り除き、また良いことについてはきちんと報いを与える、
そのような王としての正しい判断を促すために語ったのだと思われます。
つまり、それは感情的なものではなく、
「王国が健全に受け継がれるための整理」であった、ということです。
ダビデは、自分が死に、ソロモンの時代がやってくるという、
その大切な節目の時に、これまでの出来事を整理・生産したのだと思います。
ダビデの人生には、長い年月の中で本当に多くの出来事がありました。
良いこともあれば、悪いこともたくさんあり、
人との関係においても非常に複雑なことが多かったのです。
自分ではすべてを解決できなかった、ということもあったでしょう。
しかし、それをそのまま引き延ばすのではなく、
世代が変わるこの節目の時に、きちんと整理し、
解決しておくべきだと判断したのだと思われます。
それが、ダビデの最後の知恵であり、
神の前に誠実であろうとする姿勢であったと言えるでしょう。
そして、自分の代では解決できなかったこともあるけれども、
ちゃんとそれを引き継いで、ソロモンの代になって解決してほしい──
それは、一つのダビデの気持ちの表れだったと考えられるのではないかと思います。
歴史を学んでいると、本当にいろいろな先輩たちの「信仰の遺産」というものがたくさんあって、
私たちは確かにそれを引き継いでいるのだということを感じます。
「あの時、あの方々が戦ってくれたおかげで、
今、私たちは安心して聖書を読むことができる」──
そういうことが本当に多くありますね。
先人たちの信仰の戦いと努力があったおかげで、
私たちは今、このような恵みを受けている。
そういう事実がたくさんあります。
しかしその一方で、先の時代にはなかなか解決されなかった課題もあるんですね。
実は、それらの課題は完全に解決できなかったけれども、
今の時代に引き継がれていて、
私たちが誠意をもって取り組むようにと、
まるで「宿題」のように残されているものもあります。
そうした意味で、神様の働きというのは、
このように継承されていく面が現実的にあるのだと思います。
ですから、私たち自身も同じです。
一生懸命に生き、懸命に頑張っても、
自分の世代では解決できない問題が残されることがあります。
それは本当に残念に思うかもしれませんが、
次の世代の人たちにぜひ取り組んでほしい、
そう願うようなこともありますね。
実際、ソロモンに対してダビデはこう語っています。
六節で、「あなたは自分の知恵に従って行動しなさい」と言い、
さらに九節では、「あなたは知恵の人だから」と、
「知恵」という言葉を用いて語っています。
つまり、残された課題に対処していく上で、
「知恵をもって判断しなさい」ということを強調しているのです。
それで、3章に入っていくと、ソロモンが神様から「何か欲しいものを求めなさい」と言われる場面があるんですね。
そのときソロモンは何を求めたかというと、「私に知恵をください」と願った──あの有名な話が3章に出てきます。
でも、その前に、実はこういうやり取りがあったのだということが分かるんです。
「知恵をもって判断しなさい」と言われても、ソロモンはまだ若く、経験もなく、本当に心細かったのではないかと思います。
いろいろな課題を担わされ、王としての判断が求められる中で、迷うことも多かったでしょう。
だからこそ、ソロモンは「知恵が必要だ」と痛感して、神様に「知恵をください」と求めたのだと思います。
この流れが、3章の記事へとつながっていく。
そういう展開が見えてくるのではないでしょうか。
ここまでが一つの場面です。
そして後半では、アドニアが再び登場します。
アドニアは、かつてダビデの後に自分が王になろうという野望を抱き、一度は王になりかけた人物でした。
けれども、ソロモンが正式に王となったために退けられた──そんな経緯が1章に書かれていましたね。
ここでも、アドニアが再び登場します。
13節を見ると、あるときハゲトの子アドニアがソロモンの母バテシバのところにやって来た、とあります。
バテシバは、「平和なことで来たのですか?」と尋ねます。
すると、アドニアは「平和なことです」と答えました。
バテシバとしては、少し不安を覚えたのではないでしょうか。
無理もありません。
この人はかつてソロモンを差し置いて、自分が王になろうとした人物ですから、
「また何か企んでいるのではないか」と、心配になったと思います。
しかしアドニアは、「平和なことです」と答えたうえで、「お話ししたいことがあります」と言いました。
そして彼には、一つの願いがあったんですね。
その願いが出てくるのが17節です。
彼はこう言いました。
「どうかソロモン王に頼んでください。
あなたからのお願いなら断らないでしょうから、
アビシャグを私の妻として与えてくださるようにお願いしてください。」
──このアビシャグという女性は、ダビデが年老いたときに、王を励まし世話をするために仕えた美しい若い女性で、
最初の章にも登場しましたね。
アドニアはその女性を自分の妻にしたい、と願ったわけです。
それでバテシバはどう答えたかというと、
「いいでしょう。私から王にお話しします」と承諾してしまいました。
それが、のちにソロモンの耳に入り、
ソロモンはそれを非常に危険なことだと判断し、
結局、アドニアは処罰されることになります。
では、なぜバテシバはこのとき「いいでしょう」と言ってしまったのか。
──この点は少し考えさせられる部分です。
その理由の一つとして考えられるのは、
アドニアの言葉そのものに、影響力があったのではないかということです。
14節から始まるアドニアの話の中で、
15節にこういう言葉があります。
「ご存じのように、王位は私のものでしたし、
イスラエルは皆、私が王になるものと期待していました。
それなのに、王位は転じて私の弟のものとなりました。
主によって彼のものとなったからです。」
──この言葉を聞いたバテシバは、きっと少し心を動かされたのではないかと思います。
「イスラエルは皆、私が王になるのを期待していました。」──本当かな?と、ちょっと思いますけどもね。
少し大げさなんじゃないかな、という気もします。
むしろ、人々はソロモンが王になることを期待していたんじゃないか、そんなふうにも感じます。
でも、アドニアはそういう言い方をしているんですね。
そして、「しかし王位は転じて、私の弟のものとなりました。主によって彼のものとなったからです。」
──そう言っている。
この言葉を聞くと、「ああ、そういう報告をしているんだな」と感じるかもしれませんが、
実際にはどんな口調で言ったのか、少し想像してみると、
ここで彼が言っていることは、「自分は被害者なんだ」ということを強調しているようにも思えるんです。
彼は、すべてを失ってしまい、もしかしたら非常に惨めな生活をしていたのかもしれません。
そして、あの女性──アビシャグも、かつてはダビデに仕えていましたが、
ダビデが亡くなったことで一人になり、身寄りのない状況にあったとも考えられます。
そうすれば、「お互い寂しい者同士だし、一緒になってもいいんじゃないか」という、
そんな発想がアドニアの中にあったのかもしれません。
お互いに恵まれない境遇にある──
そのことをバテシバに少し伝えることで、彼女の感情に訴えた。
そんな面があったのではないかと感じるんですね。
バテシバとしては、「何かまた企んでいるんじゃないか」と不安もあったでしょう。
けれども話を聞くと、「なんだ、そんなことか」と思ってしまった。
──少し変な言い方かもしれませんが、
「そんな程度のことなのか」と、安心してしまったような面もあったのかもしれません。
つまり、アドニアは少しバテシバの心をくすぐるような言い方をして、
うまく取り入ろうとした、あるいはそそのかした、ということですね。
そして、「バテシバを通して頼めば、ソロモンに言えば必ず通る」と分かっていた。
つまり、自分の願いを叶えるための一つの企みだったとも考えられるわけです。
その願いを聞いたバテシバは、ソロモンのもとに行って伝えます。
20節です。
彼女は言いました。
「あなたに一つの小さなお願いがあります。どうか断らないでください。」
ソロモンは答えました。
「母上、その願い事を聞かせてください。断ることはしません。」
そこで彼女は言いました。
「シュネム人の女アビシャグを、あなたの兄アドニアに妻として与えてやってください。」
──おそらく、「彼も少しかわいそうだから、ぜひこの女性を与えてあげてほしい」というような気持ちだったのかもしれません。
しかし、ソロモンは母に答えます。
「なぜアドニアのために、シュネム人のアビシャグを願うのですか?
彼は私の兄ですから、彼のためには王位を願った方がよかったのではありませんか?
彼のためにも、祭司エブヤタルやヨアブの子のためにも、です。」
──これは少し皮肉めいた言い方ですね。
「そんなものを願うくらいなら、いっそ王位そのものを願えばよかったんじゃないですか」と。
つまり、「彼の本当の願いはそこにあったんじゃないですか」という、そんなニュアンスを感じます。
そして最終的に、ソロモンはこう宣言します。
「アドニアがこのようなことを言っても、なお自分の命を失わなかったなら、
神がこの私を幾重にも罰せられるように。」
──ここでソロモンは、ついにアドニアに対する裁きを決断するのです。
主は生きておられる。
主は、私の父ダビデの王座につかせ、私を固く立て、約束どおり私のために家を建ててくださった。
そのアドニアは、今日、殺されなければならない──。
彼は、女(アビシャグ)を与えてほしいと願い出たのですが、
その願いは退けられ、結果的に、のちに彼を殺害する、つまり処分するという結論に至った。
──それが今日のお話の中心になります。
非常に危険な動きだと、ソロモンは察したのだろうと思いますね。
やはりアドニアの中には、まだ野心が残っていた。
王に近づくことによって、なんとかその座に再び近づこうとする、
つまり「王位を狙う」という企みがあったのではないか──。
ソロモンには、そうした警戒心もあったのだと思います。
しかし、何よりも言えることは、彼が悔い改めていなかったということです。
前回の第一章の最後で、彼は命乞いをしましたね。
祭壇の角をつかみ、命を助けてほしいと懇願しました。
あの時、外から見れば、悔い改めたようにも見えました。
けれども、ソロモンは52節でこう言いました。
「彼が立派な人物であれば、その髪の毛一本も地に落ちることはない。
しかし、彼のうちに悪が見つかれば、彼は死ななければならない。」
──つまり、その時点では判断を保留し、裁きを下さなかったんです。
それは、最終的なさばきを神様に委ねた、ということだったと思います。
ところがこの段階に来て、彼はやはり悔い改めていなかった。
彼の中に悪が残っていることが、はっきりと分かりました。
その時点でソロモンは、ついに彼にさばきを下した──。
そういう経過だったと言えるでしょう。
そしてここから、私たちが学べることがあります。
罪を残したまま、悔い改めを拒み続けることが、
いかに恐ろしい結果をもたらすか──ということです。
本当に、悔い改めて罪をきちんと処分していただくことが大事なのに、
それを拒んで、とりあえず「命乞い」だけをしても、
その罪が心の中に残っているなら、
最終的には神様のさばきを受けることになる。
私たちはそのことを、心に留めておく必要があると思います。
今、私たちはこの「王位の移り変わり」の箇所を学んでいますが、
それは必ずしもスムーズに行われたわけではありません。
そこには人間の野望や欲望、思惑などが複雑に絡み合っていました。
それが現実だったのです。
しかし、その中にあっても、信仰的な判断が求められ、
そのことを通して神様の計画が進んでいった。
──そこに私たちは神の導きを見るのです。
人間の心は複雑で、なかなか簡単にはいきません。
「本当に手ごわいな」と思うこともあります。
表面的にはスムーズに見えても、
内側ではいろんな感情や思惑が絡み合っていることがある。
そんな難しい現実の中でこそ、
本当に正しい判断が求められるんですね。
だからこそ、私たちは祈りをもって、
知恵を用いて判断できるように求めていく必要があります。
ソロモンのように、神に知恵を求める姿勢が、
私たちにも求められていると思います。
第二章の前半部分までを、今日は学びました。
私たちもまた、さまざまな状況の中に置かれますが、
その中で正しく、ふさわしく判断できるように、
祈りつつ歩んでいく者でありたいと思います。
お祈りをして終わりたいと思います。
御言葉を通して、いつも励まし、また導いてくださることを感謝いたします。
私たちにも、知恵が必要です。
いろいろな難しい状況の中で、また人間関係の中で悩んだり、苦しんだりすることがありますが、
どうかいつも神様を見上げて、正しい判断ができるように、
知恵と力をいつもお与えくださいますようにお願いいたします。
御言葉の学びに感謝いたします。
また、この後の祈りの時もお導きください。
イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。