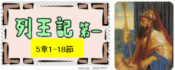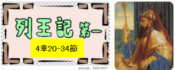マタイの福音書22章1~14節
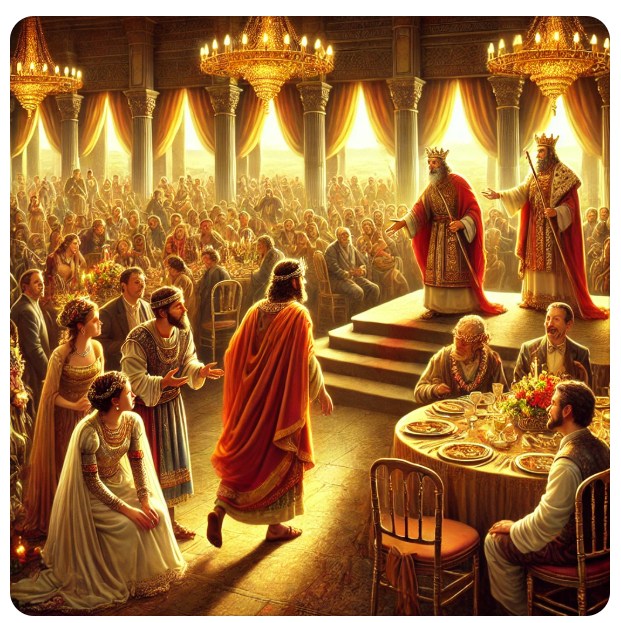
少し戻りますが、21章の23節から、祭司長たちや民の長老たちがやってきました。そして、イエス様に「何の権威によって、これらのことをしているのですか? 誰があなたにその権威を授けたのですか?」と挑戦してきたわけですね。彼らにとって一番許せないことが、そこだったのですが、非常に挑戦的な問いかけです。
それに対して、イエス様は21章の28節で、「ところで、あなた方はどう思いますか?」と問いかけ、一つの例え話をしました。それは、お父さんと二人の息子の例え話ですね。父が二人の息子に「働いてくれ」とお願いすると、兄は最初「行きたくない」と言うのですが、思い直して後で行きます。一方、弟は「はい、行きます」と答えるのに、結局行かなかったという話です。
この例えで、弟はユダヤ人たちを指しているのですね。口では「行きます」と言うけれど、実際には行こうとしない。つまり、中身のない信仰を持っているということです。イエス様は、ユダヤ人たちに対してこのことに気づいてほしいという思いで、この例え話を語ったのです。
そしてその後、33節で「もう一つの例えを聞きなさい」と言い、また別の例え話が始まります。これは、ある主人が自分の息子をぶどう園に送るのですが、ぶどう園の農夫たちは、その息子を殺してしまうという話です。まさに、イエス様がこれから経験しようとしていることですね。この農夫たちはユダヤ人たちを表しています。父なる神がせっかく遣わしてくださった一人子イエス様を、彼らはこれから殺そうとしている。そのことを、イエス様は指摘しているわけです。
最後の結論として、彼らは「これは自分たちのことを言われている」と気づきました。そして、本当はイエス様を捕えたかったのですが、群衆を恐れ、人々の目を気にして、その場では捕えることができませんでした。しかし、彼らの心の中は、イエス様に対する怒りと憎しみで煮えくり返っていたのです。
それでも、イエス様はなお彼らに話をしようとしました。この展開には驚かされますね。イエス様は彼らに対して、再び例えをもって話されたのです。さらに粘り強く関わろうとしているのですね。しかも、彼らは「自分たちのことを言われている」と気づいています。それまでは気づいていなかったのですが、今度は気づいた上で、さらに話を続けていくという展開になっています。
そこで、イエス様は三番目の話として、今度は結婚式の例え話をします。「天の国は、自分の息子のために結婚の披露宴を催した王に例えることができます。」王は、披露宴に招待した客を呼ぶために、しもべたちを遣わしました。しかし、彼らは来ようとしませんでした。
そこで、王は再び別のしもべたちを遣わし、「招待した客にこう言いなさい。『私は食事を用意しました。肥えた家畜を屠り、何もかも整いました。どうぞ、披露宴においでください。』」と言わせました。これは、天の御国の例え話ですね。
王には、すでに招待している客がいました。そして、その客たちを迎えに行くために、しもべたちを遣わしたのです。しかし、招待された客の反応は芳しくありませんでした。彼らは来ようとしなかったのです。
それでも王は諦めず、もう一度別のしもべを遣わします。そして、「こう伝えなさい」と具体的な言葉を教えます。「何もかも整いました。美味しい料理もできています。肥えた家畜を屠り、肉料理も用意しました。もう、食べるだけの状態です。ぜひ、披露宴においでください。」
しかし、彼らは気にもかけませんでした。5節には「彼らは気にもかけず、ある者は自分の畑に、別の者は自分の商売に出て行きました」とあります。彼らは結婚式の披露宴には全く関心がなく、それぞれ自分の仕事で忙しかったのです。
それだけではありません。さらにひどいことが起こります。6節では、「残りの者たちは、王のしもべたちを捕まえて侮辱し、殺してしまった」とあります。つまり、彼らは招待を断るだけでなく、使者を捕まえ、侮辱し、ついには殺してしまったのです。
この話は、さきほどのぶどう園の例え話とつながっています。ぶどう園では、主人が遣わした息子を農夫たちが殺しました。それと同じように、ここでも王が遣わしたしもべたちが殺されてしまったのです。これは、イエス様がこれから経験することを示しています。そして、この話を聞いているユダヤ人たちは、「自分たちのことを言われている」と気づいたのではないでしょうか。
それに対し、王はどうしたのでしょうか。7節では、「王は怒って軍隊を送り、その人殺しどもを滅ぼし、彼らの町を焼き払った」とあります。王の怒りがどれほど激しかったかが伝わりますね。彼らを滅ぼすために、軍隊を派遣し、町を焼き払ってしまったのです。
これは、神の怒りの激しさを表しているのでしょう。王は、披露宴の準備を整え、招待したのに、誰も来ようとせず、さらには使者を殺されました。その悲しみと怒りは計り知れません。
私たちも、例えば教会の愛餐会(食事会)で、美味しい料理をたくさん用意したのに、食べる人が誰もいなかったら、寂しいですよね。それと同じように、王も深い悲しみを抱いたことでしょう。
そんなことまでしてしまうとは、それは本当に神様にとって大きな悲しみであり、怒りであるということですね。
ここで語られているのは、まさにそのことです。せっかく披露宴の用意ができているのに、誰も来てくれない。ですが、この話はここで終わるわけではありません。では、その後、王様はどうしたのでしょうか?
8節からですが
それから、王は下僕たちに言いました。「披露宴の用意はできているが、招待した人たちはふさわしくなかった。だから、大通りに行って、出会った人を皆披露宴に招きなさい。」
下僕たちは通りに出て行き、良い人でも悪い人でも出会った人を皆集めたので、披露宴は客でいっぱいになりました。
ここで、「招かれていた人たち」とは、おそらくイスラエルの民、つまりユダヤ人のことを指しているのだと思います。彼らは本来、選ばれていたはずなのに、まったく反応しませんでした。それどころか、イエス様が来たとき、彼らはその招きを拒み、ついにはイエス様を捕らえて十字架につけてしまいました。
しかし、その後、王は下僕たちに命じ、大通りに行って出会った人々を皆招くようにと言いました。この話を聞いていた弟子たちは、おそらくこれを深く心に刻んだことでしょう。そして、後に彼らが実際に大通り、つまり全世界へ出て行き、すべての人々に福音を伝えることになったのです。
私たちも、同じ使命を与えられています。私たちの働きもまた、大通りに出て行き、神様の招きを伝え、人々を教会へと導くことなのです。このたとえ話に出てくる下僕たちのように、私たちも様々な場所で人々を招き、神様のもとへと連れてくる役割を担っています。
このたとえ話では、集められた人々の中には、良い人も悪い人もいたと書かれています。これは、当時の社会で罪人とみなされていた人々——例えば取税人や遊女など——も含まれていると考えられます。イエス様のもとには、そうした人々も招かれ、共に食事をし、話を聞き、救いへと導かれました。披露宴が客でいっぱいになったというのは、そうしたすべての人々が神のもとに集められたことを象徴しているのでしょう。
ところが、11節からは新たな展開が起こります。
王が客たちを見ようとして入ってくると、婚礼の礼服を着ていない人が一人いました。王はその人に言いました。「友よ、どうして婚礼の礼服を着ないでここに入ってきたのか?」 しかし、その人は黙っていました。
おそらく、この婚礼の礼服は、王によって用意されたものであったと考えられます。突然招かれた人々が、自前で礼服を用意できたとは考えにくいからです。貧しい人々もいたでしょうし、準備の時間もなかったはずです。しかし、王は彼らにふさわしい礼服を与えたのです。それなのに、この男はそれを着ていなかった。
13節では、その結果が語られます。
そこで王は召使いたちに命じました。「この男の手足を縛って、外の暗闇に放り出せ。彼はそこで泣いて歯ぎしりすることになる。」
せっかく招かれ、婚礼の席にいたにもかかわらず、礼服を着ていなかったために、彼は手足を縛られ、外へ追い出されてしまいました。
これは、私たちにとっても重要な警告です。私たちはイエス様の救いに預かり、神の国へと招かれました。しかし、与えられた「礼服」をちゃんと着ているでしょうか?
礼服を着ていないことで、私たちは神様を大いに失望させてしまうのではないかと考えさせられます。そもそも「礼服」とは何を指しているのでしょうか?
新約聖書を読んでいくと、パウロの手紙などに「イエス・キリストを着る」「新しい人を着る」といった表現がたびたび登場します。イエス様を信じ、救いをいただくとはどういうことなのか。その一つの説明として、「新しい人を着せていただく」「イエス様を着せていただく」ということが挙げられます。これは、クリスチャンとしての新しい生き方であり、クリスチャンとしての姿なのです。
例えば、ガラテヤ人への手紙3章27節には次のように書かれています。
「キリストに着くバプテスマを受けたあなたがたは皆、キリストを着たのです。」
これは、外見的に劇的な変化があるわけではなく、一見すると人が大きく変わったようには見えないかもしれません。しかし、神様の目から見たら、すでにその人は変えられているのです。なぜなら、キリストを着た人だからです。
キリストの義の衣を着せていただいたことによって、罪人であるにもかかわらず、神の前に義と認められる。それが、神様の恵みなのです。この義の衣をまとっている限り、私たちはキリストのうちにあって、どんどん清められていきます。それは、イエス様が私たちに与えてくださる恵みの働きなのです。
ところが、もし私たちがこの義の衣を脱ぎ捨ててしまい、「やっぱり元の古い衣の方がいい」と言って、汚れた衣を再び身につけるならばどうなるでしょうか? それは、イエス様が十字架にかかってまで私たちを救ってくださったという恵みを無にする行為です。そんなことをしてしまえば、神様を深く悲しませることになるでしょう。それは、せっかく与えられた恵みを踏みにじる行為であり、神様に対して大変失礼なことでもあります。
ですから、私たちは、せっかく神様に招かれ、その場に招かれた者としての恵みを味わっているのに、礼服を着ていなかったがために、そこから除外されてしまうことのないようにしなければなりません。
救われた者として、私たちは本当に気をつけるべきです。この例え話を通して、神様が私たちに与えてくださった恵みをしっかりと覚え、ふさわしく生きていくことの大切さを学びたいと思います。
新約聖書には、「キリストを着る」という表現が出てきます。例えば、ガラテヤ人への手紙3章27節には、
「キリストに着くバプテスマを受けたあなた方は皆、キリストを着たのです。」
と書かれています。
つまり、神様の目から見れば、私たちはキリストの義の衣をまとっているのです。それによって、罪人であっても義と認められ、神の前に立つことができるのです。
しかし、その衣を脱ぎ捨ててしまったらどうなるでしょう? せっかく与えられた恵みを受け取らず、ふさわしい姿で神の前に立とうとしなければ、たとえ披露宴の席にいたとしても、最終的には外へ追い出されてしまうのです。
私たちもまた、このたとえ話を通して、自分の姿を振り返る必要があります。神様が用意してくださった「義の衣」をしっかりと身にまとい、ふさわしい者として神の国に迎えられるように、日々の歩みを大切にしていきましょう。
招かれる人は多いが、選ばれる人は少ない
イエス様は、今回のたとえ話の最後に 「招かれる人は多いが、選ばれる人は少ないのです」(マタイ22:14)と言われました。
伝道をしていると、この言葉を実感することがあります。例えば、トラクト(福音のチラシ)を配って、「ぜひ教会に来てください」と多くの人を招くのですが、実際に来てくれる人はほんのわずかです。招かれる人は多いけれども、それに応じる人は少ないという現実を経験することがあります。
しかし、これは私たちだけではなく、神様ご自身がずっと感じておられることなのではないでしょうか。
神様の絶え間ない招き
ヨハネの福音書には、 「イエス様はすべての人を照らす真の光として来られた」(ヨハネ1:9)とあります。イエス様はすべての人の救いを願い、絶えず招いておられます。しかし、その招きに応じる人は決して多くありません。
イエス様の時代、パリサイ人たちは非常に頑なで、何度招かれても応じようとしませんでした。それでも、イエス様はあきらめることなく、「あなたも招かれていますよ。本当に戻ってきてほしい」と熱心に呼びかけ続けられました。このイエス様の情熱と愛を、私たちも学びたいと思います。
今回のたとえ話では、王(神様)が何度も招待を送る姿が描かれています。実際に 4回も 招待しているのがわかります。
1. 最初に招待状を送りました。
2. 次に、しもべを遣わして再度呼びかけました。
3. それでも応じないので、別のしもべを遣わしました。
4. さらに、最終的には町の大通りにまで出て、誰でもいいから招こうとしました。
これは、神様がどれほどあきらめずに招き続けておられるかを示しています。私たちも、この神様の姿勢にならい、 伝道において「一度誘ってダメだったから諦める」のではなく、何度でも祈りながら招き続ける者になりたい と思います。
なぜなら、神様のもとには必ず 「救い」 があるからです。その確かな祝福があるからこそ、私たちはあきらめずに人々を招き続けるのです。
救われた恵みを無駄にしない
また、このたとえ話から、もう一つ大切なことを学ぶことができます。それは、 せっかくいただいた「義の衣」を無駄にしないこと です。
私たちは、イエス様の義の衣を着せていただき、罪人であるにもかかわらず 「義」と認められた特権 を与えられました。この衣を着ている限り、私たちはどんどん清められていきます。しかし、もしそれを脱ぎ捨て、「やっぱり昔の古い衣の方がいい」と言って罪の生活に戻ってしまうならば、それは神様の恵みを踏みにじることになってしまいます。
ですから、私たちは せっかく救われた後も、古い生活に戻ることなく、いつも神様の恵みの中に生き続ける ことが大切です。
神の国は披露宴のような場所
最後に、神の国が「披露宴」に例えられていることにも注目したいと思います。
披露宴には、 喜び があります。美味しい食事があり、祝福の言葉があり、新郎新婦の幸せな姿があります。私たちは、披露宴に参加すると、自然と祝福された気持ちになりますよね。
教会も、それと同じであるべきです。
もし、せっかく招かれて教会に来た人が、そこに 陰口や争い、妬み しかないとしたら、誰も居続けたいとは思わないでしょう。しかし、本来 教会とは、イエス様(花婿)が中心におられ、喜びと愛に満ちた場所 であるはずです。
だからこそ、私たちの教会が 「披露宴のような、愛と喜びと祝福に満ちた場所」 であり続けることが大切なのです。そのような教会であればこそ、自信をもって 「ぜひ教会に来てください!」 と人々を招くことができます。
私たちの教会が、ますます神の国の喜びを体現する場所として成長していけるように、みんなで祈りながら励んでいきたいと思います。
祈り
神様
今日の御言葉を通して、あなたの私たちへの熱い思いを知ることができました。
あなたは何度も何度も私たちを招いてくださり、私たちを恵みの中に加えてくださいました。ありがとうございます。どうか、いただいた 義の衣 を脱ぐことなく、いつもキリストの恵みの中に生き続けることができますように。
また、私たちも 伝道において、あきらめることなく招き続ける者 となれますように。教会が、披露宴のような愛と喜びに満ちた場所となり、多くの人に祝福を届けることができますように。
この励ましの御言葉に感謝し、イエス様の御名によって お祈りします。
アーメン。