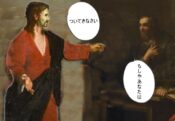マタイの福音書27章27~44節
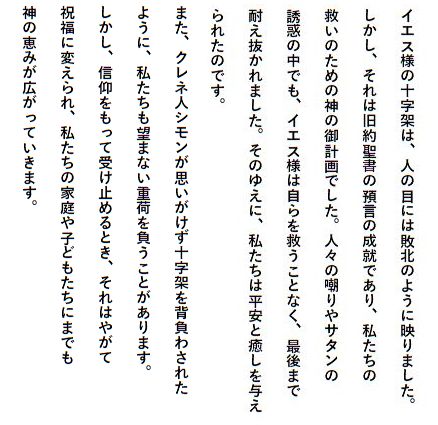
要約
イエス・キリストの十字架の場面は、一見すると敗北のように見えます。しかし実際には、旧約聖書の預言が成就し、神の救いの御心が実現している瞬間でした。
最初はイエスを罵っていた盗人が、最後の時に救いへと導かれたことに示されるように、イエスの十字架には人を変え、救う力があります。また、人々の「もし神の子なら降りてみろ」という嘲りは、荒野でサタンが語ったのと同じ誘惑でしたが、イエスは自らを救わず耐え抜くことで、私たちに平安と癒しをもたらしました。
さらに、偶然十字架を背負わされたクレネ人シモンの出来事は、思いがけない重荷や苦しみさえも、神の側から見れば祝福へと変えられることを示しています。シモンの家庭が祝福を受け、子どもたちが信仰を受け継いだことはその証です。
このように、イエスの十字架の苦しみと、それに関わった人々の姿を通して、私たちは「苦しみの中にも神の勝利と祝福がある」という真理を学びます。そして私たち自身も試練や辱めに直面するとき、イエスが先に耐えてくださったことを覚えつつ、信仰をもって従っていくよう招かれているのです。
筆耕
先週の場面は、裁判によってイエス様の死刑が確定した場面でした。今日の場面は、いろんな人々がイエス様に様々な苦しみを加えていき、それをひたすら耐え忍んでおられる、そういう場面だと思います。罵ったり侮辱したりということがずっと続いていく場面で、その間ずっと耐えておられたのだな、ということを教えられる場面だと思います。
まずは、ピラトと直属の兵士たちですね。嘲ったり、暴力を振るったりしているのが、今日の最初の場面だと思います。27節「それから総督の兵士たちはイエスを総督官邸の中に連れて行き、イエスの周りに全部隊を集めた」とありますから、この時、全部隊が集められたのだな、ということに気づかされました。全部隊の兵士たちがそこにいる中での嘲笑であり暴力であった、ということですね。ですから、ちょっと異様な雰囲気だったのではないか、ということが分かります。
それで、イエス様を連れてきて着物を脱がせ、緋色のマントを着せ、そしていばらで冠を編んでイエス様の頭に置き、右手に葦の棒を持たせました。これは要するに、イエス様を王様のように仕立てた、ということですよね。杖のようなものを持たせ、王様のように仕立てて、そしてイエス様の前に彼らはひざまずき「ユダヤ人の王様、万歳!」と言ってからかいました。そして、さんざんからかった後でイエス様に唾をかけ、葦の棒を取り上げて頭を叩き、さらにマントを脱がせて元の衣を着せ、十字架につけるために連れ出しました。つまり、十字架を背負って出発する前に、さんざん兵士たちに馬鹿にされ、侮辱され、暴力を振るわれたということですね。
けれども、32節に「兵士たちが出て行くと、シモンという名のクレネ人に出会い、彼らはこの人にイエスの十字架を無理やり背負わせた」とあります。最初はイエス様がおそらく十字架を背負って歩み始めたのだと思いますが、とても重い十字架を背負えるような状態ではありませんでした。前の日から全然眠っておらず、一睡もしていなかったのですし、ピラトの裁判で判決が下った後の26節に「イエスはムチで打たれてから」と出てきます。普通のムチではなく、その先に石や硬い貝殻などがついた、非常に残酷なムチだったと言われています。それで打たれれば、すぐに体が裂けて血が流れる。つまり、この時点ですでに血だらけで、背中は傷だらけの状態だったと考えられます。その上でローマ兵に散々馬鹿にされ、嘲られ、棒で叩かれて、とても十字架を担える体ではなかったということなのです。それで倒れてしまったのかもしれません。
そこに、たまたま通りすがりのシモンという名のクレネ人がいたので、この人に無理やりイエスの十字架を背負わせた、ということですね。そういう展開だったと考えられます。
そして、イエス様は苦味を混ぜたぶどう酒を飲ませようとされたが、それを舐めただけで飲もうとはされませんでした、と34節に記されています。その後、彼らはイエスを十字架につけ、くじを引いてその衣を分けました。こうして十字架には「これはイエスである」と書かれた罪状書きが掲げられていた、と37節に出てきます。さらにヨハネの福音書によると、それはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていた、とあります。ですから、いろんな国の言葉で誰が見てもわかるようになっていた、ということですね。
また、イエス様と一緒に2人の強盗が、1人は右に、もう1人は左に、3人で十字架につけられました。ここで通りすがりの人々が登場します。十字架に磔にされているイエス様の前を、いろんな人たちが通って行ったわけですが、その通りすがりの人たちもイエス様を罵ったと、39節に出ています。通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵った、と。これは頭を激しく振りながら嘲っている様子を表す言葉ですが、実は詩編22編の成就であることが分かります。
詩編22編の冒頭には「わが神、わが神、どうして私をお見捨てになったのですか」という言葉が出てきます。この詩編は十字架によって成就したものですが、6節から8節にはこう書かれています。
「しかし、私は虫けらです。人間ではありません。人のそしりの的、民の蔑みの的です。私を見る者は皆、私を嘲ります。口を尖らせ、頭を振ります。」
ここに「頭を振る」という表現が出てきます。つまり、通りすがりの人々がイエスを罵りながら頭を振った出来事は、すでに詩編22編に預言されていたことの成就なのです。さらに8節には「主に身を任せよ、助け出してもらえばよい。主に救い出してもらえ。彼のお気に入りなのだから」と書かれています。これは、この後に登場する祭司長や律法学者たちがイエス様に向かって語った言葉そのものです。
41節以降には、祭司長や律法学者、長老たちがイエスを嘲って言いました。「他人は救ったが、自分は救えない。彼はイスラエルの王だ。今、十字架から降りてもらおう。そうすれば信じよう。彼は神により頼んでいる。神のお気に入りなら、今救い出してもらえ。『私は神の子だ』と言っているのだから。」──この「神のお気に入りなら」という表現も、詩編22編にある言葉の成就なのです。
つまり、通りすがりの人々も、祭司長や律法学者、長老たちも、みなイエスを罵り嘲ったのですが、それはすでに預言されていたことが実現した姿だったのです。彼らは長い間イエス様を殺そうと策略を巡らし、協議を重ね、陰謀を企んで努力してきました。その結論が出た時、一気に憎しみが爆発し、さんざんイエス様を罵ったのだと思います。
さらに44節には、イエスと一緒に十字架につけられた強盗たちも同じようにイエスを罵った、とあります。つまり、右と左にいた強盗たちも最初はイエスを罵っていたのです。ルカの福音書によると、この後1人は悔い改めへと導かれますが、それでも最初はイエスを罵っていたことが分かります。
おそらく彼は、十字架上でイエスが語られた「父よ、彼らをお赦しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです」という言葉をすぐそばで聞いて、心が打たれたのではないでしょうか。そして、「この方こそ本当の救い主なのだ」と気づき、悔い改めへと導かれたのだと思います。
それまで彼も一緒になってイエス様のことを罵っている、そういう人だったんだと思うんですけれども、そのイエス様の言葉に耳を止めた時に、「本当にこの方は救い主だ」と導かれて、本当に最後の最後の段階でしたけれども、イエス様を信じることができて、「あなたは私とともにパラダイスにいる」と言っていただける展開に導かれていった、ということが見えてくるのかなと思います。
今日は、このようにローマ軍の兵士たちもイエス様を馬鹿にし、通りすがりの人たちもイエス様を罵り、祭司長たちや律法学者たち、長老たちもまことに激しくイエス様を罵りました。しかしイエス様は、そういう人々の嘲り・罵り・暴力に苦しんでおられた、というのが今日の場面です。
この場面は、イエス様は敗北したように見えるかもしれません。一般の人が読んだら、「イエス様は敗北したな」と見えるかもしれません。しかし、これは神様の御心の成就であったということは、旧約聖書を読むとよく分かることです。今までも学んできましたが、これはイザヤ書53章の御言葉の預言の成就だと言えると思います。では、53章の1節から3節までを読んでみます。
「私たちが聞いたことを、誰が信じたか。主の御腕は誰に現れたか。彼は主の前にひこばえのように生え出た。砂漠の地から出た根のように。彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々から除け者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。」
ここに出てくる「彼」とは、メシヤ、つまりイエス様のことを指しています。イエス様には見るべき姿も輝きもない。確かにその通りだと思いますね。彼は蔑まれ、人々から除け者にされ、悲しみの人で、病を知っていました。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。──人が顔を背けるほどの蔑みとはどれほどのものだったのでしょうか。顔を見ることもできないくらいひどい蔑みを、この方は経験されたのだと預言されていて、まさにその通りだったと思います。
私たちも読めば理解できますが、その場面を実際に見ることはできないほど、心が痛みますね。イエス様はそれを耐えておられた。外からは敗北のように見えますが、そこに本当の勝利があるのです。私たちはそれを覚える必要があると思います。
また、マタイの本文に戻りたいと思います。いろんな人々から嘲りの言葉を、様々な表現でぶつけられているイエス様ですが、ここで注目したい言葉があります。それは通りすがりの人々がイエス様に向かって言った40節の言葉です。
彼らは頭を振りながらイエス様を罵り、こう言いました。
「神殿を壊して三日で建てる人よ。もしお前が神の子なら、自分を救ってみろ。そして十字架から降りてこい。」
「もしお前が神の子なら」という言葉は、非常に誘惑の言葉だと思います。マタイ4章に出てくる、イエス様が荒野で40日40夜断食した後、サタンの試みを受けた場面を思い出します。
イエス様がお腹を空かせておられる時に、サタンは「あなたが神の子なら、これらの石をパンに変えてみろ」と言いました。確かにイエス様は神の子であり、それはなんでもないことです。しかしサタンの狙いは、神の御言葉ではなく自分の力に頼らせることでした。それに対してイエス様は、「人はパンだけで生きるのではない」と御言葉をもって勝利されました。
さらにサタンは、「あなたが神の子なら、下に身を投げなさい」と言いました。これも同じ誘惑の言葉です。「神の子ならできるだろう」と挑発しているのです。
十字架上でイエス様に向かって「もし神の子なら降りてこい」と叫んだ人々の言葉は、まさに同じ性質の誘惑だったと思います。イエス様は間違いなく降りることも、自分を救うこともできました。激しい痛みの中で、この言葉は本当に大きな誘惑だったと思います。しかしイエス様は、あえて降りてこられませんでした。自分を救おうとはされませんでした。そこにこそ、イエス様の勝利があるのです。
イザヤ書には「彼は私たちのために刺され、私たちの咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された」とあります。イエス様は、私たちの平安と癒しのために苦しみを負ってくださったのです。
だから、このイエス様の苦しみの場面を、私たちは心にしっかり刻む必要があります。というのは、私たち自身も時に馬鹿にされたり、侮辱されたり、苦しみに遭うからです。子どもたちも学校でいじめにあったりする。理不尽で、どうすることもできない苦しみがあります。
しかし、イエス様がその苦しみを味わってくださったという理解は、大きな慰めになります。「イエス様は自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができる」と聖書にあります。その通りです。イエス様が様々な苦しみを体験されたからこそ、私たちを助けることができるのです。
私たちも虐げられたり、悩んだり、痛みに遭うことがあります。その時、「この痛みをイエス様なら分かってくださる」と覚えることができる。それは大きな慰めであり、信仰の支えになると思います。
最後にですね、今日はこの十字架を背負わされたクレネ人シモンという人に注目をして、終わりたいなと思います。イエスの十字架を無理やり背負わせた、無理やり背負わせたということなんですね。全然そのことを想定もしていなかったんだけれども、たまたまその場面に居合わせたんだと思います。おそらく今の北アフリカのリビアのあたりだっただろうと言われています。アフリカ人なんですね。
お祭りの時というのは、いろんな地域に散らばっているユダヤ人たちは、ユダヤだけではなくアフリカの方にまで散らばっていました。それでも過ぎ越しの祭りの時には、みんな集まってくるわけですね。それで十字架のために集まってきていて、アフリカから来ていたということは考えられるんですけれども、そのたまたまそこに居合わせたために、十字架を背負わされた。これは想定外のことだったと思いますね。
その時の彼にとっては、とても嫌なこと、辛いことだったかもしれません。けれども結果的に彼は、イエス様の苦しみの一端を担うという、そういう特権が与えられたんだと思います。見方によっては、私たちにとってはすごく嫌なことであるかもしれない。けれども神様の側から見れば、それはイエス・キリストの苦しみの一端を担うことのできる特権が彼に与えられた、そういうことになるのかなと思いますね。
その後どうなったかということは全然分かりません。しかし福音書にシモンについて「この人はアレクサンドロとルフォスの父であった」との記述が出てきます。15章21節に出てくるんですね。息子が二人いたんだな、ということがその時わかるんです。このアレクサンドロスという人はよく分かりませんけれども、ルフォスという人はこの後出てきます。聖書を開いて、今日はそこで終わりたいと思いますが、ローマ人への手紙16章13節にこう紹介されています。
「主にあって選ばれた人ルフォスによろしく。また、彼と私の母によろしく。」
挨拶している場面なんですね。つまり、パウロが「彼によろしくね、あの人にもよろしく伝えておいてね」と書いている。そこに「主にあって選ばれた人」として紹介されているのです。これはローマ教会の大切なメンバーの一人であった、ということ。そしてとても親しみを込めて呼んでいるんですよね。友達だったんじゃないか、ということも言われています。本当にローマ教会の大事な一員だったということが見えてくるんですね。
また「彼と私の母によろしく」という言葉も出てきますが、これは実の母ではなく、パウロが母のように慕っていた人だと考えられています。それほど親しい間柄であった、ということがここから見えてきます。
おそらくシモンにとって、十字架を担ったのはとても辛い経験だったと思います。けれどもイエス様の十字架の一端を担った。その苦しみの一部を担わせていただいたということが、その後、恵みの体験に変えられていったのではないかと思います。その経験が祝福に変えられ、神様は彼の家庭を祝福され、奥さんを祝福され、子供たちを祝福してくださいました。そして息子は「選ばれた人」としてパウロの友人となっている。その姿から私たちは大きな励ましを受けることができるんじゃないかと思います。
私たちもいろんなことに巻き込まれて、「嫌だな」と思うことがあります。思いがけない十字架を背負わされ、辛い思いをしなくてはならないこともあります。けれども、もしその時に「これは苦しみの一部を自分が担わせていただいたのだ」と信仰をもって受け止めたなら、それは恵みの体験へと変えられていく。劇的な変化を経験することができるんじゃないかと思うんです。
もう本当に嫌なこと、もう二度とやりたくないと思うような経験であっても、そのことを通して神様の祝福が家庭にあふれ、子供たちがその親の信仰を見て育つ。やがて子供たちもまた「選ばれた人」として信仰を受け継いでいく。そこに神様の祝福が広がっていくんですね。それは私たちにとって大きな励ましではないでしょうか。
ですから、ぜひこのシモンが十字架を背負った姿から私たちも学び、いろんなことがありますけれども、信仰をもって神様により頼んで歩んでいくものでありたいと思います。その時、祝福してくださる神様に感謝していきたいと思います。
神様、イエス様がいろんな人からいろんなことを言われ、散々バカにされ、嘲られ、ひたすら辱められましたけれども、全部それは私たちの救いのためであったことを覚えてありがとうございます。私たちもこの世でいろんな経験をしますけれども、その中にあってイエス様の十字架を思い起こし、イエス様の苦しみの一端を担わせていただき、そしてその中にあっても信仰をもって従っていくことができるように導いてください。と、お祈りをいたします。