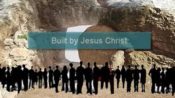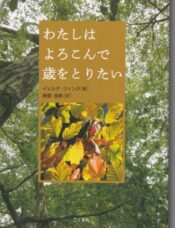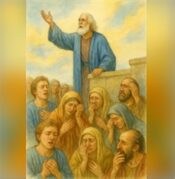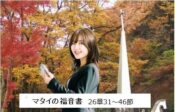マタイの福音書20章17節~34節

「ご覧なさい。わたしたちはエルサレムに上って行きます。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、
異邦人に引き渡します。嘲り、むちで打ち、十字架につけるためです。しかし、人の子は三日目によみがえります。」
そのとき、ゼベダイの息子たちの母が、息子たちと一緒にイエスのところに来てひれ伏し、何かを願おうとした。
イエスが彼女に「何を願うのですか」と言われると、彼女は言った。「私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるように、おことばを下さい。」
イエスは答えられた。「あなたがたは自分が何を求めているのか分かっていません。わたしが飲もうとしている杯を飲むことができますか。」彼らは「できます」と言った。
イエスは言われた。「あなたがたはわたしの杯を飲むことになります。しかし、わたしの右と左に座ることは、わたしが許すことではありません。わたしの父によって備えられた人たちに与えられるのです。」
ほかの十人はこれを聞いて、この二人の兄弟に腹を立てた。
そこで、イエスは彼らを呼び寄せて言われた。「あなたがたも知っているとおり、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄にふるまい、偉い人たちは人々の上に権力をふるっています。
あなたがたの間では、そうであってはなりません。あなたがたの間で偉くなりたいと思う者は、皆に仕える者になりなさい。
あなたがたの間で先頭に立ちたいと思う者は、皆のしもべになりなさい。
人の子が、仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として、自分のいのちを与えるために来たのと、同じようにしなさい。」
さて、一行がエリコを出て行くと、大勢の群衆がイエスについて行った。
すると見よ。道端に座っていた目の見えない二人の人が、イエスが通られると聞いて、「主よ、ダビデの子よ。私たちをあわれんでください」と叫んだ。
群衆は彼らを黙らせようとたしなめたが、彼らはますます、「主よ、ダビデの子よ。私たちをあわれんでください」と叫んだ。
イエスは立ち止まり、彼らを呼んで言われた。「わたしに何をしてほしいのですか。」
彼らは言った。「主よ、目を開けていただきたいのです。」
イエスは深くあわれんで、彼らの目に触れられた。すると、すぐに彼らは見えるようになり、イエスについて行った。
聖書 新改訳2017©2017新日本聖書刊行会 許諾番号4–2–3号
これまで学んできた箇所を振り返ってみると、持てるものを捨てることができたか、できなかったかの違いはあるんですけれども、金持ちの青年も、ペテロを含む弟子たちも、みんな結局は自分のことを考えているんですよね。自分が先か後か、自分が上か下か、誰が一番偉いか。たえず自分のことばかり考えている傾向が、弟子たちにはあったんだろうなと思います。
そういう弟子たちの状態を意識した上で、先週はぶどう園のたとえを学びました。イエス様は、やはりそういうことも意識しながら、このたとえを話してくださったんだろうなと思います。そして改めて、御国の姿について提示してくださいました。
「御国は、ぶどう園で働く者を雇うために、朝早く出かけた家の主人のようなものです。」
ぶどう園の主人に、御国の豊かさや素晴らしさが表されている、ということですよね。そういうたとえ話を前回学びました。
このぶどう園の主人というのは、本当に気前がよく、誰にでも同じように恵みを与えてくださる主人ですよね。その主人にしっかり目を留めていれば、私たちは妬んだりすることはないし、「どっちが先だ」「後だ」「多い」「少ない」といったことで、心を煩わせる必要もありません。ただ神様だけを見ていればいいのですが、私たちはつい自分のことを考えてしまいます。そして人と比較し、ああだこうだと言って、心を騒がせてしまう。そういう状態なのだと思います。
それで、イエス様は弟子たちに対して、ぶどう園のたとえを通して、改めて御国の素晴らしさを教えてくださった。それが前回の話だったかなと思います。
でも、その続きの話が今日の箇所なのですが、どうもイエス様のメッセージというのは、なかなか弟子たちには伝わっていかないのかな、という感じがするのが今日のお話かなと思います。
今日は、イエス様とその一行がエルサレムに向かう場面から始まります。
17節
「さて、エルサレムに登る途中、12弟子だけを呼んで道々彼らに話された。『私はエルサレムに登っていきます。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。嘲られ、むちで打たれ、十字架につけられるためです。しかし、人の子は三日目によみがえります。』」
このように、イエス様はエルサレムに向かう途中で、もう一度、自分が十字架にかけられて死ぬことを伝えています。これは「十字架予告」といわれるもので、これが三回目になります。
一回目は21節、二回目は17章の22〜23節。それぞれ、「自分は引き渡されて死ぬ」と弟子たちに伝えていましたが、今回は三回目。そして、この三回目の内容は、今までよりもさらに詳しく、具体的になっていることがわかります。
「人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは人の子を死刑に定める。そして異邦人に引き渡される。」
ここでいう「異邦人に引き渡す」とは、ローマ人に引き渡すことだと思います。「嘲られ、むちで打たれ、十字架につけられる」と、非常に具体的ですよね。そして、ここに書いてある通り、イエス様がおっしゃられた通りのことが、この後、本当に起こっていきます。
とにかく、今回の十字架予告は、詳しく、具体的です。イエス様がこの時、どのような思いでおられたのかが伝わってきます。
もう、自分の死が近づいている。十字架が近づいている。
この時のイエス様の思いとは、どのような思いだったのかと想像しますが、本当に想像できないような、張り詰めた思いをイエス様は持っておられたのではないかと思います。しかし、そのことに弟子たちは全く気づいていなかったでしょう。それどころか、気づいていないだけでなく、関心すらなかったのではないでしょうか。
この時、弟子たちの心をとらえていたのは何かというと、その次に出てくることが象徴的なのですが、やはり「どれだけ自分たちが偉くなれるか」ということ。つまり、自分のことしか考えていないのです。そのために、イエス様のことが全然見えていないし、イエス様の御心も全くわかっていない。弟子たちは、そういう状態になっていたことがわかるのだと思います。
それで、次の話に進んでいくのですが、何が起こったかというと、ゼベダイの息子たちの母が登場します。これは、ヤコブとヨハネのお母さんのことですね。彼女がイエス様のもとに来る場面を見ていきたいと思います。
20節
「その時、ゼベダイの息子たちの母が、息子たちと一緒にイエスのところに来て、ひれ伏し、何かを願おうとした。イエスが『何を願うのですか』と言われると、彼女は言った。『私のこの二人の息子が、あなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。』」
ヤコブとヨハネのお母さんが、ここで突然登場します。同じ内容の記事がマルコの福音書にも記されていますが、そちらには母親は登場せず、ヤコブとヨハネが直接願い出る形になっています。マタイの福音書の方が、より詳しく書かれているのだと思います。つまり、実際には母親もそこにいたということですね。
彼女の願いは、「御国で、私の息子のために、右の座と左の座を確保してください」というもの。おそらくこれは、イエス様がマタイの福音書19章28節でおっしゃった言葉に反応したものだと考えられます。
19章28節
「誠に、あなたがたに言います。人の子がその栄光の座に着く時、新しい世界で、私に従ってきたあなたがたも十二の座について、イスラエルの十二の部族を治めます。」
イエス様は、このようにお話しされています。これは、おそらくイエス様の再臨の時、つまり、ずっと先の話なのだと思います。しかし、ヤコブとヨハネ、そしてその母親は、「その時がもう迫っている」と感じたのでしょう。イエス様が栄光の座に着くその時が、すぐ近くに迫っていると考えたのではないかと思います。
他にも十二人の弟子たちはいるわけですが、彼らよりも先に、自分の息子たちに一番良い場所を確保してほしい、という願いだったのです。母親として、息子たちへの愛からくる願いだったのかもしれません。しかし、状況が見えていないというか、冷静さを欠いているというか、非常に目的意識が強く、盲目的な姿ともいえるでしょう。
それに対して、イエス様は対応されます。
22節
「イエスは答えられた。『あなたがたは、自分が何を求めているのか分かっていません。私が飲もうとしている杯を、飲むことができますか。』 彼らは『できます』と言った。イエスは言われた。『あなたがたは、確かに私の杯を飲むことになります。しかし、私の右と左に座ることは、私が許すことではありません。それは、私の父によって備えられた人たちに与えられるのです。』」
まず最初に、イエス様が言われたのは「あなたがた」という言葉でした。これは、ヤコブとヨハネ、そしてその母親の三人に向けられた言葉だと思います。
「あなたがたは、自分が何を求めているのか分かっていません。」
彼らは一生懸命願っていました。母親も、強く願っていたのですが、イエス様は「あなたは何を願っているのか、実は分かっていないのだ」と指摘されます。その願いは、的外れなものであり、誤った求め方をしているということなのでしょう。
続いて、イエス様は「私が飲もうとしている杯を、飲むことができますか?」と問いかけました。彼らの中には、何かしらのイメージがあったのだと思います。しかし、この「杯」という言葉は、イエス様がゲツセマネの祈りの中でも語られているように、「十字架の苦しみ」と「死」を象徴しています。つまり、イエス様は「私がこれから経験する十字架の苦しみを、あなたがたも受けることができますか?」と問われたのです。
それに対し、彼らは「できます」と答えました。すると、イエス様はこう言われました。
「あなたがたは、確かに私の杯を飲むことになります。しかし、私の右と左に座ることは、私が許すことではありません。それは、私の父によって備えられた人たちに与えられるのです。」
つまり、誰が右と左の座に座るのかは、天の父なる神が決めることであり、人が願えば叶うものではないということです。神の御心にかなわない祈りは、叶えられないということなのでしょう。イエス様は、そうした神の主権を明確に示されました。
私たちも、何でも願うことはできます。しかし、その願いが自分勝手なものになってしまうこともあります。もちろん、御心にかなう願いであれば叶えられますが、最終的な決定権は神にあるのです。私たちは、そのことをしっかりと覚えておく必要があるのではないでしょうか。
このようにして、イエス様はヤコブとヨハネ、そしてその母に答えられました。しかし、その様子を他の弟子たちも見ていました。そして、十人の弟子たちは、この二人の兄弟に対して腹を立てたのです。
なぜ、彼らは腹を立てたのでしょうか? それは、結局のところ、彼らも同じように考えていたからではないでしょうか。ヤコブとヨハネが、自分たちを差し置いて先に良い地位を得ようとしたことに対し、彼らは強い怒りを感じたのです。しかし、それはつまり、彼ら自身も「自分がどれだけ偉くなれるか」「どれだけ高められるか」ということに執着していたことの表れでした。
イエス様が、この時どのような思いでおられたのか、弟子たちはほとんど理解していませんでした。イエス様の思いや、神の御心を理解することができず、自分のことばかり考えていたのです。
私たちも、この話を通して、自分自身のことを考えさせられます。私たちは多くの願いを持っていますが、果たしてイエス様は私たちに何を願っておられるのか、どのような期待を持っておられるのかを、どれだけ理解できているでしょうか?
私たちは、御心のままに歩みたいと願いながらも、実際にはそれが見えてこないこともあります。また、神の御心に関心を持たず、気づかないまま生きてしまうこともあるかもしれません。
だからこそ、ヤコブとヨハネ、そして弟子たちの姿を通して、私たち自身の姿を省みることが大切なのではないかと思います。
そして、イエス様はさらに話を続けられます。
25節
「そこで、イエスは彼らを呼び寄せて言われた。『あなたがたも知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。しかし、あなたがたの間では、そうであってはなりません。あなたがたの間で偉くなりたいと思う者は、皆に仕える者になりなさい。あなたがたの間で先頭に立ちたいと思う者は、皆のしもべになりなさい。』」
この26節の冒頭で、イエス様はまず、当時の時代の姿について指摘されているように思います。「あなたがたも知っている通り」と言われたように、弟子たちはこの現実をよく理解していました。
「異邦人の支配者たちは、人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。」
これは、当時のユダヤの人々が日々直面していた現実です。ローマ帝国の支配がユダヤ全土に及び、その統治者たちは非常に横柄な態度をとっていました。つまり、ユダヤ人は異邦人の支配のもとで虐げられ、苦しみを受けていたのです。これが、彼らが生きていた社会の姿であり、厳しい現実でした。
このような世界の中で、弟子たちは生きていました。しかし、その後、イエス様はこう続けられます。
「あなたがたの間では、そうであってはなりません。」
これは、とても重要な言葉です。世の中では、権力を持つ者が横柄に振る舞い、人々を支配するのが当たり前になっています。しかし、イエス様の弟子たちの間では、そのような生き方をしてはならない、ということです。
ここで注目すべきなのは、「あなたがたの間では」という言葉です。イエス様の12人の弟子たちは、実はこの世の価値観にとらわれたままでした。つまり、「誰が一番偉いのか」「誰がイエス様のすぐそばにいられるのか」「誰が右と左の座を得るのか」といったことで競い合い、ライバル意識を持っていたのです。
彼らはイエス様に仕え、日々その教えを受け、信仰を養われているはずでした。しかし、心の奥底では、この世の生き方と同じ価値観にとらわれていました。イエス様は、そんな彼らに向かって「あなたがたの間では、そうであってはなりません」とはっきりと指摘されたのです。
では、弟子たちはどのように生きるべきなのでしょうか? 天の御国では、どのような生き方が求められるのでしょうか? それを、イエス様は教えられました。
「あなたがたの間で偉くなりたいと思う者は、皆に仕える者になりなさい。」
「あなたがたの間で先頭に立ちたいと思う者は、皆のしもべになりなさい。」
人は誰しも「先頭に立ちたい」「偉くなりたい」という思いを持っています。しかし、イエス様はそうではなく、「仕える者になりなさい」「しもべになりなさい」と教えられました。
そして、その模範となる生き方を示されたのが、イエス様ご自身でした。
28節
「人の子が仕えられるためではなく、仕えるために来たのであり、多くの人の贖いの代価として、自分の命を与えるために来たのと同じように、あなたがたも仕えなさい。」
ここで、イエス様はご自身の来られた目的を語られています。
「私は、人々に仕えられるためではなく、仕えるために来た。」
この言葉は、イエス様の生涯そのものを表しています。イエス様は王としてこの世に来られましたが、人々を支配するためではなく、むしろ仕える者として来られました。そして、最も偉大な仕え方として、ご自身の命を贖いの代価として捧げられたのです。
私たちもまた、イエス様の教えに従い、仕える者として生きることが求められています。
イエス様は本来、王であり、仕えられるべきお方でした。しかし、イエス様はその権威を振りかざすのではなく、私たち一人ひとりに仕えるために、しもべとなってこの世に来てくださいました。
そして、もう一つ注目すべきは「贖いの代価」という言葉です。これは「身代金」という意味であり、まさに十字架の出来事を指しています。イエス様は、私たちすべての罪を背負い、身代わりとなって贖いの代価を支払ってくださいました。つまり、イエス様はこの世に来られた目的の中心として、自らの命を捨てることを選ばれたのです。
このイエス様の姿勢は、私たちにとって模範となる生き方です。イエス様に倣い、私たちも仕える者となるようにと教えられています。イエス様を見上げ、目を離さずに歩んでいくことが、ここで示されている教えの核心なのではないでしょうか。
学びを深める中で、いくつかの気づきがあります。一つは、イエス様の忍耐深さです。イエス様はたとえ話を用いて何度も教えられましたが、弟子たちはなかなか理解しませんでした。この場面でも、イエス様は十字架を目前に控え、心が張り詰めるような状況にあったはずです。それにもかかわらず、弟子たちはまだ自分たちの地位や名誉のことを考えていました。
もし私たちが同じ立場にいたら、弟子たちの姿を見て苛立ちを感じ、怒りをぶつけてしまうかもしれません。しかし、イエス様は決してそうはなさいませんでした。弟子たちが理解できなくても、何度も繰り返し、忍耐強く教え続けられました。この姿には、イエス様の深い愛が現れているように思います。
もう一つの気づきは、弟子たちの本音が次第に明らかになっていくことです。彼らは網を捨ててイエス様に従い、奇跡を行い、悪霊を追い出すなどの働きをしました。しかし、決定的な場面になると、彼らの本音が露わになりました。自分の立場を気にし、誰が最も偉いかを競い合い、イエス様の本当の意図を理解しようとしませんでした。
この弟子たちの姿は、まさに人間の本性を映し出しています。人は、どれほど信仰深く見えても、根本には自己中心的な欲望があるものです。しかし、それを認識することが、イエス様を本気で求め、救いを求めるきっかけになるのではないでしょうか。
イエス様の導きの中で、私たち自身の姿に向き合うことは、決して無駄ではありません。むしろ、それは私たちが本当に神に近づくために必要な経験なのです。このような聖書の記事が記されていることに感謝しながら、私たちもまた、自分自身の在り方を問い直していきたいと思います。
私たちも、「結構立派な生き方をしてきた」と思っているかもしれません。しかし、実はそうではなく、本当の自分の姿と向き合わない限り、心から救いを求めようとしない傾向があるのではないでしょうか。
ですから、これは弟子たちにとっても、とても大切な経験だったのだと思います。そして、この経験を経て、彼らは砕かれていきます。私たちにとっても、この出来事は大切な教訓となる記事です。だからこそ、私たちはイエス様を必要としているのです。
ここでイエス様は、一つの生き方を提示してくださいました。それは素晴らしい生き方ですが、私たち自身の力ではとても実践できるものではありません。むしろ、絶望するしかないような存在です。しかし、そんな私たちに対しても、イエス様は決して諦めず、丁寧に教え、導いてくださいます。その導きがあることを、私たちは覚えておきたいと思います。
そして、後半には二人の盲人の話が出てきます。これは29節からですね。
さて、一行がエリコを出て行くと、大勢の群衆がイエスについて行きました。その時、道端に座っていた目の見えない二人の人が、イエスが通られると聞いて叫びました。
「主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください!」
群衆は彼らを黙らせようとたしなめましたが、それでも二人はますます叫び続けました。
「主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください!」
エリコを出て行く、ということは、イエス様はすでにエルサレムに近い場所に来ていたことが分かります。つまり、十字架の時が迫っているのです。そんな中で、道端に座っていた目の見えない二人が、イエス様の存在を知り、叫び求めるのです。
彼らの叫びに対し、周囲の人々は「うるさい」と思い、イエス様の邪魔になると考え、黙らせようとしました。しかし、この二人はそれに負けず、さらに大きな声で叫び続けました。
この二人がどのような人だったのか、なぜそこに座っていたのかは、詳しくは分かりません。しかし、この記事から少なくとも二つのことが読み取れます。
一つ目は、彼らが自分自身の罪深さをよく理解していた、ということです。彼らは、自分には神の憐れみが必要であることを知っていました。
二つ目は、彼らがイエス様を救い主と信じていた、ということです。どこでそのことを知ったのかは分かりませんが、「ダビデの子よ」と呼びかけています。「ダビデの子」とは、メシア(救い主)を意味する言葉です。彼らは、イエス様こそが救い主であることを確信していました。そして、今まさにその方が目の前を通ろうとしている。だから、必死に叫び、憐れみを求めたのです。
この叫びに対して、イエス様は素通りすることなく、立ち止まってくださいました。そして、彼らを呼び、こう尋ねられます。
「私に何をしてほしいのですか?」
彼らは答えました。
「主よ、目を開けていただきたいのです。」
ここで興味深いのは、イエス様が「何をしてほしいのか」と尋ねたことです。目の見えない人々が目を開けてもらいたいと願っているのは、誰の目にも明らかだったでしょう。しかし、それでもイエス様はあえて尋ねられました。
その理由は、おそらく彼ら自身に、信仰をもって願いを口にさせるためだったのではないでしょうか。イエス様は、ただ一方的に癒しを与えるのではなく、彼ら自身が信仰をもって願い求めることを大切にされたのだと思います。
この二人の姿勢から、私たちも学ぶことができます。私たちも、自分の弱さや罪を認め、イエス様に憐れみを求めることが大切です。そして、信仰をもって願い求める時、イエス様は必ず応えてくださるのです。
彼らは、「主よ、私たちを憐れんでください」と叫び、ただすがることしかできませんでした。しかし、そこからさらに一歩踏み込み、信仰を引き出すように、また信頼を引き寄せるように呼びかけています。
それに応えて、二人は「主よ、目を開けていただきたいのです」と願いました。
すると、イエス様はその求めに応じてくださいました。34節には、「イエスは深く憐れんで、彼らの目に触れられた。すると、すぐに彼らは見えるようになり、イエスについて行った」とあります。
つまり、彼らの願い、祈り、求めに、イエス様はしっかりと答えてくださいました。彼らの信仰に応えてくださったのです。やはり、イエス様はご自身を信じ、信頼する者に対して、必ず答えてくださる方です。御心にかなう祈りであれば、必ず叶えてくださるということを、私たちはこの出来事から教えられます。
この話全体を振り返ってみると、非常に明確な対照が示されていることが分かります。本来、見えているはずの弟子たちが、実は何も見えていなかったのです。彼らは日々イエス様の教えを受け、直接交わりを持っていたにもかかわらず、霊的には盲目でした。
一方で、何も見えないはずの盲人たちは、イエス様が誰であるのかを正しく理解していました。自分の姿を知り、イエス様を知り、だからこそイエス様に信頼することができたのです。その結果、彼らは見えるようにされました。
つまり、「見えているはずの者が見えておらず、見えていないはずの者が見えるようになった」という、明確な対照がここに示されています。
このことは、私たちにとっても重要な問いかけではないでしょうか。
私たちは、本当にイエス様が見えているでしょうか? 本当にイエス様の御心を知っているでしょうか? もしかすると、私たちも見えていないかもしれません。
私たちは、いつもイエス様のそばにいるはずです。礼拝に集い、神様の御声を聞いているはずです。しかし、本当にどれほど主が見えているでしょうか? どれほど御声が聞こえているでしょうか? どれほど御心を理解しているでしょうか?
もしかすると、私たちも霊的に盲目になっている部分があるのかもしれません。
だからこそ、私たちもこの二人の盲人のように、「主よ、目を開けてください」と祈る必要があるのではないでしょうか。
「主よ、あなたの御心をよく理解できますように。あなたの素晴らしさがよく見えるように。」
このように願うなら、私たちは神様との関係に満たされるはずです。他人と比較してどうかとか、先に行ったか後に行ったかといったことで心を乱されるのではなく、ただ神様との素晴らしい関係に生きることができるのです。
この記事から学ぶべきことは多いですが、何よりも「見えるようにしていただくこと」「正しい方向に向かうこと」が重要です。私たちは、それを求めて祈るべきではないでしょうか。
そして、主は必ず導いてくださるお方です。
弟子たちは当初、見えていませんでした。しかし、この後、彼らも見えるようになっていきます。主の導きによって、霊的な視力を回復させられていくのです。
私たちもまた、主の導きを信頼し、祈り続けていきたいと思います。
さて、これで20章は終わりました。ここまでにしたいと思います。
(そうですね……私たちの考えでは、家族を捨てて行くという決断は、なかなか理解しがたいものかもしれませんが……。)
お母さんは、もしかしたら息子のことが心配だったのかもしれません。母親として、それは当然のことですよね。心配で、もしかするとついてきたのかもしれません。
はい、まだ皆、十字架を見ていないんですよね。実際に見たとき、人はやはり変わっていくのだと思います。今はまだ、その前の段階ですので、十字架と出会う前の人間の生身の姿が表れているのでしょう。
女性たちもまた、そのようにして救いへと導かれていく。そのような展開につながっていくのかなと思います。
それでは、これで終わりたいと思います。学びをありがとうございました。
お祈りをします。
見えているようで、実は見えていないことの多い私たち。
そして、自分の思いにとらわれ、自分本位な信仰になりやすい私たちを、どうかお許しください。
御言葉の導きを通して、自分の姿を知らされることも、また恵みであることを感謝いたします。その中で悔い改め、あなたへの信頼へと導かれていきますように。
そして、確実に死の方向へと導いてくださる、あなたの導きがあることを感謝いたします。
心を注ぎ出して祈り続けることができるように、私たちの信仰の歩みを励まし、支えてくださるようお願いいたします。
感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。